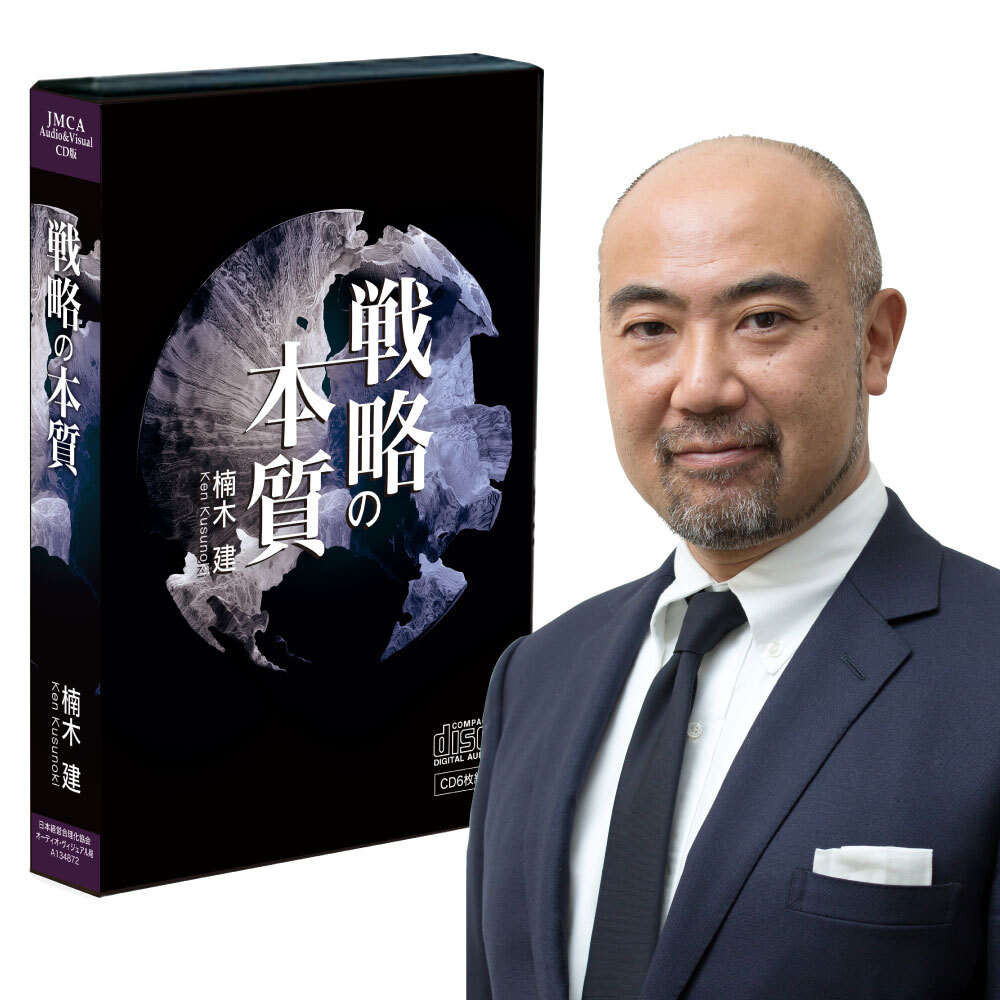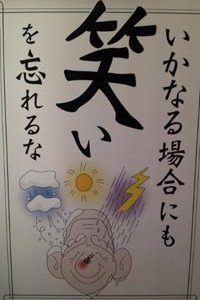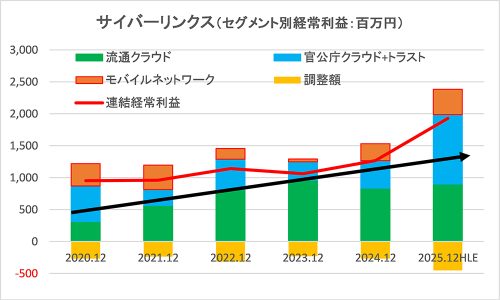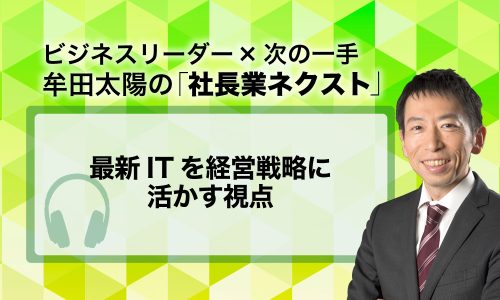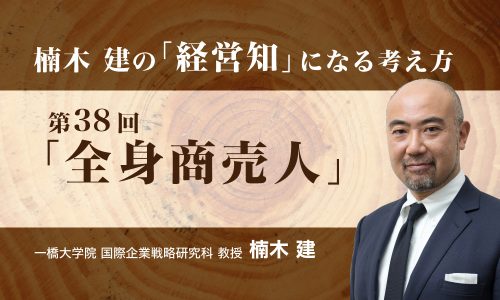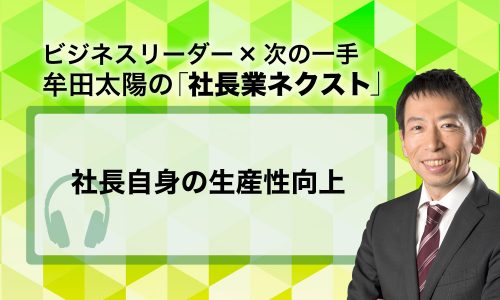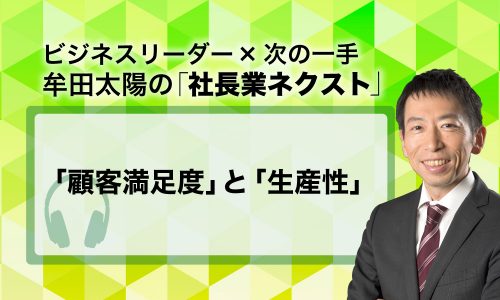優れた業績をあげる人はどのように仕事をしているのか?
モートン・ハンセンという人が『Great at Work』という本で「優れた業績をあげる人はどのように仕事をしているのか」という普遍にして不変の問題に対して包括的な議論をしている。
若かりし頃のハンセンは優秀な若者によくあるパターンをたどった。ビジネススクールでファイナンスを専攻して修士号を取得し、一流のコンサルティング・ファームに職を得た。野心と向上心満々の著者はハードワークこそ(とくに経験に不足するキャリアの初期段階では)業績をあげるカギだと考え、以来3年間、週に90時間も働くという仕事漬けの生活に突入する。
ところが、である。ある企業買収のプロジェクトで悪戦苦闘しているとき、ハンセンはその後長く引きずることになる「ナタリー問題」に直面する。ナタリーというのは同じプロジェクトで仕事をしていたチームメートの名前。彼女の分析をまとめたスライドは、簡潔明瞭にしてアイデアに溢れ、首尾一貫した説得力があり、美しかった。著者は彼女の仕事が自分よりも優れているという事実を認めざるを得なかった。
しかも、ナタリーは決して残業をしないことで知られていた。仕事は午前8時から午後6時まで。休日出勤もゼロ。
このことを知ったハンセンは大いに動揺する。二人とも優秀であり、コンサルタントに求められる分析能力を持っている。実務経験が浅いことも共通している。しかし、ナタリーは明らかに少ない時間でよりよい仕事をしている。つまり、一生懸命働いているのではなく、「賢く働いている」のである。
賢く働く…「ナタリー問題」の答え
「賢く働く」とはどういうことか。ハンセンは「ナタリー問題」に答えを出す大規模な調査プロジェクトを立ち上げた。数百の学術論文を精査することによって既存の知見を検討し、多数のプロフェッショナルとのインタビューを経て仮説を精緻化し、最終的にはアメリカのさまざまな業界業種のマネジャーと従業員から5000人を抽出してサーベイを実施した。サーベイの対象となった職種は、コンサルタントや弁護士、医師といった高度専門職だけでなく、トレーナー、プログラマー、商店店長、工場長、看護師からカジノ・ディーラーまで多岐に渡る。
5000人分のデータセットを回帰分析にかけたところ、何が業績に大きな影響を与えるかと同時に、たいした影響を与えない要因は何かが明らかになった。学歴や在職期間、年齢、性別といった(しばしば取りざたされる)人口統計学的要因は業績の差の5%以下しか説明しなかった。
もっともインパクトがあったのは、「することを減らす」だった。賢く働く人々は、優先すべきことを厳選し、選んだ分野に強いこだわりを持ち、努力を注ぎ続けている。事実、データの分析結果でもこのファクターがもっとも業績を左右している。
「することを減らす」ことは、働き方改革そのもの
このところ日本では、生産性向上のための「働き方改革」が叫ばれている。労働時間の削減は「働き方改革」の文脈で頻出するテーマだ。
長時間労働というと日本に特徴的な問題であるかのような先入観がある。しかし、ハンセンが調査したアメリカでも事情はそれほど変わらない。とくに高額所得のプロフェッショナルやマネジャーに限定してみれば、日本と同等かそれ以上のハードワークが常態となっている。
ハンセンのプロフェッショナル1000人を対象とした調査では、94%が週に50時間以上働いている。週に65時間以上(ということは、週5日仕事をするとして、毎日13時間以上)働いていると回答した人々が50%もいた。高所得者についての調査では、35%の人が週60時間以上働き、10%は実に80時間を超えていた。
たしかに労働時間が長くなるほど業績は向上するが、一定の限界がある。正の相関がみられるのは週当たり労働時間が30時間から50時間までの間で、それ以上になると業績は横ばい、65時間以上になると逆に労働時間が長くなるほど業績は低下する。
生産性向上の本丸はあくまでも「分子」
労働時間の短縮は日米ともに「働き方改革」の主要テーマだ。一見すると「することを減らせ」という本書のメッセージはこれと軌を一にするものであるように聞こえるかもしれない。しかし、著者が展開する「賢く働く」という主張はこれとは似て非なるものだ。
生産性とはバランス指標、つまりインプット(例えば労働時間)を分母、アウトプット(業績や成果)を分子とする分数である。確かに「時短」は分母を小さくすることによって生産性を改善しうる。しかし、それによって分子が小さくなってしまっては元も子もない。
生産性向上の本丸はあくまでも分子にある。アウトプットの最大化が本筋であって、インプットはそもそもアウトプットのための手段に過ぎない。「とにかく早く帰れ」「残業はするな」「職場をホワイト化しろ」という昨近の「働き方改革」の掛け声は、手段の目的化を引き起こしかねない。
「することを減らす」が分母を小さくするだけでなく、分子を大きくするのはなぜか。これについてはまた次回。