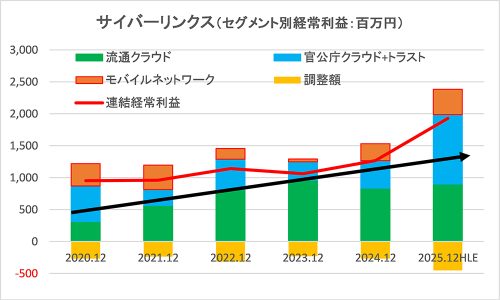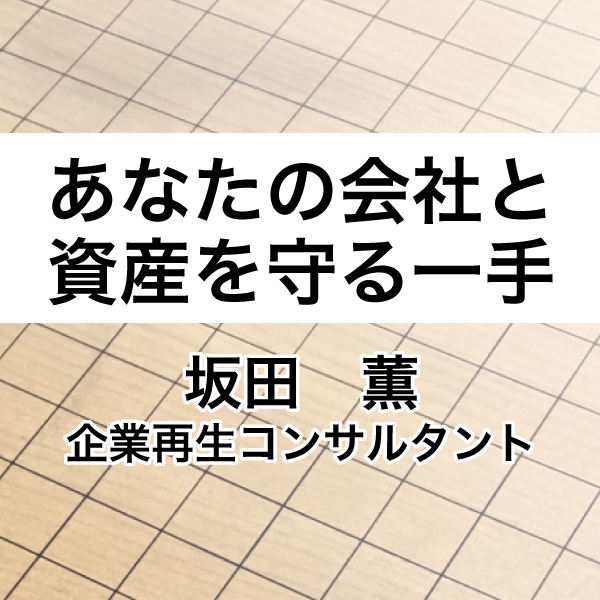丹羽宇一郎の信用を獲得する三原則「TDR」
前世紀末に伊藤忠の変革をリードした名経営者、丹羽宇一郎氏の話を続ける。
失敗したと思ったときは素直に認めてバッサリと切るのがイイ。未練たらしく引きずっていてもイイことはない。精神的にもすっきりするし、社員にもわかりやすい。負け戦の処理ほど疲れる仕事はない。そのエネルギーは新しい商売に向けたほうがイイ――。
決断しても人がついてこなければ実行できない。すなわち経営者は信用されていなければならない。丹羽さんは信用を獲得するための3原則「TDR」を掲げている。
- Transparency:経営の透明度を高める
- Disclosure:社内外に適切に情報を公開
- Responsibility:トップが社員や市場に説明責任を果たす
企業トップが説明責任をいかに果たすか
ガバナンスの関連でTやDは必ず出てくるトピックだが、肝心なのはR。どうしてこういうことをやる/やらないのか、社会や社員に対してトップ自らが理由を説明することが何よりも重要だ。これができない経営者は結局のところ信用されない。
前回も話したように、丹羽さんは伊藤忠の社長時代にとんでもない決断をしている。当時、伊藤忠はバブル崩壊の後遺症を引きずっていた。不動産などの不良資産を抱えて大幅赤字に転落。社内の役員や銀行は10年、20年という時間をかけて少しずつ償却し、不良資産を処理するというソフトランディングを主張したが、丹羽さんは一括処理に踏み切った。
ソフトランディングの道を選んでしまえば、社員がいくら一生懸命働いても、利益は不良資産に吸い取られてしまう。給料も増やせない。新規事業にも投資できない。配当もできない。社内が暗くなるーー覚悟を決めた丹羽さんは1990年に不良資産を一括処理し、4000億近くの特別損失を計上した。バブル後遺症に苦しむ日本企業の中で、これだけの規模の現存処理をした会社は伊藤忠が初めてだった。
このとき丹羽さんは会社初の社員集会を開いている。旅費がかかる社員には会社が費用負担して全員集める。そこで会社の状況と意思決定の理由を包み隠さず説明する。TDRの原則に忠実に行動した。
人間に流れている「動物の血」を制御する
丹羽さんは人間に流れている「動物の血」を理解するべきだと言う。人間の弱さ、むき出しの欲、保身、妬み、嫉み、業――こういったものをひっくるめて「動物の血」と表現している。「理性の血」が「動物の血」を制御しているのだが、人類文明の発症以来たかだか1万年。猿人以来の動物の血が人間には脈々と流れている。こっちの血の方が濃いのは間違いない。だからこそコーポレートガバナンスが必要になる。
不良債権の一括処理を行うにあたって、丹羽さんは特命チームを立ち上げ、各事業や資産の実体を解明するところから始めた。徹底的に調べると、想定を超える損失が続々と出てくる。人間は自分の出した損を自己申告するときに、自己保身という「動物の血」が体を走る。露見しなければイイとばかりにできるだけ小さく報告する。これに対して利益の額が後から増えることはない。「私がやりました」とわれ先に報告するので最初にドーンと出てくる。
3期連続赤字の子会社はほとんどすべて整理した。整理した子会社は450社に上った。企業年金積立金の金利が6%もあったので、これを3%に引き下げ、イヤな人には積立金を引き取ってもらう。お願いをしたOBの大半はこれを拒否し、「社長の一存でそんなことをやっていいのか」と抵抗した。
丹羽さんは社長OBへの給与支払いを75歳で打ち切り、自分の代からこの制度を全廃している。当時の伊藤忠には歴代社長の給料を死ぬまで払い、黒塗りの車と秘書を用意するという制度があったそうだ(伊藤忠に限らず、当時はそういう会社は多かった)。当然OBは反対する。「これからの人生設計が狂う」――これに対して丹羽さんは「若い社員の方がこれからの人生はずっと長いんだ。会社をこんな風にしたのはあなたたちではないか」
役員が射程距離に入っている人は「役員にならなくてもいいので積立金はそのままにする」ということなら受け入れると言ったところ、一人も役員辞退者は出なかったそうだ。すべては動物の血がなせる業。動物の血はなくせない。企業にガバナンスが欠かせない理由もここにある。