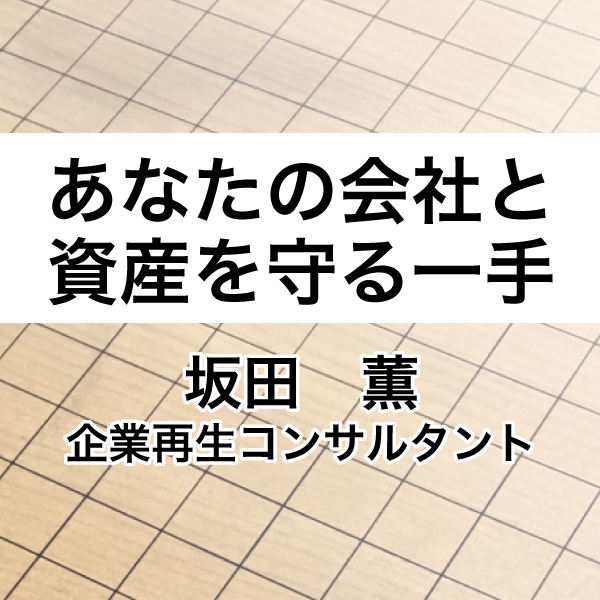孟子の説く外交の要諦
中国の戦国時代、西方の秦国と並んで天下を争った東方の斉国の宣王(せんおう)は、学問を奨励し各国から学者を集め、富国強兵の道を探っていた。重用された学者の一人に孟子(もうし)がいる。
ある日、宣王は孟子を呼んで「隣国とうまく交際するのに、何かよい方法はあるか」と、外交の秘策を訪ねた。
孟子は答える。
「ございますとも。こちらが大国でたとえ隣国が小国でも、決して侮らず礼を尽くして付き合うのが肝心です。また、反対にこちらが隣国に比べて小国なら、たとえ圧迫されてもこらえて大国につかえ、国の安全を図ることです。よく小国と付き合う君主は天下を保つことができ、身の程を知ってよく大国に仕える君主は自分の国を保つことができます」
侮らず、驕らずということである。外交のみならず個人の交際、組織の対応でも同じだろう。
小勇と大勇
当たり前といえば当たり前、優等生の回答ではある。へりくだってばかりではないか。宣王は納得しかねた。
「ご立派な意見ではあるが、私には少々、悪い癖があってな」。血気にはやるところがあって、そんな聖人君子の真似はできそうにない、と言葉を返した。
「王様、普段から刀の柄(つか)に手をかけて相手を睨みつけ、『お前なんか大したやつじゃない』と力みかえって怒るのは、〈匹夫の勇〉(小人物の蛮勇)というものです。せいぜい一人を相手にする勇気です。王たるもの国を治めるための大勇を持っていただきたいものです」
漢の三傑の一人、韓信(かんしん)が若い時にチンピラに絡まれ、ぐっとこらえて相手の股を潜る屈辱を甘んじて受けた話を彷彿とさせる。
真の怒りを持て
孟子先生、単に〈長いものには巻かれろ〉と言っているわけではない。さらに故事を引いて王を説得する。
周の文王は、密国が理不尽な理由で隣国の莒(きょ)を侵略したときには顔を真っ赤にして怒り、大軍を差し向けて征伐した。同じく周の武王は、犯罪の横行には毅然として怒り征伐した。
「いずれも国の安全を保ち、民に安心をもたらすためのもの。こうした怒りであれば、国民も相手も王様の大勇を恐れるようになるでしょう」
その場の怒りに任せて、義侠を気取り小勇を誇ったことがなかったかどうか。筆者など、あの時、この時を振り返って、思わず赤面してしまうのである。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『孟子(上)』小林勝人訳注 岩波文庫
- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 故事成語に学ぶ(14)匹夫の勇(ひっぷのゆう)