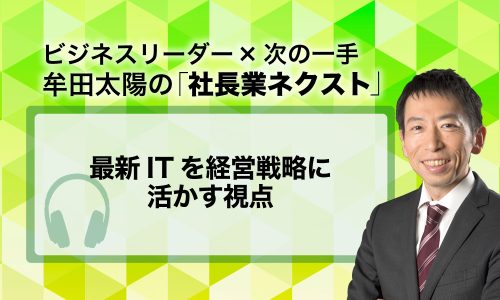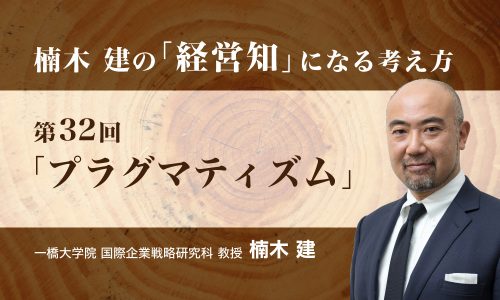- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 故事成語に学ぶ(15)賢(けん)を進むるには已(や)むを得ざるがごとくす
任命責任は重い
安倍政権で、閣僚級の不用意な発言による辞任が相次いでいる。その発言内容を聞けば、なんでこんな人物が要職に取り立てられるのかと、小学生だって唖然としてしまう。
安倍首相は、「任命責任はもとより私にある」と陳謝したが、ではなぜこんな人事がまかり通ってきたのか。派閥の力学の中でゴリ押しの人材推薦もあろう。年功序列への配慮も。しかしこんな人物が省庁の指導的立場に座って事足りると考えているとしたら、その根本的原因は、「どうせ大臣は飾りもの、政権は私が運用するからいい」という、国のトップの奢りでしかない。招いた結果は、国民から大きなしっぺ返しを食らうことになる。
高い神木よりしっかりとした家臣
孟子は、斉の宣王(せんおう)に会って、人材登用のあり方について講義している。まずは、国の存続の基盤について話しはじめた。
「しっかりとした国というものは、国の中心の鎮守の森に高い神木が聳えているだけではだめなのです。伝統ある国は、代々しっかりとした家臣に支えられているのです。新しいこの国ではそうした人材がおりません。王様が任命される臣下も、昨日とりたてたものが、きょう悪事を働くかも知れず安定しないのです」
首相もその先を聞きたいだろう。宣王も聞いた。「ならば、私はどうしたら臣下の才能のないものを判別して、任用しないようにできるだろう」
孟子は表題のように答えた。
「〈賢(けん)を進むるには已(や)むを得ざるがごとくす〉国のトップが有能な臣下をとりたてる時は、いかにもその人物でなければならないように、自然に行われないといけません」
人物判断は国民に問え
その人物でないとだめだという判断とは? 自然にとは? 孟子は続ける。「位の下の賢者を上の位のものを超えてとりたて、また遠い分家筋のものを本家のものを越えて採用することもあるでしょう。だから慎重さが必要です」。今流でいえば、優秀な人材を集めようとするなら年功序列や派閥の推薦を無視すべきということだろう。そして孟子の講義は王の問いへの回答にたどり着く。
「王様の側近が推薦しても、高官たちがいいだろうと言ってもそれだけではいけません。国民たちが口を揃えて優れているといい、調査の上で王様が人物を見極めたのちに、これを任用なさいませ」。
逆の場合も同じ手順を踏めと孟子はいう。側近、高官がある人物にだめを出してもすぐに聞き入れるなと。国民がみなだめだといい、王様が調査してだめなことを見極めて免職せよと。
孟子先生の言は、二千年以上経っても決して古くない。それだけ人事登用はいつの世にも厄介であり、かつ重要なのである。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『孟子(上)』小林勝人訳注 岩波文庫
『孟子』貝塚茂樹著 講談社学術文庫