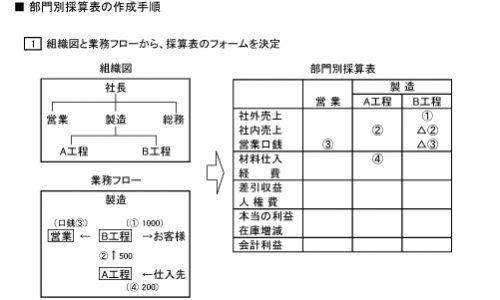日米繊維交渉を前に、
ケネディは、主要繊維製品の対米輸出伸び率を年間5%
「この案をのまなければ、大統領は『対敵通商法』
うむをいわせず、かつて第二次大戦時に制定しドイツ、
田中はケネディを睨み返して言った。
「わが国の繊維産業連盟は7月から輸出を抑える自主規制を始め、
就任時に官僚たちから聞かされたシナリオにそって、まさに「
脅しに堂々と原則で蹴り返した田中に官僚たちも業界も、「
どんな組織でも新たなリーダーを迎えたときに、「さて、
しかし交渉ごとである。相手が存在する。
秘密折衝を含めて米国の出方を、ケネディの言葉の端々から探る。
米国内では、対敵通商法適用の準備が進んでいた。期限は10月中
「まずは原則でぶつかり合う。敵(米国)は、
早期妥結のシナリオはできた。「あとは準備だ、あくまで内密に。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※ 参考文献
『早坂茂三の「田中角栄」回想録』早坂茂三著 小学館
『田中角栄 頂点をきわめた男の物語―オヤジとわたし』早坂茂三著 PHP文庫
『田中角栄の資源戦争』山岡淳一郎著 草思社文庫
『日米貿易摩擦―対立と協調の構図』金川徹著 啓文社