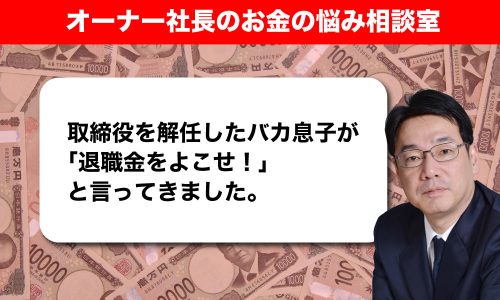「勲功に値せず」
11世紀前半に対馬・壱岐から北九州沿岸が異賊に襲われた刀伊(とい)の来襲は、太平の眠りを覚ます未曾有の危機であったが、それを撃退したのは九州現地の守りを固める太宰府の長官職にあたる権帥(ごんのそち)だった藤原隆家(ふじわら・たかいえ)と、彼の指揮下にあった九州在地の武士たちだった。彼らにはどんな論功行賞が行われたのだろうか。
戦功に対する恩賞が朝廷で論じられたのは、戦後二か月が経った寛仁3年(1019年)6月29日のこと。隆家は指揮官クラス12人の戦功を上申していたが、口火を切った大納言の藤原公任(ふじわら・きんとう)は、「あっという間に終わった戦いで、勲功に値せず」と言い放った。「朝廷が恩賞を約束した時には、すでに戦闘は終わっていた」というのが理由だった。和歌に遊興に明け暮れる都の公卿たちには、この程度の危機感しかなかった。
これには、同じく大納言の藤原実資(ふじわら・さねすけ)が、さすがに見かねて、「もしここで恩賞が下されなければ今後、奮闘する者など出てこない」と諌めて、ようやく「恩賞を下す」ことで決したが、具体的な沙汰は示されなかった。
ちぐはぐな対応
その後の叙任文書には、博多防衛にあたった武士一人が、壱岐守に任命されたが、他の11人の恩賞の消息は書かれていない。最大の功労者である隆家には何の沙汰もなかった。昇進もなく京都へ呼び戻されている。
同じ日付の叙任文書には、奇妙な人事が載っている。異族の来襲を知った後、後一条天皇の岩清水八幡行幸に供奉した大納言実資に位一階の昇進が与えられている。「怨敵退散」の祈祷の効果が評価されたのだろう。
なるほど、隆家から一報を受け取った直後の公卿会議では、京都への街道の防備を固めることを指示するとともに、有力寺社に祈祷を命じている。藤原一族が取り仕切った平安王朝時代の政治(まつりごと)とは、まさに、危機回避は神に頼むという「祀りごと」優先だった。
朝廷周辺の事後処理にはさらに奇妙なことがある。北九州を襲った勢力が、当初朝廷が疑い恐れた隣国の高麗の指し金ではなく、北方女真族の海賊だったと判明したのは、事件後に小舟で高麗に渡った対馬島の役人が帰国後に太宰府に報告した情報によるものだった。しかも彼は帰国に際して刀伊に連れ去られた捕虜を高麗と交渉して連れ帰ってもいる。隣国外交の功労者だ。ところが、彼の行為は、外国への渡航を禁じている鎖国政策に違反しているとして、太宰府に彼の拘禁を命じている。
危機から生まれた隣国高麗との外交のチャンスの糸口をみすみす取り逃した。なんともちぐはぐな、というかトンチンカンな対応を見せている。
内なる危機
京都に戻った隆家は、朝廷にも出仕せず昇進もなく半ば軟禁状態で過ごす。朝廷周辺の公卿たちが刀伊の来襲で懸念したのは、内政の危機だったのだろう。外敵を相手に戦った隆家と在地武士団へのつれない対応も、内なる武力である武士たちが力をつけることを恐れ、また朝廷と距離を置く隆家が彼らと手を結べば、その力が朝廷に向かうかもしれないと恐れたのか。
筆者の時代の歴史教科書では、平安王朝時代について、「中国、朝鮮半島との交流が制限されたことで、独自で豊かな国風文化が花開いた」時代だと習った。だが、「独自で豊かな」というのは、京都、しかも朝廷周辺に限られたことで、公卿たちの関心は、朝廷というコップの中の権力争いであり、地方で何が胎動し始めているかは興味の外だった。
100年後、朝廷の護衛部隊程度にしか評価していなかった武士たちが、地域に根を張り、経済力をつけ始める。朝廷のボディーガードであったはずの平清盛が保元、平時の乱を勝ち抜いて、朝廷を凌駕する政治力を身につけて、日宋貿易に乗り出すのは、歴史の必然なのだ。(この項、次回に続く)
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『刀伊の入寇 平安時代最大の対外危機』関幸彦著 中公新書
『日本の歴史5 王朝の貴族』土田直鎮著 中公文庫
『日本の歴史6 道長と宮廷社会』大津透著 講談社学術文庫