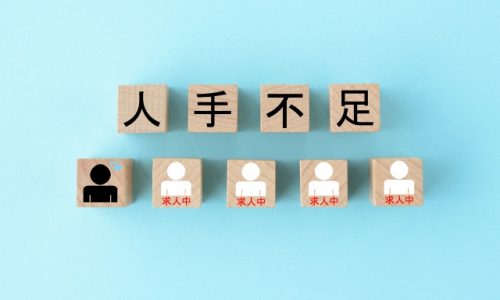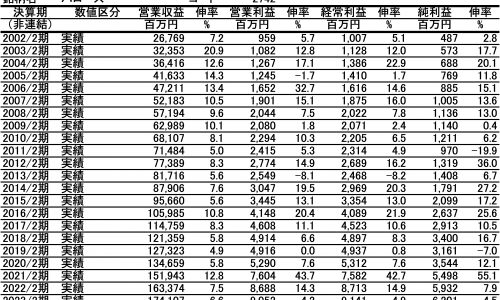国家と個人の関係を見直す
英国とアルゼンチンの間でフォークランド紛争が勃発した1982年4月、機動艦隊を出撃させる決断を下した英国首相のマーガレット・サッチャーは、最後まで開戦に難色を示す会議メンバーに、「この場に男はいないのか」と言い放ったという逸話が残されている。英国憲政史上初の女性首相として、「鉄の女」というジェンダー的な興味で語られることの多いサッチャーだが、彼女の偉大さは、強い女であることではなく、英国が直面していた危機の真の意味を見抜く力と、その処方箋を示し実行し、成功させたことにある。
1979年5月、サッチャーは保守党党首として総選挙に勝利し、労働党から政権を奪還して第71代首相の座に就いた。当時、英国を取り巻く政治、経済、社会の状況は立ち直り不可能とも見えるほど惨憺たるものだった。
インフレは進行して27%に達し失業者が溢れている。政治は打つ手を失っていた。首相官邸の主人となった彼女は、表面の数字ではなく、背景にある真の大きな問題に着目していた。国家と個人の関係だ。その見直しが不可欠だと見据えていた。「これは私にしかできない。私はやる」と決断した。
遠因は、勝利したとはいえ国家経済に壊滅的な打撃を被った第二次世界大戦からの復興のための政治理念にあった。戦後の英国政治は、疲弊した国民生活を立て直すため、国民健康保険制度と完全雇用を柱とする福祉国家建設を理想に据えた。さらに電気、ガス、水道などのインフラ事業を次々と国有化していく。労働党政権時代には、鉄鋼、造船、自動車など主要産業まで国有化の動きが広まった。高級車で知られるロールスロイス社まで雇用重視の観点から国有化された。そのために膨大な国費が注ぎ込まれる。
こうした「大きな政府」の発想は、保守党内部でも当然のこととして受け入れられていた。サッチャーは野党時代からこの根本的な「国家と国民」の構図に異を唱えたのだ。
矢継ぎ早の改革着手
おんぶに抱っこの経済政策は、労働組合の発言権も増大させ、1970年代にはストライキが多発し、企業の生産効率は大きく下落し国際競争力を失っていった。非効率な戦後体制からの脱却を目指して就任したサッチャーは次々と聖域に切り込んでいく。
国有企業を矢継ぎ早に民営化し、労働組合の力を削ぎにかかる。企業の活性化のために所得税と法人税を引き下げ、逆に消費税は8%から15%へと引き上げて税収バランスをとる。こうした強硬で強引な姿勢は当然、国民の反発を呼ぶ。就任二年目の1979年の冬は、労働争議が多発し、「不満の冬」として人々の記憶に焼きついている。
選挙が怖い普通の政治家、ポピュリストならこうした政治手法はとらない。妥協しながら時間をかけるが、それでは危機はより深化する。サッチャーは、国民に不人気でもやり通す信念があった。「我慢が必要だ。この先に光明はある」と国民に訴えながら。
サッチャーは、自らを「確信の政治家」と自称していた。信念が通じて、現実にインフレ率が下がり、企業の生産性は高まり、経済苦境から脱却をはじめる。その時、国民はついてくる。保守党は、三度の総選挙に勝ち、サッチャー政権は1990年11月に退陣するまで11年半の長きにわたった。国民は彼女の信念に国を託したのである。
理想と現実のはざまの政治術
国民の甘えを許さず「小さな政府」を目指す手法は、「新保守主義」として、その後の日本でも国鉄分割民営化など公共機関の改革で成功し脚光を浴びたが、サッチャーが成果を生み出すまで、経済理論では存在しても、実践例はない。日本でも「サッチャーを見習え」が改革の掛け声となった。
もちろん、危機にあたって従来の常識、慣行を打ち破って大胆な改革を導くには、理想を思い描き確信するだけでは達成できない。官僚、国民をリードする巧みな行政手腕があればこそできることだ。サッチャーが抵抗を排除しながら理想に向けて政策を実現するためにとった現実的な政治手法とは、どのようなものだったのか?
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『サッチャー回顧録(上・下)』マーガレット・サッチャー著 石塚雅彦訳 日本経済新聞社
『マーガレット・サッチャー 政治を変えた「鉄の女」』冨田浩司著 新潮選書