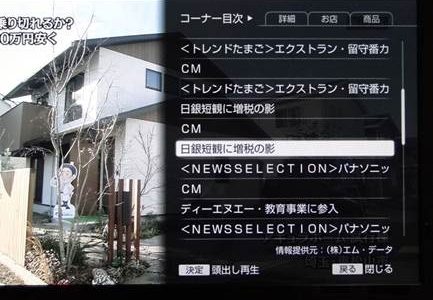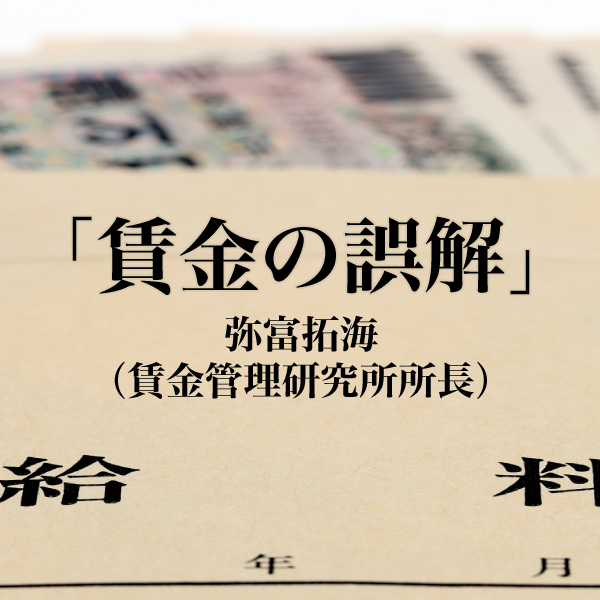二・二六事件後の軍による露骨な組閣干渉
五・一五事件(1932年)、二・二六事件(1936年)と続く青年将校らによる反乱事件を経て、1930年代の日本は軍部独裁の暗黒時代に突入する。
二・二六事件によって岡田啓介(おかだ・けいすけ)内閣は総辞職し、外務大臣の広田弘毅(ひろた・こうき)に組閣の大命が降った。軍内を抑えるために軍部から宇垣一成(うがき・かずしげ)大将を推す声もあったが、選考にあたった元老らは、喫緊の課題は満洲問題に端を発した日中外交にあるとして、和平派の広田に期待して起用した。クーデター騒ぎの後の対外イメージにも考慮し文民を立てた。
しかし、組閣作業に入ると軍の干渉は露骨だった。広田が外相に予定した吉田茂(戦後に首相)ら四人の入閣を、「自由主義的すぎる」として拒否する。広田は一時、組閣を断念するほどの圧力だった。陸相、海相以外の閣僚ポストに軍がいちゃもんをつけるのは前例がない。
もはや国を率いる首相に、軍部を抑えるリーダーシップは失われたのである。
「統帥権」という名の怪物
軍が政府を超える権力を持ち始めたのは、1930年のロンドン軍縮会議で、濱口雄幸(はまぐち・おさち)内閣が、軍部の反対を聞かずに英米主導の軍縮案を飲んだことにあった。「これで国が守れるのか」と不満を募らせた軍部は、「軍の統帥権は天皇のみが持つ大権である。政府がそれに手を出すのは統帥権の干犯(侵犯)である」と厳しく批判した。
たしかに、明治憲法では、「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」(第11条)と定められている。軍の作戦立案、行使の判断は天皇に委ねられているが、一方で、「天皇の権限は、国務大臣が輔弼(ほひつ=助言補佐)する」とあり、実質的な権限は政府にあると見るのが、明治憲法の正しい読み方である。天皇には実質的な権限はない。それを拡大解釈して、天皇を隠れ蓑にして「軍の行動に政府は口を出すな」と極端な解釈が罷り通るようになる。1930年代に入って、「統帥権」は、政府の枠を離れた軍の特別な地位を保証する「怪物」として一人歩きするようになる。
軍が全てを決める。政府の口出しは無用。この論理の行き着く先が、関東軍による満州国の建国を起点とする中国大陸戦線の拡大という暴走につながり、英米への宣戦布告、国家滅亡の危機を招いてしまう。
批判を封じる政体は滅びる
国防のための軍は、国家において唯一の暴力装置だ。その装置が政府の枠から外れ、あるいは政府で制御不能となった場合、暴走する。暴走する軍は政府を意のままに動かして国民の批判を封じにかかる。
「天皇機関説」で有名な明治憲法学者の美濃部達吉(みのべ・たつきち)は、統帥権干犯が問題になったロンドン軍縮条約批准に際して、「兵力の決定は統帥権の範囲外であるから、内閣の責任で決定するのが当然だ」として濱口政権の判断を支持した。さらに美濃部は相次ぐ右翼テロに対して、政府の右翼取締りが甘すぎると非難したが、のちに貴族院議員を逐われる。
政党も口をつぐむようになり、中国進出を批判する民衆も「アカ」(共産主義者)として、特高警察に摘発、拘束されていく。
それをはねのけて国家を主導するリーダーシップが、政党にも、財界にももはや存在しない時代だった。権力を手中にした軍にも国益を冷静に判断できるリーダーシップはない。
危機にあって、批判世論を封じることがリーダーシップだと考えるような政体は、いずれ滅んでゆく運命にある。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『日本の近代5政党から軍部へ』北岡伸一著 中公文庫
『日本の歴史24 ファシズムへの道』大内力著 中公文庫