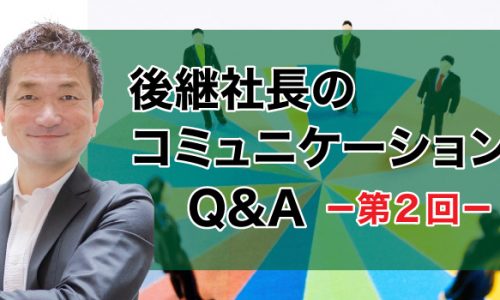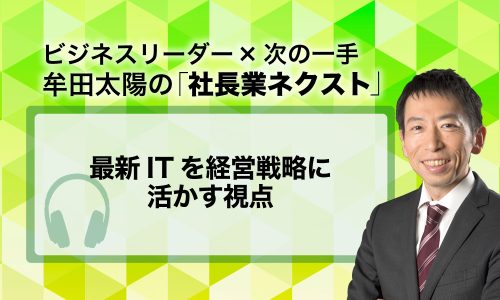婦人参政権
6月2日に行われたメキシコ大統領選挙で、与党系女性候補のクラウディア・シェインバウムが約60%の得票を集め、初の女性大統領に当選を確実とした。1953年に女性参政権が認められた同国では、議会の女性議員はおよそ半数を占めており、当然の帰結でもある。
シェインバウムは、勝利宣言で女性全体の勝利であると強調した。
「私はひとりでここにたどり着いたのではありません。私たち女性は一緒にここまで来ました。国を作った女性の英雄たち、私たちの母たち、娘たち、そして孫娘たちです」
彼女は、2018年から5年間、首都メキシコ市の市長をつとめ政治実績を積んできた。
人間社会の半分は女性が支えている。今、世界的に女性の地位の見直しが進められているが、政治の世界一つをとっても日本の女性参画比率は、先進国でも最低レベルだ。
来月に行われる東京都知事選は、事実上、女候補の一騎打ちとなりそうで注目を集めている。しかし、国会における女性議員比率は、衆議院が11.3%(54人)、参議院は17.4%(42人)にとどまっている。
このアンバランスこそが、政治を窮地に追い込んでいるとしか思えない。「政治は力の論理で動く。女には政治は無理」という男社会の思い込みが、生活者としての女性の発想と活躍を排除している。であるが故に、政治資金うら金問題でも国民の怒りに気づかない与党の迷走に振り回されている。「数で押し切れば、国民は黙ってついてくる」。これが明治以来あいも変わらぬ男社会の論理なのだ。
「青鞜」の創刊
「女は男の従属物である」という男社会の強固な思い込みに対して叛逆の狼煙をあげたのが作家の平塚らいてう(らいちょう)だった。明治末年(1911年)、女性のアイデンティティ回復を目指して、女性による、女性のための雑誌「青鞜(せいとう)」を発刊する。その創刊の辞で平塚は書いた。
「元始、女性は実に太陽であった。真正の人であった」。その自ら光輝く太陽であった女性たちが、他の光(男)によって青白く輝き、生きるだけの月になってしまった。自律的に生きる人となれ、と女性たちに呼びかけた啓蒙の一文だ。結社には、歌人の与謝野晶子らも参加した。
「青鞜」とはブルーのストッキングのことだ。英国のフェミニズム(女性解放運動)の活動家たちが、男好みの黒いストッキング着用を拒否し、青靴下を履き始めたことに由来する。ブルー・ストッキングの命名は、男たちによる、うるさく騒ぐ女性活動家に対する蔑視の意味が込められている。平塚らは、あえて青鞜を名乗ることで封建的な男たちに挑戦状を突きつけた。
案の定、男性社会は強く批判し、やがて雑誌は「伝統的な家族制度を危うくする」として発禁処分を受ける。若い女性たちは平塚らの運動を強く支持したが。
やがて、大正デモクラシーが盛り上がる中で、高額納税者に限定されていた選挙権を拡大する普通選挙法制定の社会運動が高揚する。平塚は、市川房枝(いちかわ・ふさえ)らの参加を得て、「新婦人協会」を結成し、「婦人参政権」と「母性保護」を求めて立ち上がる。
結局、女性に参政権がみとられるのは、戦後、戦勝国米国の軍政下まで、待たねばならなかったが、市川らは戦前、戦中もねばり強く女性の権利獲得運動を続け、昭和21年(1946年)4月の戦後初の総選挙では、39人の女性議員が誕生する。根拠なく男社会に屈従を迫られてきた女性の力が爆発した。
企業の女性登用の遅れ
政治場面だけではない。企業の女性役員登用率(2022年)についてみると、日本を除くG7各国の平均が38.8%なのに対して、わが国の全上場企業の平均はわずか9.1%に過ぎない。
政府は、2030年までに全プライム上場企業は、女性役員比率を欧米並みの30%に引き上げるように企業に促している。政府に言われるまでもなく企業のトップ自らが自覚して進める他ない。
平塚らいてうが男社会の打破を求めて立ち上がって113年。現状のままでは、「申し訳が立たない」どころか、政治も経済も激動の世界から取り残されていくばかりだ。
女になんか大事な会社を任せられるか―と考えているそんなあなたこそ、直ちにトップの座を辞すべき時だ。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
(参考資料)
『平塚らいてう』 その思想と孫から見た素顔』奥村直史著 平凡社ライブラリー
『元始、女性は太陽であった 平塚らいてう自伝』大月書店
『日本の歴史 23 大正デモクラシー』今井清一著 中公文庫
内閣府女性共同参画局資料