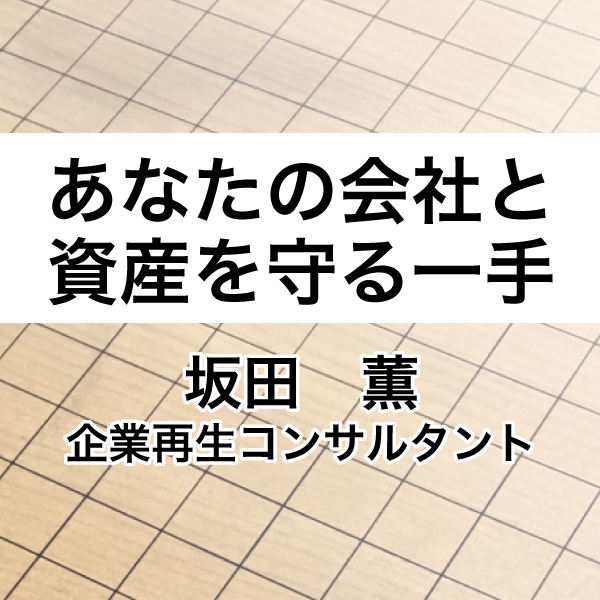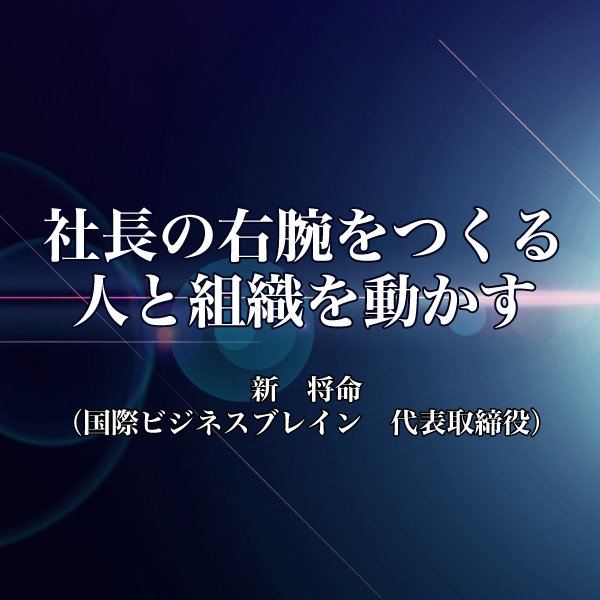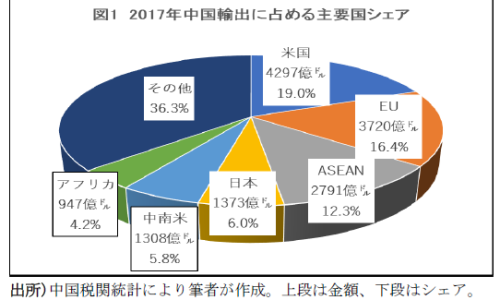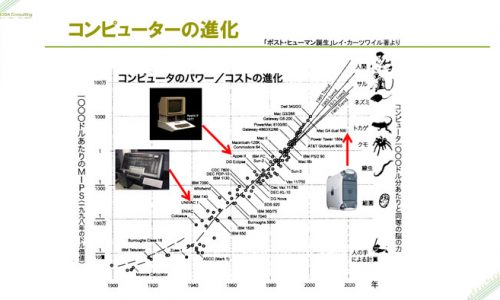太平洋最後の砦、硫黄島に赴任
ガダルカナル島に上陸した米海兵隊は、島伝いに日本軍守備隊を撃破しながら北上を続けていた。東京の近衛留守部隊の師団長だった栗林忠道(くりばやし・ただみち=中将、のち大将)が、硫黄島を含む小笠原諸島を管轄する109師団長として父島に赴任したのは敗色が濃くなりつつあった1944年(昭和19年)6月だった。
直後の7月にはサイパン島が、8月にはテニアン島が陥落し、米軍は11月から、両島を拠点にB29による本土直接空襲を強化する。米軍の次の上陸目標が日本の飛行場が整備されている硫黄島にあることは明らかだった。栗林の赴任に際して、首相の東條英機(参謀総長兼務)は、「(玉砕した)アッツ島のように見事に戦ってくれ」と送り出したという。だが、栗林は玉砕するつもりは毛頭ない。本土防衛のためにも硫黄島と飛行場を死守する覚悟だった。
大本営の幕僚からも、「師団長は後方の父島にとどまり指揮を取るように」とアドバイスがあったが、栗林は着任早々、師団司令部を硫黄島に移し、自らも同島に乗り込んだ。
水際作戦を捨て島を要塞化する
島に着いた栗林は、自らの足で指揮杖をついて歩き回った。島の地形を頭に叩き込んだ。大本営からの指令は、敵上陸場面で阻止する水際作戦だ。士官学校で叩き込まれる島嶼防衛のセオリーだが、制海権も制空権も奪われる中で、島々は水際作戦で失敗を続けている。最後は指揮官が銃剣突撃を命じて玉砕する。敗北主義である。
明治以降の日本の国家運営は、現場を知らないエリートによる官僚主義によって主導されてきた。軍も同様に、大本営に詰めるエリートたちが現場も見ずに机上で立てた作戦で失敗を繰り返している。栗林が島を死守するために必須と考えた航空兵力を含む連合艦隊の支援は、艦船の消耗が激しく日を追うにつれて絶望的となる。どうすれば、敵を迎え撃つことができるか。栗林は斬新なアイデアを実行に移す。島を塹壕と地下壕で結び要塞化することだった。
着任直後から23,000の守備兵を動員して掘らせた地下20−30メートルの地下壕のネットワークは総延長18キロに及んだ。戦車も車体を埋めてカムフラージュした砲塔だけを地上に出してトーチカとした。こうして徹底抗戦の態勢を整え、米海兵隊の上陸を待ち構える。
自らの足で地形を確かめ、島の南西端に摺鉢山が盛り上がるだけであとは平な土地が広がる硫黄島では、地下で戦うしかないと考えたのだ。
バンザイ突撃を禁じる
栗林は、扶養家族のない壮年男子以外の軍属と民間人全員を本土へ送還し、迎撃態勢を整える。そして「敢闘ノ誓」を作成し全軍に配布して戦いの方針を徹底させた。「我らは全力を奮って本島を守り抜く」から始まり、「我らは各自敵十人を倒さざれば死すとも死せず」「我らは最後の一人となるもゲリラに依って敵を悩まさん」。勇ましい言葉で書かれているが、日本陸軍の伝統とされるバンザイ突撃、やけくその斬り込み戦は無駄だから避けて「一人で十人の敵をやっつけるぐらい粘り強く敢闘せよ」と明示しているのだ。
栗林は、自ら島を歩き回りながら兵士たちに声をかけ、食事も兵士たちと同じものを食べた。斬新な作戦を立案する知的で柔軟な人柄に兵士たちは、親しみを感じていた。ただ「潔く死ね」と後方から命じるだけの当たり前の官僚的司令官では、訓示も徹底しない。
果たして米軍の海兵隊は、1945年2月19日、三日間の艦砲射撃の後、61,000人が上陸用舟艇で海岸へ殺到する。これまでの上陸作戦では、上陸地点で待ち構える日本軍を圧倒的な火器で制圧すれば5日で戦いは終わると考えていた米軍は戸惑う。上陸したがどこにも日本兵の姿が見当たらない。
戦闘の詳述は避けるが、トンネル網を駆使して上陸する部隊を狙い撃ちする日本軍の予想外の抵抗に、激戦は36日間に及んだ。栗林が、地下司令部で自決した後も、「遺言」によって、残兵によるゲリラ戦は続いた。 両軍の死傷者数は、日本軍21,000に対して米軍は25,000を数えた。米軍の数が上回った。
硫黄島の戦いの帰結は、米軍に大きな衝撃を与えた。当初計画していた日本本土への上陸作戦は、予想外の消耗戦になるとして見送られ、さらなる本土空襲の強化、ソ連への参戦要請、原爆の使用へと切り替えられたのだ。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『硫黄島 栗林忠道大将の教訓』小室直樹著 ワック
『昭和の名将と愚将』半藤一利、保阪正康著 文春新書
『日本の歴史 25 太平洋戦争』林茂著 中公文庫