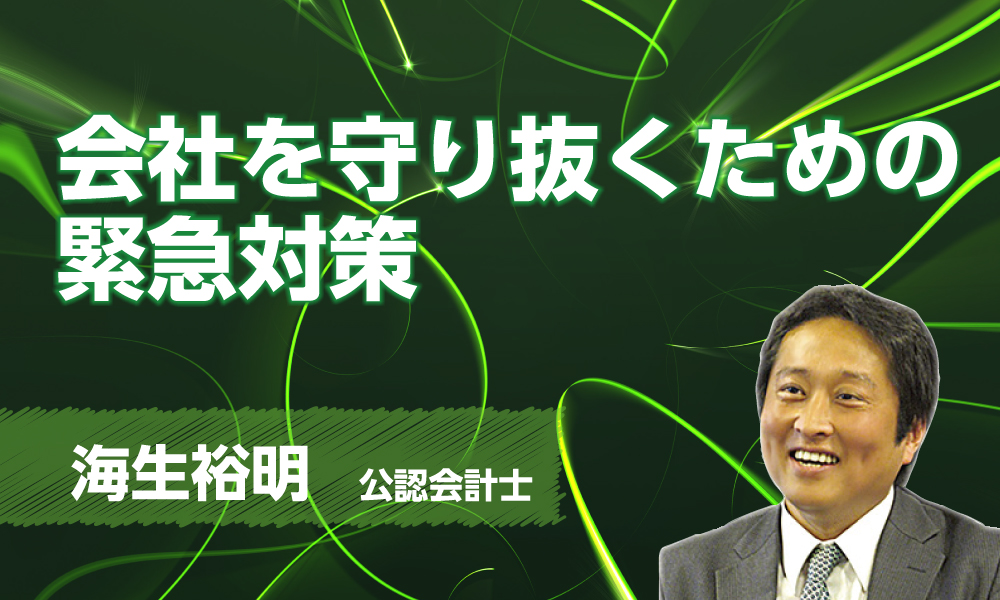欧州のへそ、もう一つの永世中立国
ヨーロッパの永世中立国といえば前回まで見てきたスイスがあまりに有名だが、東隣りのオーストリアも、第二次世界大戦後、ドイツの併合から出て独立を取り戻して以来、永世中立を宣言している。アルプスに囲まれたヨーロッパ中央に位置を占める二つの国が、いかなる軍事同盟にも属さず、他国軍の基地設置を認めず、政治的バランサーの役割を果たしている。
オーストリアと聞けば、音楽の都ウイーンを擁し、平和に包まれた国家のイメージがあるが、欧州の名家、ハプスブルグ家の支配によって、中世以来、政治的にも欧州のヘソとして大きな影響力を持ち、時代、時代に激動の歴史を経験してきた。
ドイツに翻弄されてきた20世紀前半
スイス発祥のハプスブルグ家は、13世紀にオーストリアに支配を及ぼし、神聖ローマ帝国の王位を占めてきた。巧みな婚姻政策によってヨーロッパ各地の王族と結びつくことで支配圏を広げる。女帝マリア・テレジアがハプスブルグ家を継いだ18世紀には、「日の沈まない帝国」の名を欲しいままにした。フランス革命で断頭台の露と消えたフランス王妃のマリー・アントワネットもマリア・テレジアの娘である。
西方への勢力拡大を図るオスマントルコの欧州進出を阻止した中心勢力もオーストリアだった。20世紀に入って二度の世界大戦では、同じ言語圏のドイツと結び、二度の敗戦を経験する。ドイツに翻弄された20世紀の前半だった。
皇太子夫妻がサラエヴォで暗殺されたことをきっかけに始まった第一次大戦に敗れた後には属領諸国が独立してオーストリア=ハンガリー帝国は崩壊。王制も廃止されてオーストリア共和国が成立した。しかし独立は長続きせず、1938年には、ナチスドイツに併合されてしまう。そして二度目の敗戦を経験することになる。
東西冷戦の緩衝地帯として
敗戦後のオーストリアはみじめなものだった。独立国としての敗戦ではなく、ドイツの属領の立場だったから、国土は、連合国の四か国(アメリカ、イギリス、フランス、ソ連)による分割統治下に置かれた。首都ウイーンも四か国の統治地区に分けられた。映画『第三の男』の舞台は、この分割占領下のウイーンだった。
占領軍統治による国家の解体は日本も同じだが、日本の場合は実質的には米軍の単独占領だった。オーストリアは四か国によって分割統治され、しかも国家としてはすでに存在しない状況での占領は、厳しいものだった。
さらに状況を複雑にしたのは、占領国にソ連が含まれていたことだ。ソ連も連合国の一員ではあるが、やがて終戦後の世界情勢は、資本主義と共産主義による体勢競争として東西冷戦に突入する。オーストリアと国境を接する国々は、ユーゴスラビア、ハンガリー、チェコスロバキアがずらりとソ連の影響下にある東側に組み込まれ、ドイツは東西に分割された。
オーストリアは、1955年に10年にわたった占領を解かれ独立する。そして憲法に「永世中立」を盛り込んだ。
もちろん、永世中立宣言は、激動する国際情勢に翻弄(ほんろう)されてきた国民の強い意思でもあっただろうが、主たる要因は、オーストリアを冷戦の緩衝地帯としておこうという大国の妥協の産物でもあった。
独立後のオーストリアは、資本主義社会に与しながら複雑なかじ取りを余儀なくされる。 (この項、次回へ続く)
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『オーストリア 永世中立国際国家』大西健夫・酒井晨史編 早稲田大学出版局