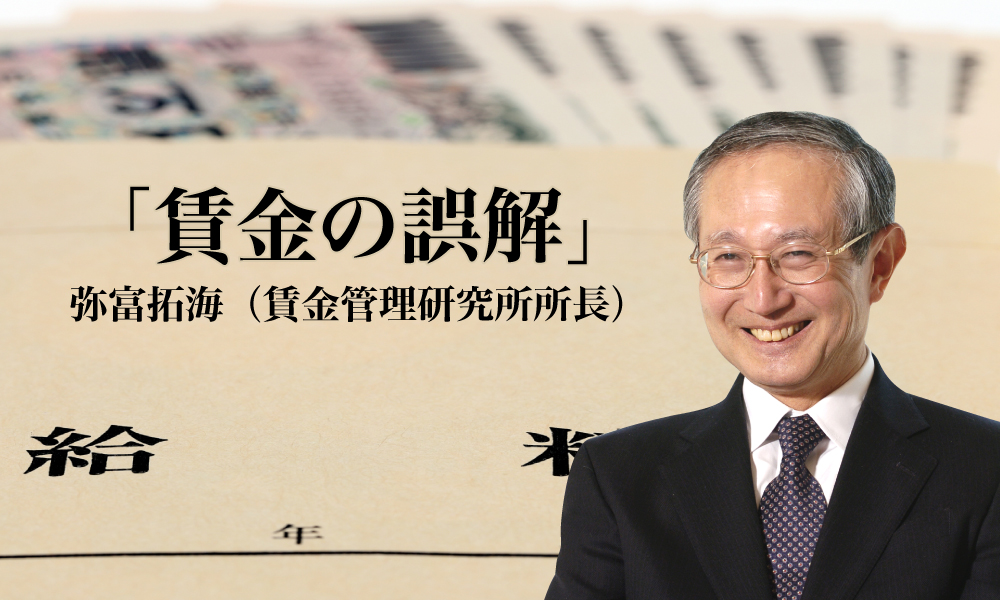- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 逆転の発想(10) 将の器が問われる撤収作戦(奇跡のキスカ島脱出)
玉砕と完全撤収
第二次世界大戦で日本軍は米国領土の二つの島を一年に渡って占領している。アラスカとカムチャッカ半島を繋ぐアリューシャン列島にあるアッツ島とキスカ島である。日本の陸海軍は1942年6月、ミッドウエイ作戦の陽動作戦としてほぼ無人の両島に上陸した。しかしミッドウエイの海戦で、日本の空母部隊は完敗し、両島占領は戦略的には無意味となった。北西太平洋の制海権を失った日本軍は、島への食糧、弾薬の補給もままならず、取り残された将兵は死を待つのみとなった。
翌年5月、米軍はまず、アッツ島の上陸奪還作戦を開始し、陸軍主体の島の守備隊は万歳突撃を繰り返し玉砕した。「生きて虜囚の辱めを受けず」という戦陣訓を守った美談として戦中の本国では語られ、その後のサイパン、硫黄島の悲劇を招いている。
そのころ、キスカ島には、陸海軍合わせて5,200人の兵が「次はわれわれの番か」と恐怖に震えていた。大本営は、ようやく兵の撤収を立案したが、島は米海軍に包囲されている。その中から、海軍の支援艦隊が米軍包囲網の隙をついて島に突入し全将兵を無傷で救出、帰還させている。
千慮して惑わず
救出部隊を指揮したのは、第一水雷戦隊司令官の木村昌福(きむらまさとみ・少将)だった。海軍上層部は、「撤収」といいながら、事実上は戦略上の島「放棄」と考えており、将兵は少しでも救出できればいいし、ダメなら玉砕もと考えていたフシがある。国民の士気を高めたアッツ島の先例もある。北千島に拠点を置く第五艦隊司令部も、「半数でも帰還できれば」と伝達して、木村に作戦指揮の全権を委任する。軍も官僚組織。よくある失敗した時の責任逃れだ。
木村は海軍兵学校を出た後、30年近く傍流の水雷、補給畑を歩んできて、下士官、水兵から慕われる人情家だった。型通りの戦陣訓の教えを嫌い、作戦指揮を任されたからには、「全員を救出して親のもとに返す」と決意を固め準備に入る。
まずは、北太平洋の夏特有の濃霧を利用することにした。そのため、海軍きっての気象専門士官の派遣を要請する。また、護衛と輸送のために駆逐艦を増強することを約束させる。島を包囲する米艦隊の動向を捕捉するために最新鋭のレーダーを装備した駆逐艦「島風」も参加させる。
濃霧の中で敵を欺くため、煙突を米艦に合わせて偽装した。7月中旬の作戦開始に向けて、上陸用舟艇(大発)による訓練も重ねた。
そして万全の準備を終えた7月7日、出航に際して、救援艦隊(巡洋艦2、駆逐艦12)の各指揮官を集めて、「全員撤収」の作戦趣旨を徹底させた上で、訓示した。
「さまざまの困難の中での窮余の策であるが、古語に『千慮不惑』という句がある。諸君は準備を尽くしてきた。各員の奮励努力で成功を確信している」
言葉だけなら誰でも言える。精神論が先行しがちな旧軍内にあって、準備が伴っていることを知ればこそ、部下は上司を信頼する。小さな艦艇中心で傍系を歩んできた軍歴でたまには酒を酌み交わし親身に一水兵まで付き合ってきた木村は、信頼こそが最大の武器であることを知っていた。
練りに練って柔軟に
待つもの同士が出会う七夕の出航を設定したのも単なるゲン担ぎではない。その物語を全員に思い出させ、救出作戦への意識を高めるためだった。
しかし、キスカ沖まで行きながら濃霧が出ない。撤収作戦期日を三度延ばしたが、「機にあらず」と判断して北千島に引き返す。
司令部からは「腰抜け」呼ばわりをされたが耐えて、最適の期日を待った。「島の湾内までは入れたはずだ。それなら幾人かは収容できただろう」と批判もされた。しかし、全員を一気に救出するのでなければ意味がないとの信念は変わらなかった。
そして7月22日に再出航し、26日、濃霧に紛れて米軍に気づかれず、わずか55分の作業で5,200人の将兵を全員、乗艦させて撤収に成功した。
万全の守りをかい潜られることはあり得ない、と米軍は無人の島に上陸を躊躇い、日本軍撤収を確認したのは、3万4千もの大軍を動員して大規模な上陸作戦を敢行した8月17日になってからのことである。
撤収に際して、木村は乗艦後の兵に、命より大事とされた菊の紋章が入った陛下下賜の歩兵銃を海に投棄させた。少しでも軽くして一人でも多くの兵を救うためだった。
目的は何か?兵を救うこと。この一点で木村の行動は一貫している。玉砕を強いる発想の対極にある。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『戦史叢書29 北東方面海軍作戦』防衛庁防衛研修所戦史室著 朝雲新聞社
『キスカ撤退の指揮官』将口泰造著 潮書房光人新社N F文庫