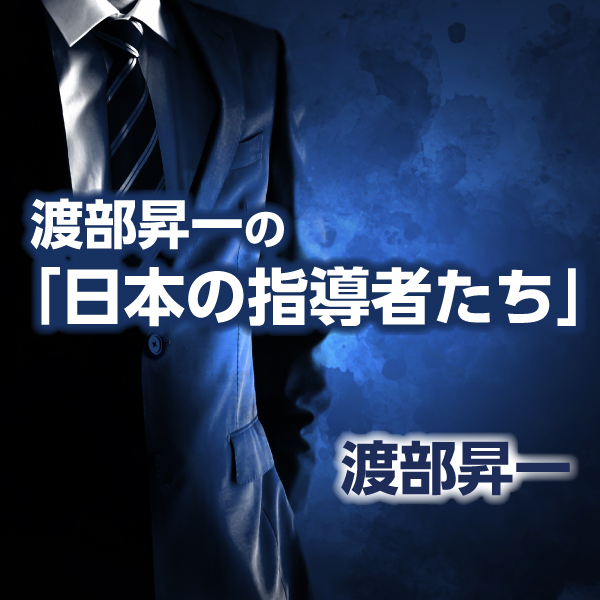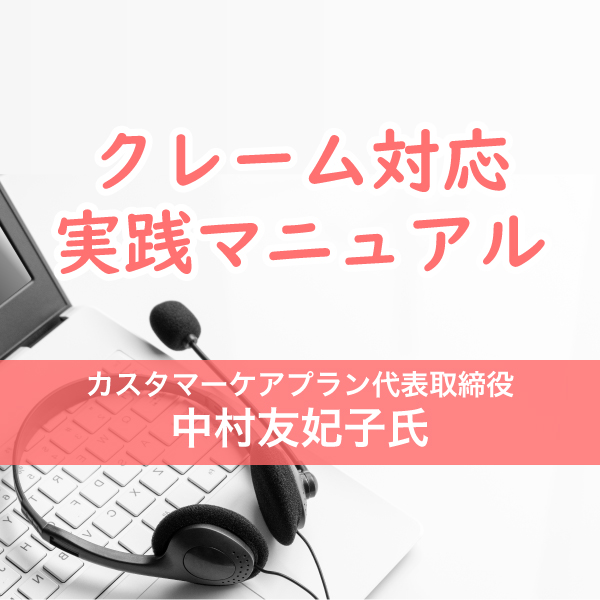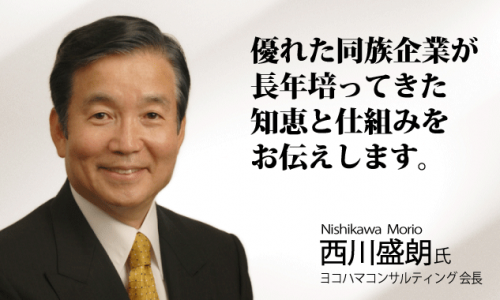フレッシュな感覚の若者が、面接などで「座右の銘」を尋ねられた折に、「初心忘るべからず」です、などと答えることがある。あるいは、会社の朝礼などでこの言葉が使われることもあるだろう。多くの場合、「この仕事に就こう、と思った時の自分の燃えるような気持ち、やる気を忘れないで頑張ろう」との主旨で解釈されているようだ。
その気持ちが大切なのは言うまでもないが、実はこの表現は「誤用」に当たる。まず、この言葉がどこから出て来たかと繙けば、「能楽」の大成者、世阿弥(1363?~1443)が遺した多くの能に関する言葉の中の『花鏡』(はなかがみ)の中にある。ここで世阿弥が言う「初心」に関する言葉の真意を現代的に訳せば、こういうことだ。
「自分が初めて能を舞った時の出来の悪さと言ったらなかった。あの恥ずかしさ、悔しさを忘れずに、増長することなく、日々の研鑽に励もう」。どうも、我々の頭の中にあるイメージとはだいぶ掛け離れているようだ。冒頭で例に挙げた言葉を端的に現わしているという意味では、「初一念」という言葉が最も近いのではないだろうか。「初一念を忘れないように…」とは、立派な心掛けだ。
長い時間の中で、本来の意味を取り違えて使われる事例はしばしばあり、目くじらを立てるほどのことではない。しかし、正しい使い方を知っているに越したことはない。もう旧聞に属する都市伝説の類だが、学校の同窓会の案内状がかつての恩師の元へ届き、「枯れ木も山の賑わいですから、ご参加ください」との言葉に、先生が絶句したという話にならないようにする必要もあるだろう。
世阿弥が「能楽」の大成者と同等の重みを持って語られるべき事柄は、江戸時代以前に初めてとなる「体系的、理論的な演技論」を、実演者の経験をもとにまとめたことである。有名な「秘すれば花、秘せずば花なるべからず」もそうだが、ビジネスの局面、あるいは人間の成長、という面で考えても「なるほど」と思う言葉が随所に含まれている。
俗に『花伝書』と呼ばれる『風姿花伝』には、人間における「花」が記してある件がある。これなどは、「人生100年」の時代を迎えた今でも、全く色褪せることなく通用する話だ。
世阿弥曰く、能役者には年代に応じた「花」が咲くと言う。若い頃には「若木の花」、中年辺りには、「実(まこと)の花」、そして、老年になってからはただ「枯れる」のではなく、その前に「老木(おいき)の花」が咲くとのこと。年齢的な感覚は、700年前と今では10歳以上違っているだろうが、その時期のありようを示すという点では、今も同じだと思える。
サラリーマンに例えれば、「若木の花」は入社5,6年目まで、30代辺りまでのまだどこかフレッシュな感覚を持つ世代の花だ。香気の高い若鮎のような時代、とでも言えばいいだろうか。
それから10年、ないしは15年と実務経験を重ね、管理職ともなり、世間の酸いも甘いも嚙み分けられるような年齢になる。ここで、ようやく「実の花」が咲くという。仕事だけではなく人生の経験も重ね、知識も豊富でまだ身体も元気、まさに「心技体」が充実した年代である。この時の成果が「実の花」なのだ。
会社であれば、その後よほどの事がない限りは「定年」に向かって人それぞれの歩みということになるのだろうが、世阿弥の意見は違う。
肉体的には衰えはじめても、歳月を重ねた「老木」でなくては出せない味わいがあり、それを「老木の花」だと言うのだ。決して枯れているわけではない。もちろん、壮年期のような力はないまでも、さらに多くの経験を積んだ分、微かではあるが馥郁とした香りを放つ。これが「老木の花」の魅力だ。
今のシルバー世代に「老木」などとは失礼だが、各分野での元気な活躍ぶりは、再度び花が咲いているようにも思えるほどの力に溢れている。世阿弥の言うには、力を蓄えて咲いた花は、若々しく匂やかな花の魅力に、決して引けを取るものでもない、と。
考えてみれば、花が咲けばやがて散るのは宿命だ。しかし、その後には「実」がなり、中には新たな「種」が含まれている。樹木の生涯は、若芽を吹き、花が咲き、散りてのち実をならせ、やがて枯れるまでの一年を人の一生に例えたのだとすれば、それが何十年、時に何百年も繰り返されることになる。その間に高さも太さも立派なものになる。我々は、大きな時間の流れの中で、自らの一生で芽吹きから枯れ、朽ちるまでを経験することになるのだ、とも言えよう。
世阿弥は、スポンサーである時の足利五代将軍義満の死と共に境遇が代わり、佐渡へ配流された。会社で言えば、トップが交替して派閥が変わり、左遷されたことにでもなろうか。しかし、稀代の芸術家はそこで腐ることなく、己の半生を顧みつつ、「芸の極意」をまとめることに時間を費やした。この辺りも、我々が見習うべき点が多いような気がする。過去の事象や人物の行動を振り返ると、意外な発見が隠されているものだ。