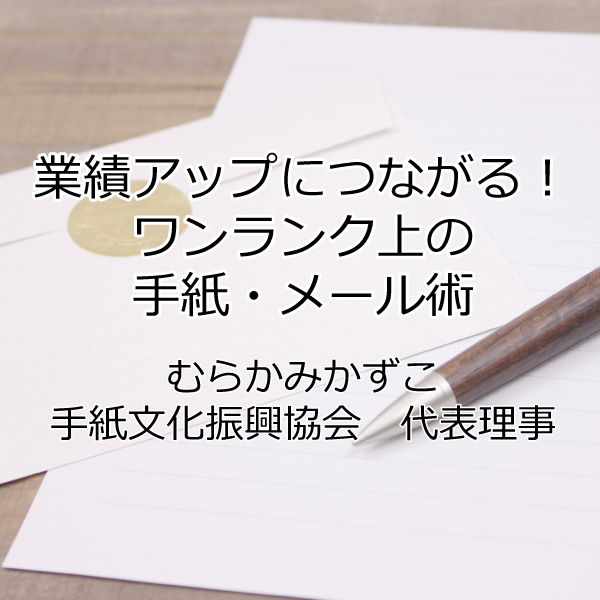しばらく前に「漢字検定」がブームになったことがある。調べてみると歴史は意外に古く、昭和50(1975)年に開始され、当時位は「15級」から始まり、最上位の「5段」まで20段階に分かれていたようだ。それまでは「検定」と言えば「英語技能検定」(「英検」)ぐらいしか知らず、その惨憺たる成績も、とても口にできたものではなかった。平成に入り、「江戸検定」や「文章能力検定」など、他の分野でもこの種の検定試験が行われるようになり、「漢字検定」もその仲間に入り、最盛期の20年には300万人近い受験者がいたようだ。この頃には「7級」から「準1級」「1級」の8段階に整理された。
◆
文部省によれば、我々は高等学校を卒業するまでに「常用漢字」として「2,136」の漢字を覚えなくてはならない。しかし、日ごろそのどの程度の割合を使用しているのかは、定かではない。
「漢字検定」の「1級」ともなると、常用漢字の「音」「訓」の使い分けのほか、「伽藍堂」(がらんどう)、「浪漫」(ロマン)などの当て字、「波斯」(ペルシャ)、「西班牙」(スペイン)、「新嘉坡」(シンガポール)など、海外の国名や地名の漢字表記まで含め、6,000字以上の漢字に関する知識が必要となる。また、俗に「旧字」と呼ばれる表記、例えば「鹽」(塩)、「颱風」(台風)なども理解していないとダメなようだ。
恥を話せば、実は漢字検定の試験を受けた経験がある。必要に迫られたわけではなく、あまりに流行るので、物書きと称して生きている自分が、検定のために捻り鉢巻きをせずとも受かるのはどの程度のレベルなのかを確かめるためだ。仕事に関する自分の技量を知る、と言えば聞こえはいいが、「どんな問題が出るのだろうか」と冷やかし半分であったことも否定はしない。結果は、何とかそれらしいところへギリギリで受かったものの、問題に関して言えば、ほとんど「マニア」の領域に達していた。恐らく、この試験以外でその文字を目にすることは生涯二度とないだろう、という文字がずいぶんあったのを憶えている。
それにしても10代の終わりまでにひらがな、カタカナ、アルファベットに加え、2,000以上の漢字を覚え、それらを混ぜて文章を書くとは、日本人の国語に関する能力は世界に冠たる、と言っても言い過ぎではないだろう。
30年ほど前だろうか、「丸文字」なる非常に読み難いが可愛さを狙った書き方が若い女性を中心に流行った。それが、現在のスマホのLINEやメールで使われる絵文字の源流だと推測することは容易い。
加えて、こうした当て字や文字の記号化は、江戸期にはかなり確立されており、スマホの絵文字が格段に新しい感覚で生まれたわけではない。となると、江戸末期の方が、今よりも更に国語の能力が高かかったと考えることもできる。もっとも、人口に対する割合など、諸事情を考えての比較が必要ではある。
◆
昔から、分野を問わず日本は「加工」に優れた能力を持つと言われてきた。資源のない国の宿命とも言えよう。それは、工芸品や食品、衣類などだけではなく、文字にも及んでいる。「漢字」は読んで字の如く「漢」、すなわち中国の文字だ。しかし、「畑」や「峠」などの文字は、中国産ではなく、国産の文字で、これらを「国字」と呼ぶ。自国の言語体系の根幹の一部は他国からの輸入品でありながら、それを加工し、中国では一つの文字に一つの読み方しかないのに対し、「音読み」と「訓読み」を分け、音と意味で文字の意味が変わるという離れ業までやってのけている。
その上、漢字にない文字は自分たちで作ってしまおうという発想だ。皮肉でも何でもなく、先人の見事な知恵としか言いようがない。
「国字」も、古くから使われている事物を現わしたものと、明治維新以降の文明開化で入って来た西洋の物を漢字で表記するものと二種類に分かれている。
前者で言えば、山のてっぺんで上下を分ける「峠」、田圃を焼いてのち米以外の作物を植える「畑」、神に供える木の「榊」、人が往来する十字路の「辻」、人が動いて「働」などだ。
後者は単位が多く、日本でそれまで使っていた計算とは違う単位が入って来たものを漢字に直したパターンだ。「瓩」(キログラム)、粁(キロメートル)、糎(センチメートル)、などがその部類に入る。
こうした類の例は、朝鮮半島やベトナムにも少数ながら存在するが、日本のように大雑把でも方向性や内容が明確にはなっていない。日本の巧みな加工技術は、食品や工芸品などに留まらず、その国民のアイデンティティの一部でもある「文字」にまで及んでいるのだ。こういう国は他にはないだろう。
◆
今、日本は経済、高齢化の問題、外交さまざまな問題を抱えており、どれもが簡単に片付くようなものではない。しかし、遥か二千年を超える長い期間、四方を海に囲まれながら過ごしてきた中で生まれた知恵の厚みは、ちょっとやそっとの事では揺るがない。若い世代にはその自信を持ち、過去を振り返り有益な種を探す勇気を出していただければと思う。