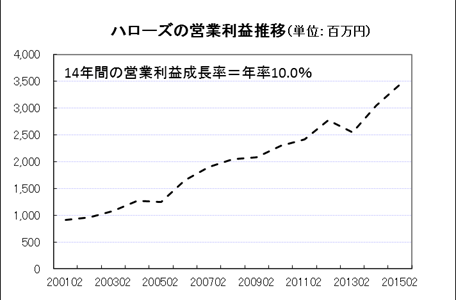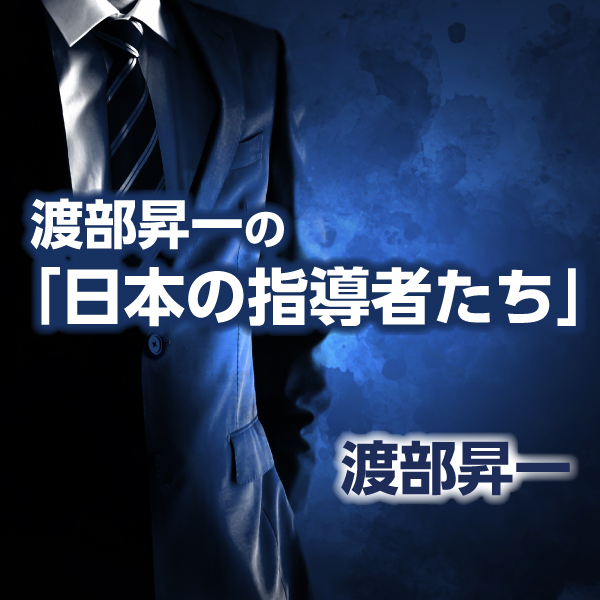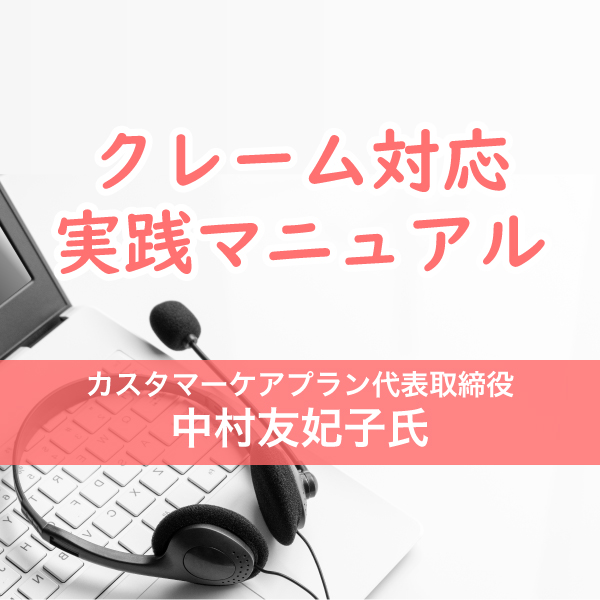ここ10数年のことだろうか、テレビのバラエティ番組を中心に、女装した「オネエキャラ」と呼ばれる人々の登場と台頭、そして、性的少数者(セクシャル・マイノリティ)を現わす「LGBT」という表現の広がりや行動により、性的指向とは別な部分でも、男性が女装をすることや性的マイノリティへの理解が深まっている。これは一般社会の話だが、こと「芸能」の世界に眼を向ければ、歌舞伎の「女形」に代表される男性の異装の歴史は遥かに古い。
「女形」。「おんながた」だけではなく「女方」の字を当てて「おやま」と読む場合もあるが、男優だけで演じる歌舞伎の場合、子役などの例外を除いて、すべての役が男優により演じられているのは周知の事実だ。平成から令和にかけて、女形のトップの座である「立女形」(たておやま)の五代目坂東玉三郎は、今も変わらぬ妖艶な美しさを見せている。1600年代初頭に始まった歌舞伎は、当初は「出雲の阿国」を中心としたメンバーに代表されるように、女性だけの集団によって演じられていた。それが、風紀上の問題から若い少年だけで演じられる「若衆歌舞伎」に変わった。
中世の日本は、男ばかりの社会「武士」が中心に成り立っていたせいもあるのか、日本で最も同性愛が盛んであり、寛容な時代でもあった。しかし、それでもさすがに度が過ぎたのか、今度は成人男子だけで演じる「野郎歌舞伎」に変わり、そこで女性の役を演じるための「女形」が出現した、というのが演劇史の教科書的な解説である。しかし、その底流に流れているものは、あまり学校の歴史ではこの流れの本質には触れないのが現状でもある。
以降、女形の歴史は綿々と続き、男性が女性を演じる苦心は、多くの名優により江戸期から語られている。「恋人役の男優が好きな香りを、衣裳に焚き染めて舞台に出る」、あるいは「冬の夜の逢瀬の場面で、自分が出る寸前まで氷水の中で手を冷やしておく」など、観客には見えない工夫の数々が舞台を充実させてきた歴史があるのだ。男性を演じる「立役」と女形の間に男女のような恋愛感情が育つケースも時にはあったようだが、それも時代の変化と共に、現代ではほとんどなくなった。ただ、それでもコンビとして夫婦や恋人を演じていると、僅かな体調の変化に実際の夫人よりも先に気付くケースもあったと聞いたことがある。
いずれにせよ、繊細な神経を持たなくてはできない仕事だが、世界の演劇史を見渡せば、男優が女装する例は唯一ではなかった。古代ギリシア・ローマ劇から始まり、シェイクスピア当時の英国では自らも俳優であったシェイクスピアは、女性が男装する作品も書いており、日本の女形との感覚は違うものの、女性役を男優が演じていた例もある。
また、近代まで来れば、中国の伝統芸能で日本の歌舞伎との近似性を持つ「京劇」には、梅蘭芳(めい・らんふぁん、1894~1961)とう「旦」(たん。京劇では歌舞伎の女形に相当する役割をこう呼ぶ)が高名で、日本へも何度か来日した。しかし、1966年に起きた悪名高き「文化大革命」で京劇も「不健全な娯楽」としていわれのない迫害を受け、現在も役柄としての「旦」は残っているが、女優が演じている。
こうしてみると、長い歴史を重ねている「女形」は今や日本が唯一の存在になってしまった。日本も、明治以降の近代化の中でリアリズムに反している、と「女形不要論」が何度も消長を繰り返してきたが、幸いにも現在はその気配はない。では、なぜ日本では女形が貴重な存在として残っているのか。ここからは私見だが、単純に「伝統」だけで割り切れる話ではないと私は考える。そもそも、歌舞伎の女形は「男性の肉体」を過酷なまでに駆使しなければできない仕事という側面を忘れたくはない。華やかで豪華な衣裳をまとい、艶麗な様を見せる花魁。役によっては、衣裳や道具の重さは、鬘から塗下駄までを含めると40キロにも及ぶ場合がある。その重さを背負い、動いて台詞を言う仕事は、明らかに「肉体労働」でもある。美貌の女形を捕まえて肉体労働などとはお叱りを蒙るだろうし、それが男性の肉体だから可能なのだと言えば「差別論者」だと言われるかもしれない。しかし、ここで差別的な論旨を展開したいのではない。たまたま歌舞伎の「女形」を例に挙げただけのことで、「歴史の中で残っているもの」には一つだけではなく、人が見逃しがちな要素もあり、そこに眼を向けられるかどうかを指摘したかったのだ。
トンボの複眼ではないが、一つの事象をどれだけ多くの角度や切り口から考えることができるのか。そこに人間の器量や感覚の鋭敏さが見てとれると思う。物事の一面だけを鵜呑みにするだけでは、簡単に騙される時代になってしまった。現代社会で起きている様々な事象のカギは、過去の歴史に想いをいたすことで見えてくる場合もある。
一見非常識と取られかねない考え方でも、何かのヒントになる場合もある。頭は常に柔らかくしておきたいものだ。