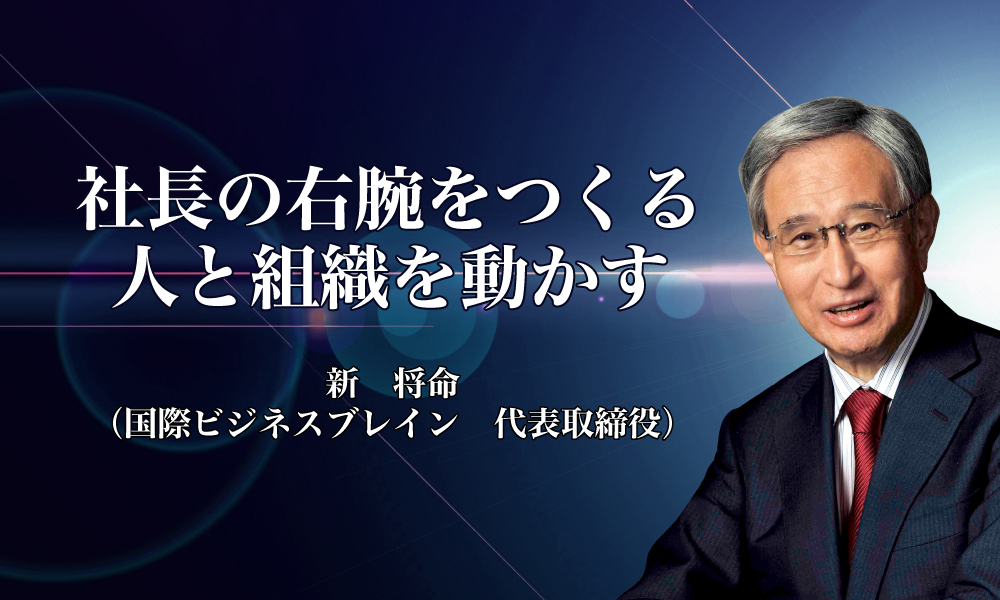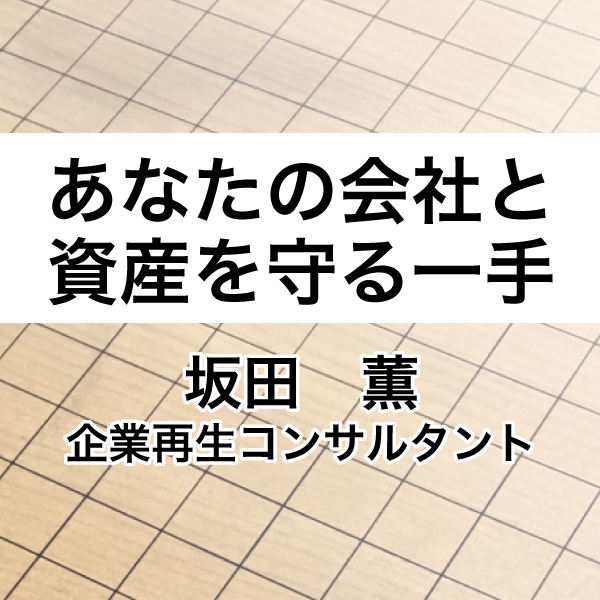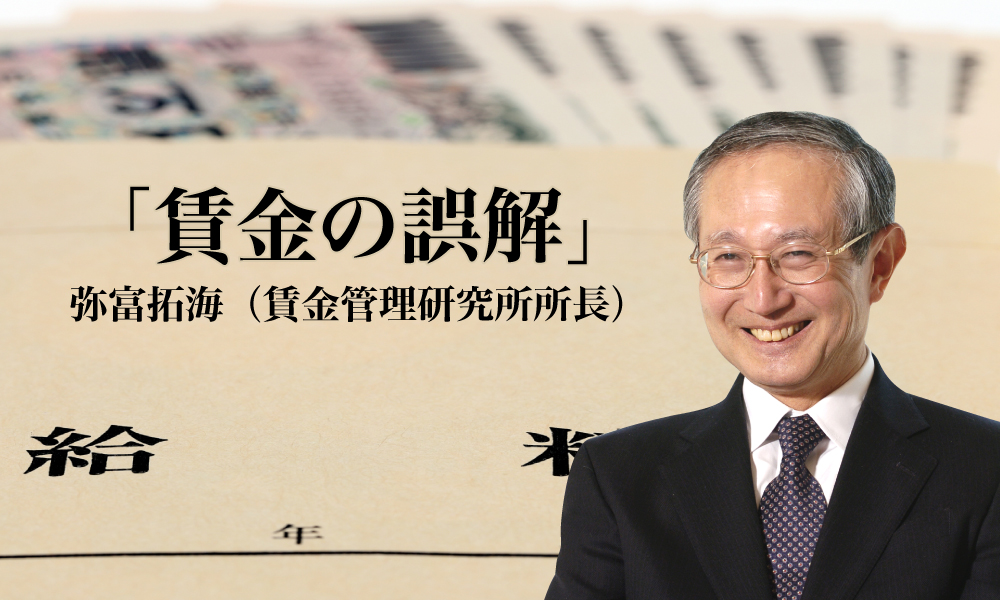「知っておいた方が良いとはわかっているが…」などの理由で、多くの人が日本の古典文学が遠ざかっている。イギリスのシェイクスピアの名は知っていても、同時代の日本の偉大な劇作家・近松門左衛門を知らない人の方が多いのが現実だ。
これは、戦後の教育方法に原因があるのかもしれない。意味も必然性もロクに教えもせずに、いきなり「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の塵におなじ。」(『平家物語』第一巻「祇園精舎」より)と、闇雲に『平家物語』の冒頭や『源氏物語』の冒頭を暗記させられたのでは、その先を読もうという気など起きるわけもない。生徒に迎合するわけではないが、前者を「ヒーロー物」、後者を「宮廷ラブ・ロマンス」とでも説明すれば、もう少し興味を示す機会が増えていたのかもしれない。
もっとも、そんな小手先の技を使わずとも、戦前から戦中にかけての教育を受けた世代の方々が持つ古典漢籍の教養の厚さに驚くことはしばしばだ。戦前の教育のすべてが良かったと言うつもりはないが、「修身」の一部と、国文学の一部に関する教育程度の高さは充分現在でも通用するばかりか、今よりも遥かにレベルが高い。もちろん、時期や場所、人により違いはあるものの、例えて言えば『源氏物語』は全五十四帖を誰かの現代語訳ではなく原文で読み、『平家物語』も重要な部分はほぼ網羅し、『百人一首』もいくつか忘れていても暗記をしている、位は朝飯前だ。
なぜ、これほどの違いが起きるのだろうか? まさに「時代」の違いだが、時代の変化の中で、多くの貴重な「古典芸能」が我々の身体から離れて行ったことは原因の一つとして大きい。ここで能や狂言、歌舞伎などを持ち出そうというのではない。ラジオしかなかった時代、流れて来る「講談」や「落語」に耳を傾け、あるいは明治末期から大正末期にかけて200篇近くが刊行された「立川(たつかわ)文庫」という講談を文庫化した人気シリーズを、父や祖父の書棚や、家の中に放り出してあるものを斜め読みしていたものが、いつの間にか一般教養として身に付いているケースが意外に多いのだ。
「立川文庫」は当時、少年から青年をターゲットにしたもので、難しい文学ではなく、忍者や勇士が登場する冒険活劇、英雄譚などが多かったが、それらとて立派な古典文学として大衆の人気を博してきたものだ。収録されている一例を挙げてみよう。
『宮本武蔵』、『真田幸村』、『真田十勇士』、『木下藤吉郎』、『西郷隆盛』、『猿飛佐助』、『霧隠才蔵』、『安倍晴明』、『水戸黄門』など、幅広くバラエティに富んでおり、いずれも歴史に名を刻んだ人として、あるいは他の形で娯楽化された物により、ご存じの名前も多いだろう。
こうした物の他に、『ロビンソン漂流記』などの翻訳もあれば、『大石内蔵之助』、『佐倉宗五郎』など、明らかに「歌舞伎」と関係の深いものもある。こうした作品に胸を躍らせながら頁を繰るうちに、知らず知らずに古文や昔の言葉遣いが「素養」として身に付いたのだ。子供向けだからとレベルが低いわけではないのは、今のアニメと同様だろう。
現在の我々と古典文学の距離がどんどん離れるのは、こうした「原典」と「時代の読者」をつなぐ物がないことが理由の一つだ。各出版社から古典の名著を現代語訳し、注釈を付けたものが数多く出版されている意義は認めるが、読んでいて「楽しくない」。内容により、何を読んでも胸を躍らせ、ワクワクとは行かないまでも、換骨奪胎した書き替えという作業は、考慮の余地がある文化ではないだろうか。
「立川文庫」まで遡らずとも、私が少年時代の昭和40年代初頭には、世界各国の名作や冒険小説を子供向けにアレンジした本はたくさんあり、ジュール・ヴェルヌの作品群などは楽しみで仕方がなかった。成人後は、オリジナルを読むことで当時を追体験する喜びもあった。現在でもそうした物はあるにも関わらず、もはや親の世代にこうした経験が少ないために、子供に読書の楽しみを体験的に教えることができなくなってきている。社会的には大きな問題にまで発展していなくても、由々しき問題であり、やがて、日本人の感覚として大きな問題になるであろうことは間違いはないだろう。
子供が小さい折には懸命に「読み聞かせ」などをしても、小学校にもなると子供は読書よりもテレビゲームなどの方が楽しくなり、親も一緒に興じている方が楽だと感じるようにもなる。しかし、我が子に限らず若手・中堅の社員を含め、一人の人間を育て、成長させることがいかに難しいかは、今更申し上げるまでもないだろう。
ただ、何事も低きに流れるのは世の例えで、そこで歯を食い縛れる「頑固オヤジ」がいても良いのではないか、あるいは必要なのではないか、と蛮勇を奮ってこの原稿を書いている。私の傍で一緒に勉強をしている若者たちは、私が怒っているうちはまだ大丈夫だろう、などと半分莫迦にしている。しかし、それも私の年代に与えられた役目なのかもしれないと開き直り、嫌がられることを怖れずに、大声を上げる日々だ。たまには、こういう変わり者がいてもいいだろう、と自分勝手な言い訳をしながら。