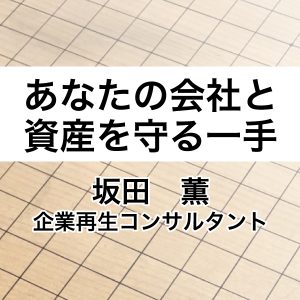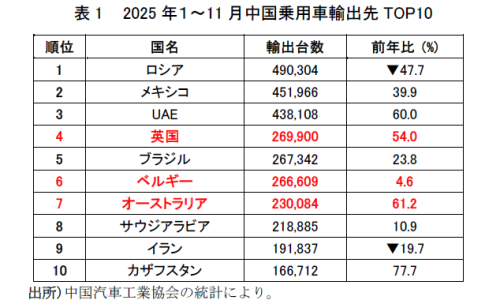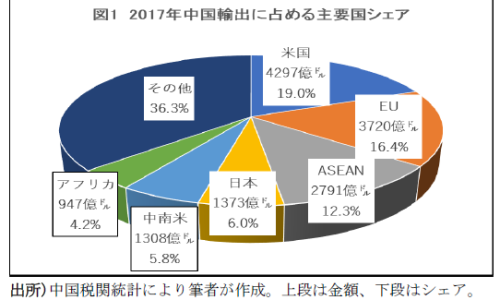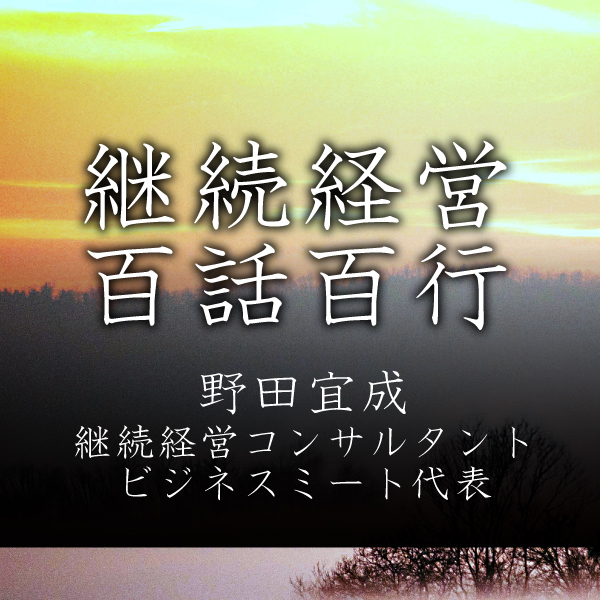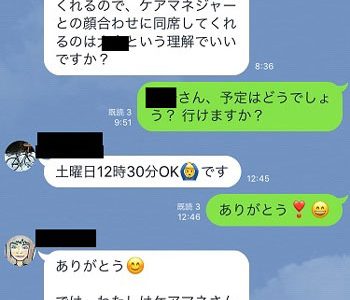財務内容もまずまずで、現金預金もそれなりにあるのに銀行融資の申し込みをするとうまくいかない会社というものがあります。その理由はさまざまですが、致命的なものの一つにあるのが税務リスクと呼ばれるものです。これは経営者が税務会計を理解しないがためにおこることなのですが、例を挙げて説明します。
だいぶ前のことですが、A社で決算時に利益がですぎるし、消費税負担も大きくなりすぎるということで、社長の一存で翌期に納品する材料の請求書を決算日前にもらい支払いをしたことがありました。決算日を超えて顧問税理士が来て、「この前払金はいくら請求書があって支払いされていても納品が翌期なので消費税を仕入税額控除できない」(注1)と言われ、さらにこれによって利益は変わらないと言われ、社長自身の無知と行った行為が無意味であったことを知ったのですが、それだけではすまず、その後にこの取引が記された決算書を融資銀行に提出したことで、銀行側の対応が変わったのです。銀行ははっきりとは言いませんでしたが、「リスクがあるので」と濁らせた発言をしたと聞いています。
その後も融資銀行の態度は変化せず、最終的に別の理由もあって破綻してしまいました。
B社の場合、経理が後手後手になる会社で、自社の利益、税負担がわかるのに1か月余もかかる会社であったため、税負担の増加に気づくのが遅れ、もはや手遅れで法人税、消費税が払えず、なんとか遅れて納付したのですが、このことがあったために融資銀行が試算表を要求するようになり、最速でも3か月前の試算表しか提出できず、銀行が取引に消極的になったケースがあります。この会社の場合、経理は優秀な人でしたが、他の従業員や社長の経理に対する意識が低く最終的には破綻しています。
C社の場合、社長はじめ役員が役員についての定期同額報酬(注2)という概念を知らず、期中に役員報酬をかなり引き上げて節税をはかるも、税理士に経理書類がわたるころにはすでに役員報酬の増額支給が進んでいたためどうすることもできず、決算時には損金算入できずに、節税どころではなくなったわけです。そして、融資銀行は決算書の別表4「役員給与の損金不算入」を指摘してきたそうです。
中小企業では、どんなに優秀な経理担当がいても経理書類の管理は社長をはじめ社員全員が大なり小なりかかわるもので適格迅速に行う必要があります。また、税務については最低限のことを理解しておくことが必要です。
これらができないようであれば融資銀行もその会社から手を引くこともあるのです。
(注1)No.6165前受金や前払金などがあるとき
決算までにサービスの提供が完了していない場合、前払金を支払っていても、原則としてその消費税(仕入税額)は控除できません。
(注2)定期同額報酬
No.5210役員に対する給与(平成29年4月1日前支給決議分)
法人が役員に対して支給する給与(注…上記リンク参照ください)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。