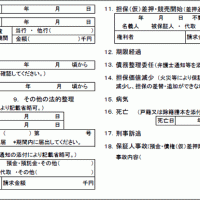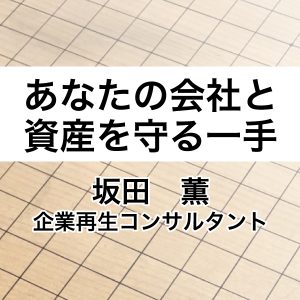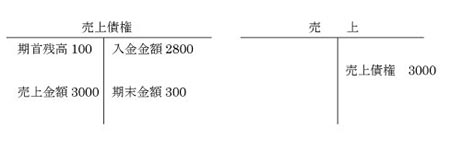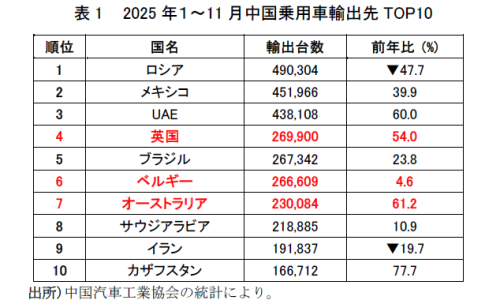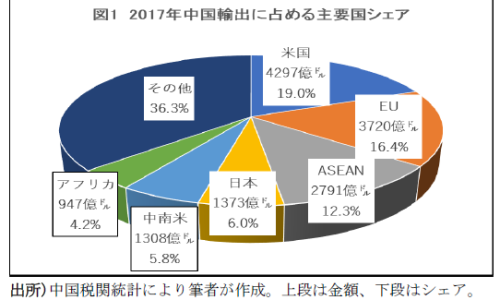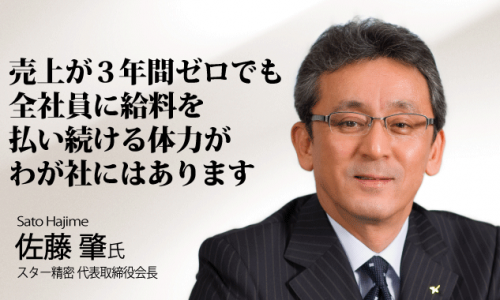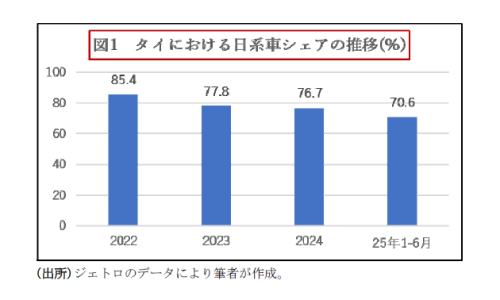会社が銀行から融資をうけて事業資金以外に使うことは許されていません。とくに信用保証協会付であれば資金使途で融資の対象外になることもあり、厳格にチェックされる項目の一つとなります。
信用保証協会の規定では約定書(金融機関と信用保証協会が締結する契約書)において旧債返済が原則禁止されています(注1)。これは厳しくチェックされていて、信用保証協会付の融資が実行入金されて、その資金でプロパー融資の毎月の返済が同日に引き落としされただけでも問題になるものです。また、設備資金名目で融資を受けた場合には、確かにその設備がおこなわれ支払いがされた旨の確認(注2)が融資金融機関側に義務づけられています。
ところが、運転資金名目で借入を受けた場合、その資金がどのように使われたかは確認しづらく、なかには、その資金で不動産を購入する会社もあります。ところが、実務的には運転資金で借りて、しばらく期間をおいてから設備投資をしたとしても、資金使途違反で保証条件の相違となり、以後の融資が停止されることもありうるのです。
これを解決するためには少なくとも当該融資を全額返済することが必要であり、それでも、一度失われた信用は回復することが難しくなります。
では、運転資金で信用保証協会付融資を受けた場合、その後に設備投資を手元資金でやってはいけないかというとそんなことはありません。融資を受けてから何回か決算を経過して、売上・利益ともに大幅に増加して手元資金での設備投資を納得させる状況に持ち込み設備投資をするとか、あえて設備資金での融資を受けてから設備投資するとかです。
多額の役員借入金がある会社で、運転資金名目の融資を銀行から借りて、役員借入金を返済し、役員名義で不動産を購入し会社に賃貸したというケースが以前ありましたが、役員を通した迂回での資金洗浄とみなされたようで、その後の融資が停止となり破たんしたケースがありました。それがバレたのが決算書の「地代家賃等の内訳書」からであり、毎年決算書を銀行に提出することが義務事項のため、そこでほとんどのことがわかってしまうものなのです。
(注1)約定書(金融機関と信用保証協会が締結する契約書)
第3条 乙は、甲の保証にかかる貸付(以下「被保証債権」という。)をもって、乙の既存の債権に充てないものとする。
ただし、甲が特別の事情があると認め、乙に対し承諾書を交付したときは、この限りでない。
(注2)信用保証協会事務規定より
資金使途が設備資金である場合、貸付実行後、速やかに申請どおりに設備が導入されていることを領収書等客観的な書類で確認し、債権書類と一緒に保管してください。
なお、信用保証書に『融資実行後、設備資金に係る領収書(写し)等の疎明資料を提出のこと』などの保証条件が付されている場合は、確認書類徴求後、速やかに協会までご提出ください。