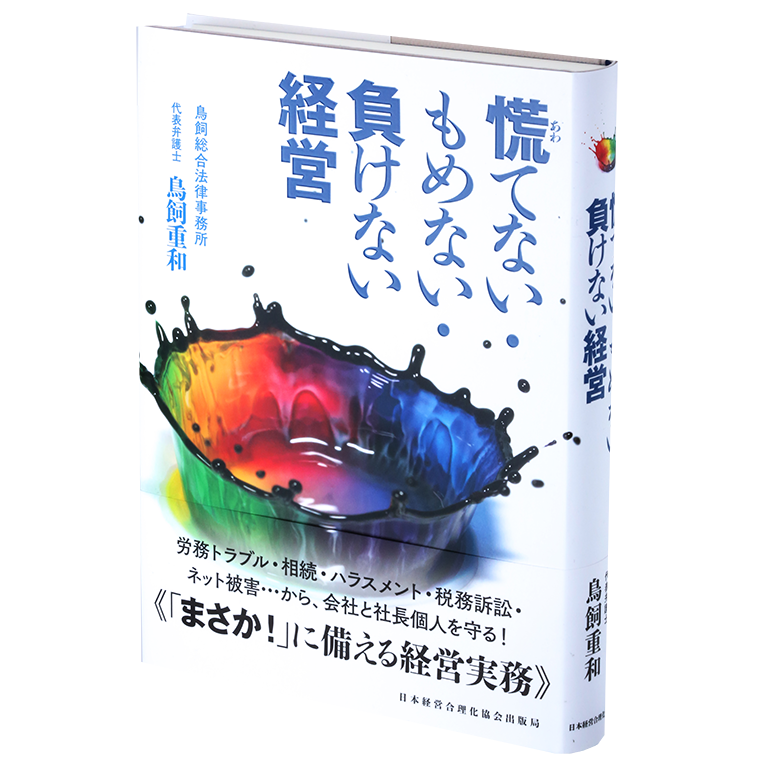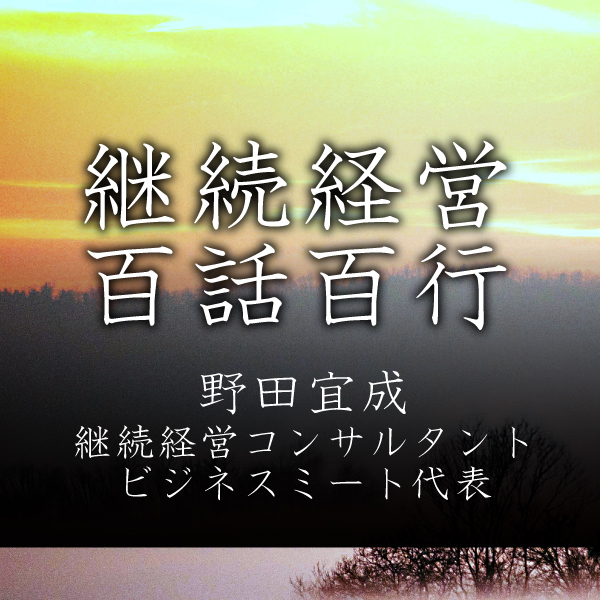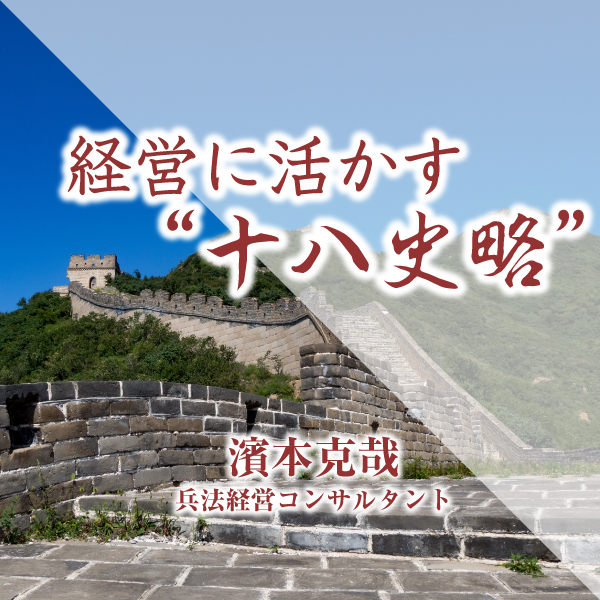阿部社長は、2025年から施行される育児・介護休業法の改正について賛多弁護士に相談に来られました。
* * *
阿部社長:2025年に改正育児・介護休業法が施行されると聞きました。具体的にどのように変わるのでしょうか。また当社としてどのような対応が求められますか。当社には子育て世代の従業員が多いので影響が気になります。
賛多弁護士:今回の育児・介護休業法の改正の趣旨は、事業者に対して男女を問わず労働者に仕事と育児・介護を両立できるようにするための職場環境づくり求めるものです。大きく次の3つが改正の柱となっています。
- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
今回の改正は2025年4月1日から10月1日にかけて順次施行されますが、まず今回は直近の2025年4月1日施行の主な改正点について説明します。
阿部社長:では早速、「1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」に関する改正とは具体的にどのような内容ですか。
賛多弁護士:まず①「子の看護休暇の見直し」です。現行では、看護休暇の対象となる子は、小学校就学前の子に限られていましたが、改正後は、小学校3年生の子まで拡大されます。また看護休暇の取得事由も、現行では子の病気・けが、予防接種・健康診断に限られていましたが、改正後は感染症に伴う学級閉鎖等や、入園(学)式や卒園式が追加されます。さらに現行では勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外できましたが、改正後はこの仕組みが廃止され、勤続6月未満の労働者も子の看護休暇を取得できることになります。
阿部社長:子の看護休暇の対象となる子の範囲、取得事由、取得できる労働者の範囲がそれぞれ拡大されるということですね。
賛多弁護士:はい。次に②「所定外労働の制限の対象拡大」です。現行では、所定外労働の制限 (残業免除) の対象となるのは3歳になるまでの子を養育する労働者ですが、改正後は、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されることになります。
阿部社長:①や②の改正によって、看護休暇を付与したり残業できない労働者の範囲が拡大するため、現状の人員体制では業務が回らない恐れがでてくるのではないか心配です。
賛多弁護士:その場合には、人員体制の見直しや業務フローを見直すなどの対応が必要となります。さらに③「育児のためのテレワークの導入」です。3歳になるまでの子を養育する労働者を対象にテレワークを導入することが事業主の努力義務となります。
阿部社長:これは努力義務なので必須ではないということですが、テレワークが導入されると小さい子を持つ労働者にとっては嬉しいですね。次に「2.育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化」に関する改正とは具体的にどのような内容ですか。
賛多弁護士:④「育児休業取得状況の公表義務の適用拡大」です。現行では常時雇用する労働者数1000人超の事業主を対象に、男性労働者の育児休業の取得状況を年1回公表することを義務付けていますが、改正後は、その対象が300人超の事業主に拡大されます。
阿部社長:当社も公表義務適用の対象になりますね。具体的にいかなる内容をどのような方法で公表すればいいのですか。
賛多弁護士:公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。 インターネットなど 一般の方が閲覧できる方法で公表することになります。
阿部社長:最後に「3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」に関する改正とは具体的にどのような内容ですか。
賛多弁護士:まず、⑤「介護休暇を取得できる労働者の要件緩和」です。介護休暇について、現行では勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外できましたが、改正後はこの仕組みが廃止され、勤続6月未満の労働者も介護休暇を取得できることになります。
阿部社長:勤続6月未満の労働者も①の子の看護休暇のみならず介護休暇も取得できるようになるということですね。
賛多弁護士:次に⑥「介護離職防止のための早期の情報提供や雇用環境整備」です。事業主は労働者が介護休暇や両立支援制度等の申し出を円滑に行えるよう、一定の措置を講じることが義務付けられます。
阿部社長:一定の措置とは具体的にどのような措置ですか。
賛多弁護士:ⅰ「労働者への研修の実施」、ⅱ「相談窓口設置」、ⅲ「利用事例の収集・提供」、ⅳ「利用促進に関する方針の周知」の4つのうちいずれかの措置を講じる必要があります。
さらに、⑦「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」です。労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について周知・意向確認を個別に行うことを事業主に義務付けられます。
阿部社長:周知する内容とはどのような内容ですか。
賛多弁護士:周知する内容は、ⅰ「介護休業や介護両立支援制度の内容」、ⅱ「介護休業や介護両立支援制度の申出先」、ⅲ「介護休業給付金に関すること」の3点です。
阿部社長:個別周知や意向確認の方法はどのようにして行えばいいでしょうか。
賛多弁護士:ⅰ「面談(オンラインを含む)」、ⅱ「書面交付」、ⅲ「FAX」、ⅳ「電子メール等」のいずれかになりますが、ⅲとⅳは労働者が希望した場合に限ります。
最後に、⑧「家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにする措置」が、事業主の努力義務となります。
阿部社長:かなり多岐にわたるため、早急に準備に取り掛かる必要がありますね。
賛多弁護士:はい。4月1日の施行日までに就業規則の変更などの対応が必要となりますので、早めに準備を開始してください。
阿部社長:わかりました。早速準備をしたいと思います。
* * *
改正育児介護休業法が2025年4月1日から段階的に施行されますが、今回は4月1日施行となる改正点について取り上げます。
2025年4月1日施行となる主な改正点は次のとおりです。
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限の対象拡大
- 育児のためのテレワークの導入
- 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 介護離職防止のための早期の情報提供や雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 介護のためのテレワークの導入
その他の改正点を含め詳細については、末尾の厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」を参考にして下さい。
今回の改正に伴い、事業主は次の対応を行うことが想定されます。
まず、事業主は、法改正の内容に合致するよう2025年4月1日までに就業規則の該当する条項の見直しが必要となります。例えば、①子の看護休暇の取得事由の拡大に伴う規定の修正、②所定外労働の制限の対象拡大に関する規定の追加、③⑧のテレワークに関する規定の追加などです。具体的な規定例は厚労省のホームページにあるので参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
社内制度として、③⑧子の看護や介護のテレワーク制度の導入・拡大、⑥に関して相談窓口の設置、⑦に関して個別の周知や意向確認の仕組みづくりなどが必要となります。
これらに併せて、労働者が新しい育児介護休業制度を利用しやすいように理解を促すため、労働者に対して社内説明会や研修などを実施して法改正の内容や社内制度を周知することが望ましいです。
加えて、④育児休暇取得状況の公表義務が課されることになるため、対象となる事業者は、男性労働者の育児休暇取得状況の把握、公表内容や公表方法を検討するなど準備を行う必要があります。
最後に、子の看護休暇の取得できる労働者や残業が免除される労働者の範囲が拡大されることなどに伴い、人員不足によりこれまでの業務に支障が生じる恐れがあります。そのため組織体制や業務フローの見直しも必要となる場合があります。
参考:厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
執筆:鳥飼総合法律事務所 弁護士 北口 建