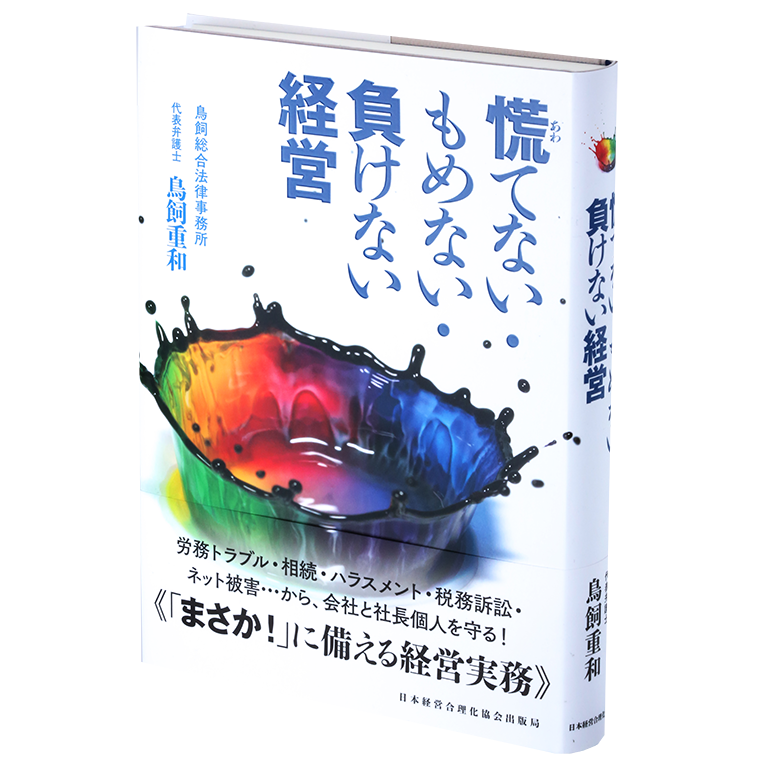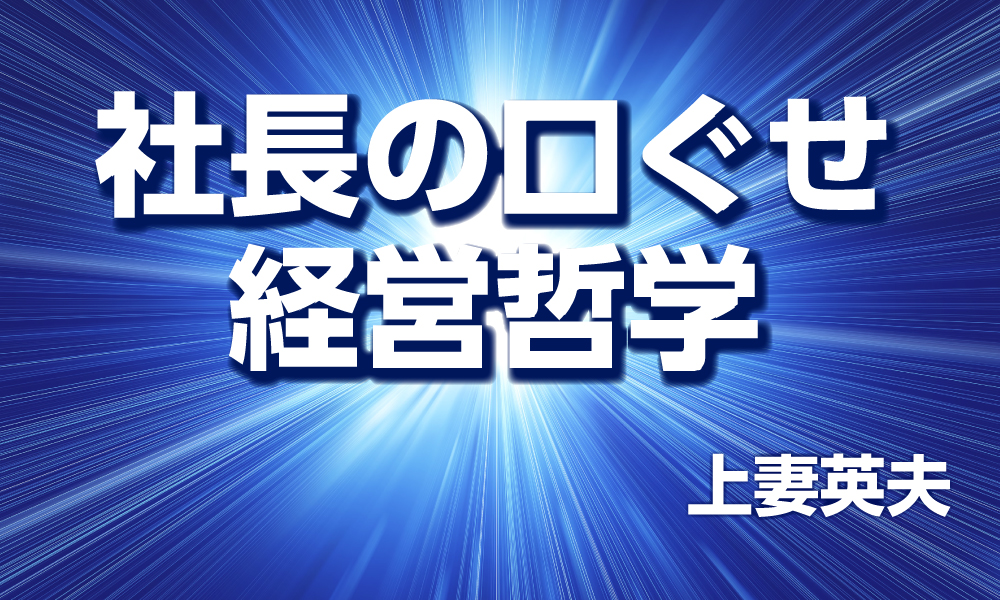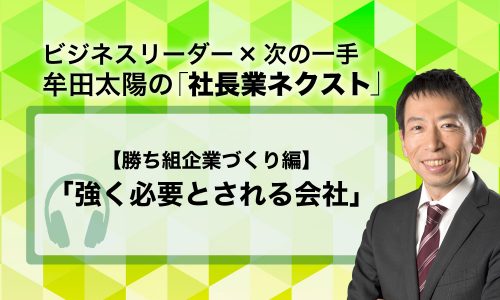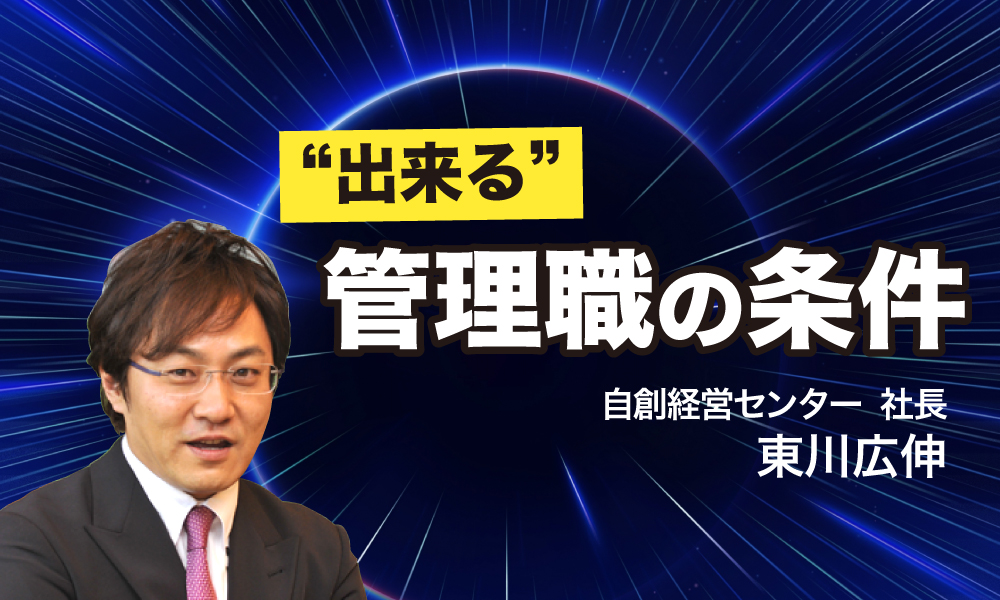愛知社長は取引先が代金の支払いをしようとしないため、今後の対応を相談するために賛多弁護士のもとを訪れました。
* * *
愛知社長:当社が昨年頃から新たに取引を始めた会社があります。何回か取引を重ねるうちに信用できる会社だと思い、だんだんと取引量も増やしてきました。最近も大きな取引をして、当社は納品も終えたのですが、その会社があれこれと難癖をつけて、代金を支払おうとしません。それなりに大きな金額だったため、当社としては頭を悩ませています。
賛多弁護士:なるほど、これは、いわゆる「債権回収」の問題ですね。契約書や納品の証拠はありますか。
愛知社長:はい、今回の取引の証拠はきちんと残してあります。
賛多弁護士:その会社の不動産や預金口座がどこにあるかご存じですか。
愛知社長:その会社がこれまでの支払いの際に使っていた預金口座は分かりますが、それ以外の預金口座や不動産の所在まではわかりません。ただ、契約書や納品の証拠はありますから、裁判をすれば勝てると思います。
賛多弁護士:その会社の言い分も聞かなければなりませんが、契約書や納品の証拠があれば、確かに、裁判では勝てる可能性が高いでしょう。ただ、裁判に勝てるかどうかという問題と実際に代金を回収できるかは、別の問題なのです。裁判で勝った後に判決書を使って代金を回収しようとする場合は、相手の財産を差し押さえる必要があります。相手の財産がどこにあるのか分からなければ差し押さえのしようがありませんので、勝訴判決は、まさに「絵に描いた餅」となってしまいます。
愛知社長:なるほど、裁判で勝つ=代金を回収できる、というわけではないのですね。相手の財産がどこにあるのか調べる方法はないのでしょうか。
賛多弁護士:勝訴判決を得た場合、裁判所の手続を利用することで、相手の所有している不動産を調査することができます。具体的には、「財産開示手続」という手続により、相手が法人であれば、法人の代表者を裁判所に出廷させ、その財産状況を明らかにさせます。これが功を奏さない場合、さらに「第三者からの情報取得手続」という手続により、東京法務局に対し、相手の所有する不動産の情報を開示するよう求めることができます。このような方法により、相手が不動産を所有しているのかどうか、そして、所有している場合にはどこに不動産を所有しているのかを把握することができます。
愛知社長:なるほど。逆にいうと、勝訴判決を得る前は、このような方法で相手の不動産の情報を得ることはできない、ということですか。
賛多弁護士:そうですね、勝訴判決以外にも公証役場で作成した公正証書があればこの手続を利用することができます。たとえば、取引の相手が代金を支払おうとしないため、取引の相手と協議を行い、その協議の結果を「債務弁済契約書」にまとめます。そして、相手が約束した通りに返済を行わない場合、すぐに相手の財産を差し押さえることができるようにするため、これを公正証書で作成します。この場合も、実際に返済がなされない場合は、先ほどの「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」を利用することができます。
愛知社長:裁判ではなく、当事者間の話し合いで解決をする場合でも、公正証書にしておいたほうが良いということですね。
賛多弁護士:そのとおりです。債務弁済契約書が公正証書で作成されていれば、このような裁判所の手続を利用できますし、また、裁判をすることなく、相手の財産を差し押さえることもできます。債務弁済契約書が公正証書で作成されているのか、それとも、そうではないのかによって、その後の「債権回収」のしやすさには大きな差があります。
愛知社長:分かりました。預金口座についてはどのような調査方法がありますか。
賛多弁護士:預金口座についても、勝訴判決を得た後か、あるいは、公正証書があれば、不動産と同じように、裁判所の手続を利用することで、相手の預金口座を調査することができます。ただし、不動産の場合には、まずは、「財産開示手続」という手続を利用する必要がありますが、預金口座の場合には、最初から「第三者からの情報取得手続」という手続を利用することができます。そのため、各金融機関に対し、相手の預金口座の情報を開示するよう求めることができ、これにより相手の預金口座の有無、所在を把握することができます。
愛知社長:よく分かりました。勝訴判決が「絵に描いた餅」にならないよう、その後の相手の財産を調査する方法も定められているのですね。最終的にはそのような方法があると分かり、安心しました。それでは、今回の取引先に対しては、まずは話し合いでの解決と公正証書の作成を目指したいと思いますので、対応をお願いできますか。
* * *
債務者である取引先が支払いをしようとしないという事態は、会社を経営していれば少なからず経験されることでしょう。まずは債務者と協議を行い、協議で解決できない場合には裁判というのが基本的な流れです。ただ、裁判をしても最終的に債権を回収できる目途が立たないのであれば、時間と費用をかけて裁判をすることには二の足を踏まざるを得ないでしょう。
弁護士が債権回収の相談を受けた場合も、「交渉や裁判を有利に進められるような証拠が揃っているか」という観点と「債務者から実際に債権を回収することができるか」という観点の両面から検討を行います。そして、実際に債権を回収できるかどうかは、債務者の財産の所在を把握できるかどうかが大きく左右します。財産の所在を把握する方法としては、今回、取り挙げた「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」という方法があります。他に、弁護士会が実施する弁護士会照会(23条照会)という方法を利用して預金口座の所在を調査することも考えられますが、勝訴判決を得る前にこの手続で得られる情報は限定的です。
債権回収は、裁判所や弁護士会の手続を念頭に検討することが重要です。また、債務者にとって、どの財産を差押えられたら支払いに応じざるを得ないかというビジネス的な感覚も求められます。債権回収は古くからある問題ですが、その解決には多角的な視点が求められるといえるでしょう。
執筆:鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田 重則