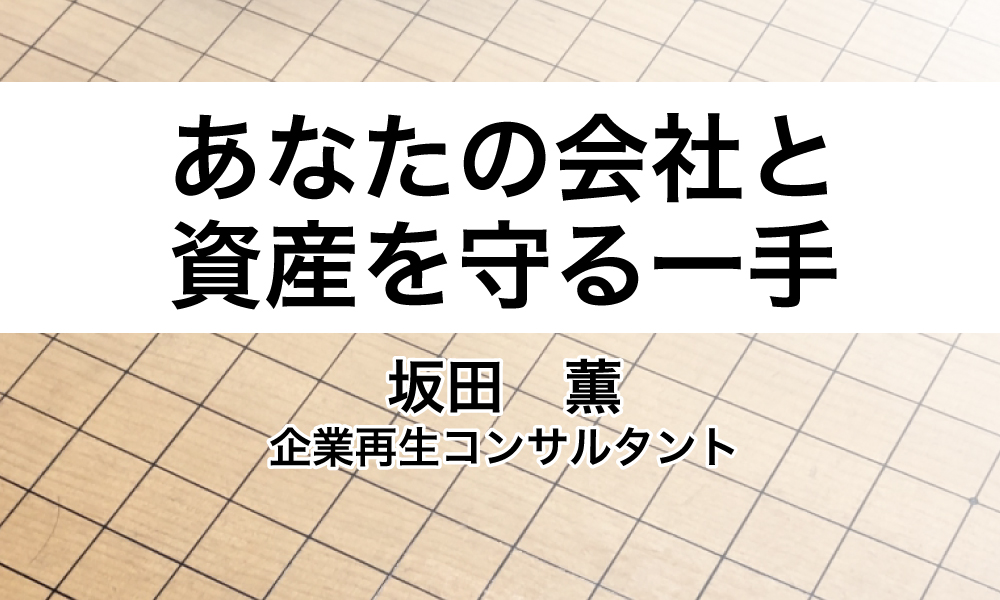論功行賞への身内からの不満
いかなる組織も公平な人事が行われなければ、だれもが働く意欲を失ってしまう。トップの親族であるというだけで、その人物を重用するのはもってのほかである。これはだれにでもわかる。わかるけれども、親族から働きかけがあればだれしも情が移って厚遇しがちである。しかしトップの家の出身であればこそ、使われている全員がその動静に細かく注目し、トップの鑑識眼以上に適切な人物評価をしているものだ。身内の能力評価に対してこそ組織のリーダーとして公平に目配りする必要がある。
大唐帝国の二代皇帝の太宗(たいそう)は、即位元年に大規模な論功行賞人事を行った。中書令(秘書格)の房玄齢(ぼう・げんれい)ら内務官僚たち三人に、天下取りの勲功第一等として爵位を与え厚遇した。
これに、太宗の叔父で淮安王の李神通(り・しんとう)が不服を申し出た。
「先代の高祖が隋の煬帝に異を唱えて義兵を挙げたとき、私は真っ先に兵を率いて馳せ参じた。その私をさておいて、軍事の現場も知らぬ内務官の房玄齢らに功績第一の栄誉を与えるのは納得できぬ」
現代風にたとえて言えば、〈先代の創業にあたり営業部隊を率いて動いた最も先代に近い身内の自分をさておいて、総務畑の赤の他人を評価するとは何事か〉との不満である。今でもあり得そうな人事トラブルだ。
賞罰こそ国の大事
その不平に対して、太宗はまず論功行賞の原則を説いて斥けた。
「賞と罰こそが国の重大事だ。褒賞がその者の功労に応じて適切であれば、功績のない者は自ずと引き下がる。与えた罰則がその者が犯した罪に相応であれば、悪事をなす者は跡を絶つだろう。私は各人の功績を慎重に見極めて表彰したのだ。房玄齢たちは、戦場は踏まなかったが、本陣で作戦を立て国を確立するに第一の功績があると判断したまでのこと」。文句を言われる筋合いはない、というわけだ。
「叔父上は私とは最も近い身内だ。お望みとあれば、何なりと差し上げてもよいが、そんな縁故だけで、勲功のある臣下と同じように褒賞するわけにはまいりません」。李神通は返す言葉がなかった。
この一件は、宮廷周辺に意外な効果ももたらした。臣下たちは皇帝の判断を聞いて、こう噂しあったという。「陛下の判断はこの上なく公平だ。親族だからといってえこひいきなさらなかった。われらも滅多なことでは不満は言えないぞ」。家臣たちの結束を固めるためのパフォーマンスだったのだろう。
太宗は、この賞罰原則をさらに、拡大させた。実は、父親の高祖は唐建国に際して、皇族の籍に連なるものをすべて洗い出し、兄弟、おい、従兄弟、さらに遠い縁者まで爵位を与えて、地方王に封じていた。その数十人にのぼったという。政権基盤の脆弱な建国直後の国固めの方策であったのだが、太宗はこの見直しにも手をつけた。地方王の封爵を受けながら実績のない者たちを調査の上で容赦なく降格させたのだった。
身内でも、できる人材は差別なく登用する
これだけなら、王族、重臣の親族にとってはさぞや居心地の悪い体制運営に見えるが、太宗は、人材登用に際しては、あくまで能力主義に基づいて、逆差別を禁じている。
同じく即位元年、側近を通じてこう命じる。
「私は、政治の立て直しのため、幅広い人材を求めて、優れた人物がいると聞けば抜擢登用をはかっている。しかし口さがない者は、〈近ごろ登用される者は重臣の縁故採用ばかりではないか〉と批判する」と嘆いた上で、こんな人事原則を伝えた。
「あらためて申し渡しておくが、肝心なのは優れた人材の確保であることを忘れぬように。批判を恐れることはない。有能な人材であれば、親族でも、かつての仇敵でもかまわない。見どころのある人物は遠慮なく推薦せよ」
縁故採用もオーケー。ただし真に仕事のできるものオンリー。どういう優秀な人材がどれだけ集まったかは、伝えられていないが、心意気やよしとしよう。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『貞観政要 全訳注』呉兢著 石見清裕訳注 講談社学術文庫
『貞観政要』呉兢著 守屋洋訳 ちくま学芸文庫