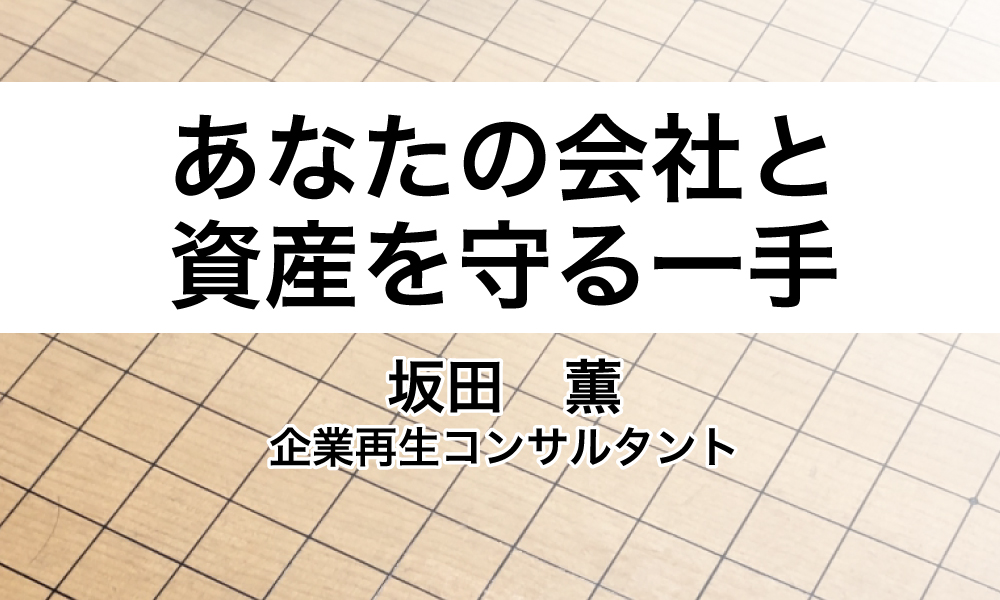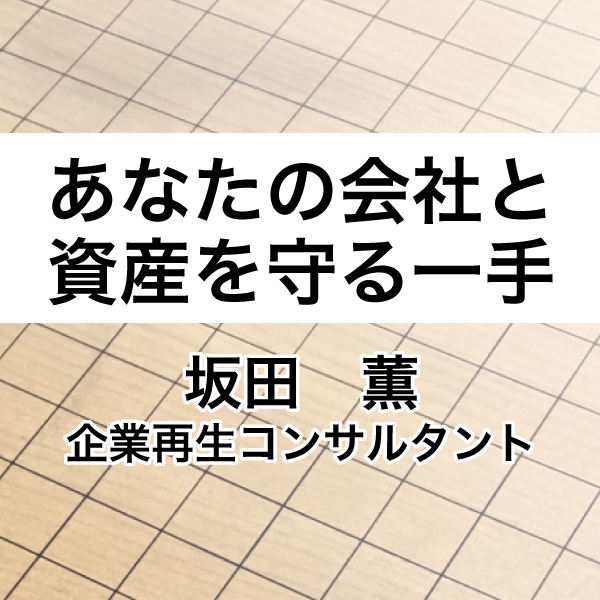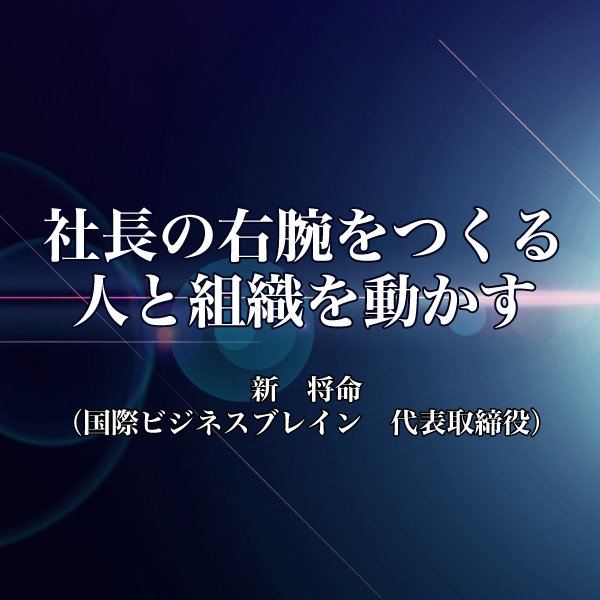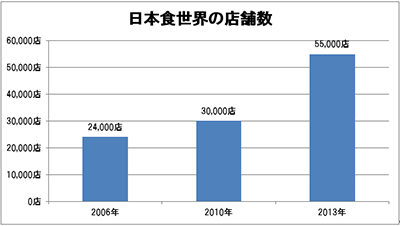臨終の枕辺
前々回に書いた真田家の第一の危機は、主君武田信玄の死から始まった。甲斐・信濃を治めるカリスマ統治者の死は、無論のこと武田家にとっても危機到来の狼煙となった。
元亀3年(1573年)の暮れに浜松近郊の三方ヶ原で徳川家康を破った信玄は、いよいよ西上して織田信長との決戦を控えた矢先、病に倒れ甲斐に引き返す途中、信州駒場(現・長野県阿智村)で最期の時を迎える。
死期を悟った信玄は、病の床に譜代の家老、一家をなす家臣たち皆を呼び寄せ遺言を告げた。後継と目された四男の勝頼(かつより)も居並ぶ場で、「武田家の家督は、勝頼の子の信勝(のぶかつ)に継がせる」と告げたのである。当時、信勝は7歳。「信勝が16歳で元服するまでの間は、勝頼を陣代(後見人)とするが、武田家に伝わる風林火山の旗などは、勝頼には持たせない。(当面は)勝頼を主人同様に盛り立てよ。ただし後継はあくまで信勝だ。信勝を信玄と思って重んじよ。よいな」。
なんとも奇妙な後継指名に、家臣たちは戸惑いを隠せなかったが、絶大なカリスマとして君臨した「お屋形さま」の遺言とあっては従わざるを得ない。だれよりも困惑したのは、勝頼だったろう。家臣全員の前で披露された複雑な役まわりを担わされて、これからどう家臣団を統率すればいいのか、憤りとともに暗澹たる気持ちとなった。
後継者を決めず信頼せず
信玄は合戦に明け暮れる中で、後継の路線をきちんと準備できていなかった。正室の間には三人の男子がいた。勝頼は、攻め滅ぼした諏訪家の娘を娶って産ませた子で、もとより後継候補ではなかった。ところが嫡男の義信(よしのぶ)は今川派のクーデターに加担したとの嫌疑をかけられて廃嫡の上、幽閉先で死去した。次男は出家し、三男は夭逝している。
そうした経緯の中で、第一候補の勝頼は、諏訪家の跡取りに出され、後継者不在のままでこの時を迎えたことになる。
かといって、勝頼に武才がなかったわけではない。武田家の宿敵である越後の上杉謙信も、この後、激しい戦闘を繰り返すことになる織田信長も、領地を接する三河の徳川家康も、勝頼の激しい戦意と用兵を評価し、一目も二目も置いて警戒している。
では、なぜ信玄はすんなりと勝頼を後継指名しなかったのか。父子でソリが合わなかったとしか考えられない。同じ遺言の中で、「勝頼は今後、武田家の領土保全のための守成に徹し、間違ってもこちらから打って出てはならない」と戒め手足を縛っているところからすると、辛抱が足りない勝頼の気性を懸念していたように見てとれる。
カリスマ創業者の思い上がり
信玄の統治術はある種独特だった。信長が築き上げた中央集権的な軍団構成ではなく、郷村ごとの武将を束ねる連合政権的な色彩が強い。攻めについては、甲府の居館に陣取る信玄の不敗のカリスマと部下の面倒をとことん見る情で動かした。守りに際しては、各地域の出城と砦に依る武将たちの自主性を尊重し敵を追い散らした。
「その人心収攬術は、血気盛んな勝頼にはできまい」。それが冒頭の遺言につながる。しかし、それは信玄の思い上がりでしかない。世のカリスマ創業者たちの陥りがちな落とし穴である。「俺にはできたが、頼りない息子(後継者)には無理だ」
無理だと思うのなら、生前に後継者候補をしっかり決めて鍛えておくべきだ。そして、満座の前では後継者のメンツを立てるべきだった。信玄は、いずれも実行しないまま世を去った。
「それならやってやろうじゃないか」。勝頼は、父の遺言を無視して自らをたのんで走り出す。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『武田三代』平山優著 PHP新書
『戦国武将に学ぶ「危機対応学」』童門冬二著 角川SSC新書