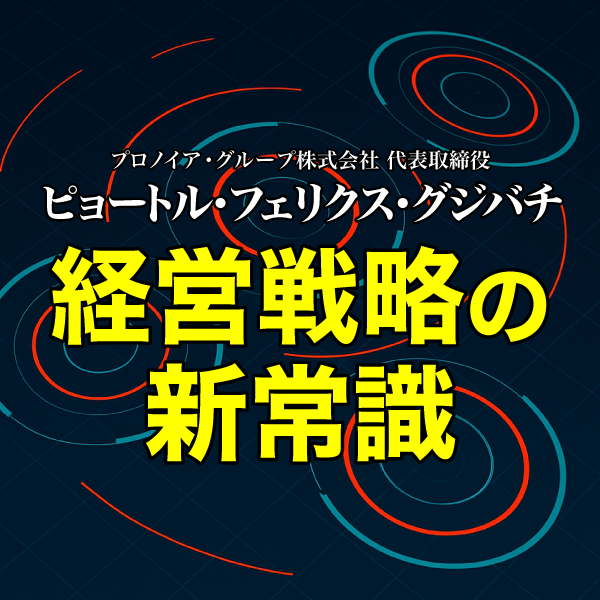保守政治家の矜持
1930年代、暗雲が立ち込める日本で、与党・民政党の衆院議員斎藤隆夫(さいとう・たかお)が、帝国議会で二・二六事件についての軍部の責任と軍の政治介入を鋭く批判する、いわゆる「粛軍演説」(1936年5月)を行なった後も軍の反省は見られなかった。陸軍は、事件の背後にいた軍の皇軍派を粛正したが、このことがかえって対立する統制派の勢力を強め、勢いを得た軍は、満州事変で固めた大陸での利権の強化を狙い、日中戦争(1937年〜)を引き起こし、中国での戦線は拡大する一途をたどった。
1938年4月には、国家総動員法が制定され、一気に国家統制が進められて国内は軍事色が高まっていく。同法制定についても斎藤は「国の将来を危機に導くもの」として反対の論陣を張ったが、国会は与野党の全会一致で同法を成立させている。
軍の恨みを買った斎藤への圧力と監視も強化される。しかし、斎藤はどちらかというと保守的な政治家で、議会制民主主義と言論の自由を重視していた。政府を超越した軍部の独裁と横暴への危機感をもち、国民の代表として、戦争の道を突き進む中で生活に苦しむ国民のために行動した。保守政治家、議会人としての矜持を捨てなかった。
愛国心からの「反軍演説」へ
1940年1月に比較的穏健な海軍出身の米内光政(よない・みつまさ)内閣が発足すると、斎藤は満を持して三年ぶりに本会議の質問に立つ。質問の趣旨は、日華事変(日中戦争)収拾の方策についてだった。民政党は軍を刺激するとして登壇を阻止しようとしたが、彼はそれを押し切って2月2日、演壇に立つ。
衆院本会議場の傍聴席は、開場直後から人々が押しかけたという。
斎藤は、日中戦争の収拾を掲げる歴代内閣が、その一方でこの戦争を「東アジア永遠の平和のための聖戦」であると定義していることについて、厳しく批判する。
「ただいたずらに(聖戦などという)理想にとらわれることなく、国家競争の現実に即して国策を立てるのでなければ、国家の将来を誤ることがあるのであります」「聖戦の美名に隠れて、国民的犠牲を閑却(かんきゃく=なおざりに)し、曰く国際正義、曰く道義外交、曰く共存共栄、曰く世界の平和、かくのごとき雲をつかむような文字をならべ立てて、そうして千載一遇の(撤兵、戦争終結の)機会を逸し、国家百年の大計を謝るようなことがありましたならば、現在の政治家は、死してもその罪を滅ぼすことはできない」。ヤジにかき消されながらもここまで言い切った。傍聴席から万雷の拍手が響く。
圧力を配しての愛国心からの魂の叫びだった。太平洋戦争突入まで一年半。まだ国会と言論の自由は(斎藤ひとりではあるが)かろうじて生きていた。
議会追放と復活
巧みなレトリックで軍部を名指ししていないものの、軍部批判は明らかだ。演説直後からこれが問題になる。議長は職権で、「聖戦批判は天皇の大権に背くものだ」として、聖戦に触れた部分を含めて1時間半に及ぶ演説の議事録から三分の二を削除する。しかし、地方紙の一部が演説の全文を掲載したことから、この「反軍演説」は国外にも配信された。
斎藤は懲罰委員会にかけられて、衆議院を除名される。そしてこの年の10月には、与野党は事実上解散し、軍と協力して戦争を遂行する「大政翼賛会」が成立する。政治は、自らの手で首吊り縄を用意し、自殺した。そして310万人の国民を死に追いやることになる。
除名された斎藤隆夫は、戦中の1942年の総選挙で、翼賛会の推薦を受けられないまま、軍部からの選挙妨害に遭いながらも、兵庫県5区で最高点当選を果たす。国民は信念のある政治家を見捨てない。そして戦後の1946年、第一次吉田茂(よしだ・しげる)内閣で、国務大臣として入閣している。
国民の心に寄り添えず、信念のない政治家は、国民から見捨てられる。今はどうか。迷走する政治を見ながら、そう思う。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『回顧七十年』斎藤隆夫著 中公文庫『回顧七十年』斎藤隆夫著 中公文庫
『評伝・斎藤隆夫 孤高のパトリオット』松本健一著 岩波現代文庫
『日本の歴史24 ファシズムへの道』大内力著 中公文庫