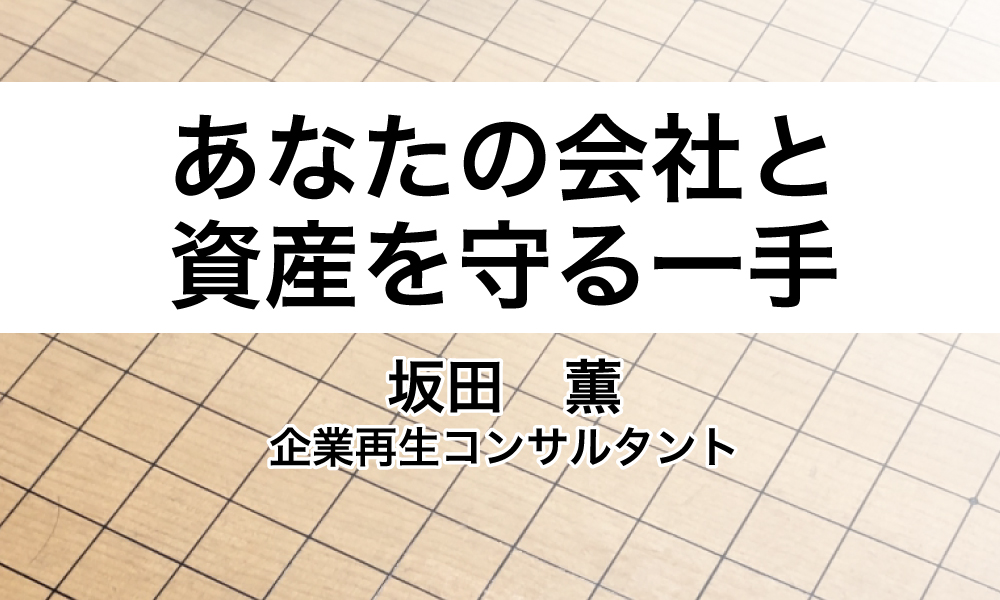主戦論に拘る陸軍
戦争というものは、「勝てぬ」と判断したら、「いかに上手く負けるか」というのが上策である。しかし戦争を始めたものはメンツにこだわり敗北を認めたがらない。
太平洋戦争の場合は、陸軍がその悪弊に陥った。とりわけ開戦の引き金を引いた、時の首相東條英機(とうじょう・ひでき=陸軍大将)は、やみくもに本土決戦にこだわった。
潮目が変わったのは、米軍が太平洋の島嶼に上陸、占領しつつ北上を続け、本土に迫りつつある戦況だった。1944年(昭和19年)6月16日、米軍はサイパン島に上陸する。強気を貫いていた東條は大きな衝撃を受ける。サイパンが陥ちれば、前回触れたように固有領土最南端の硫黄島を含む小笠原諸島を奪われる。そうなれば、本土上陸は目の前の現実となる。弱気となった東條は、皇族で陸軍大将の東久邇宮(ひがしくにのみや)に辞意を漏らしている。
しかし、東久邇宮から、「だから開戦は無謀だと言ったではないか。今さら辞任するというのは無責任ではないか」と叱責されたのを激励と受け取った東條は、以後ますます本土決戦への意思を固めていく。陸軍部内が一致して、「撃ちてし止まん」の破れかぶれに陥り大局を見えなくなりつつあったこともそれを支えた。
東條英機内閣の追い落とし
一方で、外務官僚だった吉田茂(よしだ・しげる=戦後に首相)ら、近衛文麿元首相側近の官僚グループは、東條内閣を打倒して、海軍を中心とした和平政権を樹立することを企てたが、失敗に終わっている。近衛側近の華族の一員、細川護貞(ほそかわ・もりさだ)も、「皇室を残すことのみを条件に無条件降伏する他はない」と、天皇周辺に進言を続けるが、成功することはなかった。しかし、戦争遂行方針をめぐって陸軍と微妙に対立する海軍が動く。密かに東條暗殺も辞さずと動き出した海軍は、内閣改造で事態を乗り切ろうとする東條を追い込んでいく。軍に押さえ込まれながらも不満を募らせる議会の良識派と協力して、海軍大臣を含む人事案に抵抗し、東條は内閣改造を断念し退陣を決意する、7月18日、サイパン島が陥落したまさに同じ日だった。
建前は時間を空費する
後継内閣の首班は、和平への含みを持たせて文官から選ぶべきだという意見もあったが、結局は、戦争遂行の一貫性を重視して、朝鮮総督の小磯國昭(こいそ・くにあき=陸軍大将)に組閣の大命が降った。首相経験者の米内光政(よない・みつまさ=海軍大将)が海軍大臣に復帰して副首相格で入閣するという、陸海軍のバランスをとった軍人内閣が続く。
政風刷新を期待された小磯だったが、「聖戦遂行、大東亜共栄圏確立」の方針を変えず、期待を裏切ることになる。
軍が始めた戦争を軍の責任において終えることは至難のわざだ。責任論が絡むと組織というものは、往々にして勝算がなくても破滅に向かって暴走する。責任をとって舵を切り替えることは、難しい。だからこそ、危機のリーダーには、撤退する決断ができる真の勇気が求められる。勝算なき勇ましさか、撤退することで損失を軽減するか。どちらが真の勇気かは明らかなのだが。
これから一年余り、陸軍は誰も責任を取らぬまま、誰の目にも明らかな敗北を認めず、国民と国家に多大な犠牲を強いることになる。
小磯内閣が、メンツにこだわり、戦争終結の目処をつけられないまま無駄な時を重ねる。海軍は、現実を見据えて水面下で終戦工作を開始する。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『私観 太平洋戦争』高木惣吉著、文藝春秋社
『日本の歴史 25 太平洋戦争』林茂著 中公文庫
『昭和史の天皇 1−4』読売新聞社編