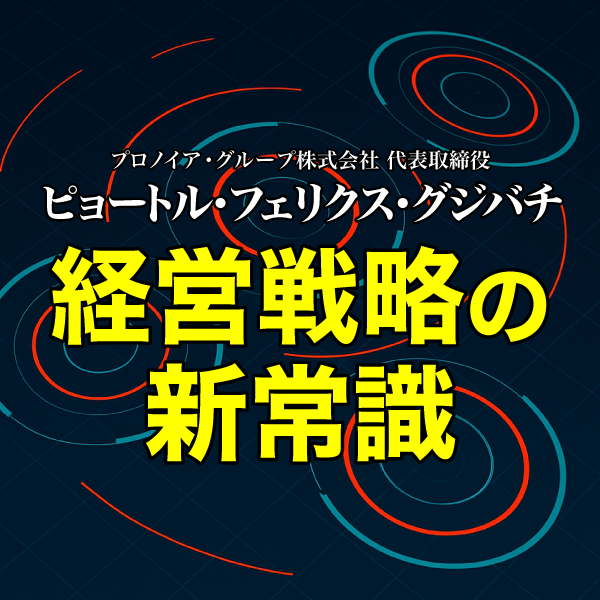- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 挑戦の決断(2) 選ぶのは勝算か義か(大谷吉継)
東軍から西軍へ寝返りの誘い
越前・敦賀城主の大谷吉継(おおたに・よしつぐ)は、居城を発ち関ヶ原を越え美濃へと向かっていた。慶長5年(1600)年7月はじめのこと。関ヶ原合戦まであと二月半、豊臣秀吉没後、五大老の筆頭である徳川家康が発した会津の上杉討伐軍に参加して東下の途上であった。
米原近くの佐和山城に蟄居(ちっきょ)していた石田三成の招きで同城を訪ねた。人払いをした三成から意外なことを打ち明けられる。
「(徳川)家康の横暴は目に余る。このままではお世継ぎの(豊臣)秀頼さまは蔑ろにされ、豊臣の天下は滅ぶ。兵を挙げようと思う。お主も賛同してくれ」
「それは無謀というもの」と、吉継は翻意を促した。
二人は共に秀吉に目をかけられて城主の地位を手に入れた。ともに天下統一に向けて太閤検地に奔走した20年来の友である。幼い秀頼への忠節は同じだが、三成が家康憎しで凝り固まっているが、吉継は家康への遺恨はない。「家康殿に秀頼公にとって代わる野心はない。今歯向かっても勝ち目はない」。
三たびの説得
吉継はいったん垂井の宿所に戻ったものの、友の無茶な決起が気になる。二度も使者を出して説得を試みるが、三成の意思は変わらない。
「計数に明るい武将」として秀吉に重用された二人だが、吉継は秀吉の馬廻衆(うままわりしゅう=側近武将)として、数々の戦功を挙げてきた。軍事戦略家としての家康の強さ、したたかさを理解している。秀吉亡きあとの天下の大勢が見えていた。勝ち目はない。しかし、三成は友を信じて策謀を打ち明けた。その動きを知った上で、友を裏切り家康方で動けるか。兵を垂井にとどめて一週間悩んだ吉継は、ともに反家康側に寝返ることを決断する。
その意思を三成に伝えるにあたって条件をつけた。「お前さんは、わしも苦労した朝鮮の役での諸将の苦労を知らず論功行賞を行い、豊臣恩顧の武将たちの恨みを買っている。しかも石高から見ても、大大名の家康とは天と地ほどの差がある。お前にリーダーは務まらない。挙兵するならしかるべき大将を担がねばならぬ」。的確であった。ともに西軍を立ち上げることになる武将たちは、西の大大名の毛利輝元を総大将に担ぎ出す。
この間の経緯は、家康の情報網に筒抜けであった。老獪な家康は、あえて三成を泳がせて自らは畿内を離れることで「反家康」勢力をあぶり出し、一挙に東西決戦で叩くことを計画していた節がある。三成は、はめられたのである。吉継にも全て見えていた。
義に死す
見えていながら、あえて不利を選んだ吉継の決断とは何だったのか?
吉継は約二ヶ月にわたって関ヶ原に陣取り、岐阜・大垣方面の地勢、敵勢の情報を収集し、勝利の方策を探った。同年9月15日、決戦場で三千の兵を率いて右翼に陣取った吉継の右手背後の松尾山には、その家康側への寝返りが勝敗を分けた小早川秀秋の大軍勢が控えていた。吉継は小早川の翻意も見抜き備えていた。部隊は東軍もたじろぐほどの奮戦を見せて、一時は正面の東軍本隊に加え、小早川の猛攻をも押し返したが、陣内の裏切りに合い力尽きた。
実は、吉継はこのころ、年来の業病(らい病とも言われる)が悪化し、ほぼ失明状態だったという。敗戦が決まるや三成は戦場を離れ北国街道を落ち延びていく。目の見えぬ吉継は、戦況を側近から聞きながら最後の決断をする。本陣から退くことなく従容として自刃し部下に首を切らせた。
吉継の決断は、友情に死んだ美談として語り継がれているが違うだろう。彼は死期を自ら悟り、秀頼公に義を捧げるために関ヶ原に死に場所を求めたのではないか。
逃げた三成は捕らえられ市中引き回しの末に斬首され、鴨川河原に晒し首とされた。吉継の首は、部下の手で関ヶ原に埋められたともされるが、東軍の捜索でも見つからなかった。討ち死の地には今、顕彰碑が建っている。武士の本懐であろう。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『関ヶ原合戦』笠谷和比古著 講談社学術文庫
『関ヶ原の役』旧参謀本部編 徳間書店
『勝つ武将負ける武将』土門周平著 新人物文庫