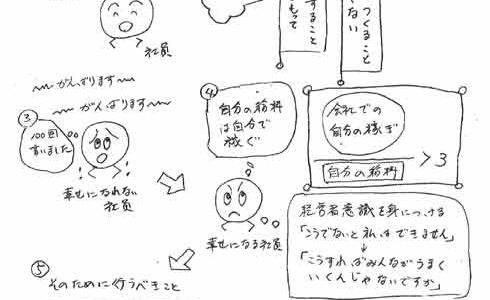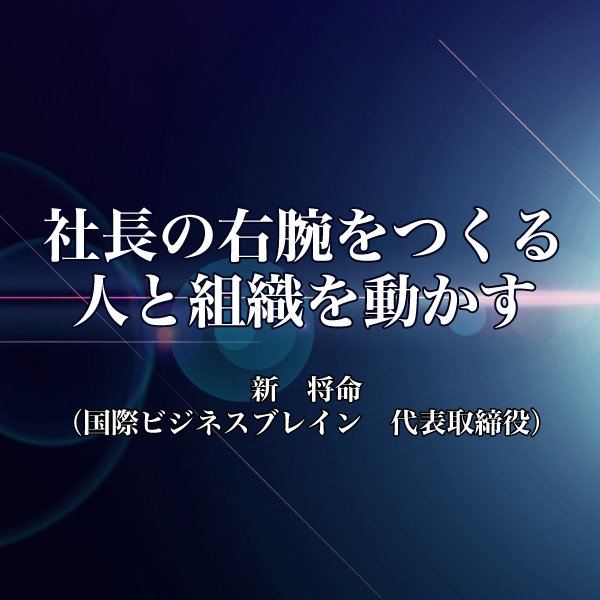わたしのもとには、全国からたくさんの悩めるオーナー経営者が
経営相談に来られます。
その多くが、事業承継で、なかでも最近多いのが、『事業承継税制はいかがでしょうか?』という相談です。つい先日も、四国地方からわが社までそのようなご相談に来られました。
事業承継税制というのは、“納税猶予”のことです。
この言葉のほうが、経営者の間では浸透していますね。
昨年の税制改正で、これまでの制度より使い勝手がよくなったとのことで、
税理士業界では、事業承継の超目玉対策にあげられています。
大手の税理士法人や銀行など、日経新聞の広告でも、
この手のセミナーが数多く開催されているようです。
しかし、私はこの納税猶予制度をお勧めしません。
理由は、3つあります。
①猶予であって、免除ではない。
“納税猶予“という言葉どおり、これは猶予です。
いつかは払わなくてはならず、免除ではないのです。
ところが、ある税理士さんの書籍を見ると、『免除』と書いてあります。
これを見て、経営者は勘違いするのです。しかし、これは猶予です。
ご子息、あるいはお孫さん、さらにその次の世代まで、
いま払わなければならない相続税を先送りするだけなのです。
しかも、使い勝手がよくなったという新制度は、10年間限定です。
今後10年間に限っては、全株式にかかる相続税が猶予の対象となりますし、雇用を継続的に確保しなければならない、という要件が、実質的に撤廃されます。
しかし、11年後にこの納税猶予を使おうという場合は、
全株式を納税猶予の対象とすることができなくなります。
5年間で80%の雇用を維持しなければならない、
というハードルも復活します。
税理士さんのなかには、ずっと納税猶予を使い続ければ、
永遠に贈与税や相続税を支払わなくて済むので、ぜひこれを活用しましょう、という方がいます。
しかし、先に申し上げたように、将来、この納税猶予を使おうという場合は、
いまの緩い制度は使えなくなります。
つまり、かわいい孫の代まで、手足を縛ってしまう、ということなのです。
これを聞いて、納税猶予を使わないと決める方が多いですね。
また、いま納税猶予を使った場合に、これから、その一部でも、誰かに譲渡した場合は、その割合に応じて、猶予してもらっていた税金を払う必要がでてきます。
たとえば、子が父から100株、相続により株式を取得して、
そのあとで子が、自分の子(孫)に50株を贈与したときは、
猶予されていた税金の50%は、そのときに納める必要がある、ということです。ということは、後継者(子)は良くても、その次の後継者(孫)のためには、何も対策ができない、ということになります。
そもそも、この納税猶予という制度がいつまで続くか、わかりません。
少なくとも、今回の改正で行われた緩い条件が使えるのは、
10年間限定であるということだけは決まっています。
15年後、20年後にこの納税猶予を使おうと思えば、もとの厳しい条件を満たさなければいけなくなることはもちろんのこと、もっといえば、グループ法人税制や、少人数私募債の源泉分離課税など、税制改正で使えなくなった制度と同様に、この納税猶予の仕組みが変更されることも十分考えられます。
ということは、やはり、負の遺産(税金)を次の世代が背負ってゆく、
ということになるのです。
デメリットの2つ目は、
②自社株を税務署に担保にいれなければいけないことです。
正確には、猶予された税額に見合うだけの債券、不動産を担保に入れればよいのですが、多くは自社株を担保に入れることになります。
自社株を担保に提供した後に、会社の体制や株式の発行形態に変更を加えることは難しいです。
また、次のような場合、税務署長から担保を増加するよう要求されます。
・合併により消滅
・株式交換により他の会社の完全子会社になる
・組織変更
・株式併合、分割
・株式無償割り当て
もし、将来、猶予された税金を支払えなかった場合は、
株式が優先的に売却されて、その売却代金をもって、猶予税金を支払うということになるのです。
万一の場合、自社株式が誰の手にわたるか分からない、ということなのです。
最後は、③税理士のメシの種になるからです。
現在、税理士業界では、納税猶予ブームです。
税理士も顧問先が減り、顧問料は落ち、
経営的に苦しいという声をよく聞くようになりました。
そんななか、この納税猶予は、
手続の申請、その後のフォローなどで、
確実に手数料(売上)が見込める分野なのです。
こうした事情もあって、税理士からは、
しきりに納税猶予が勧められるのです。
普段、節税提案の1つもしないのに、
この納税猶予はやたらと勧めてくるのは、そういうことなのです。
この3つを聞かれると、みなさん、「えっ!そうなんですか?勘違いしていました!」と言われる方が多いのです。制度の内容を税理士さんが十分伝えきれていない、あるいは、間違って伝えているようなのです。
経営者の皆様には、くれぐれもこうしたことをご理解のうえで、事業承継の対策をしていただきたいと思います。