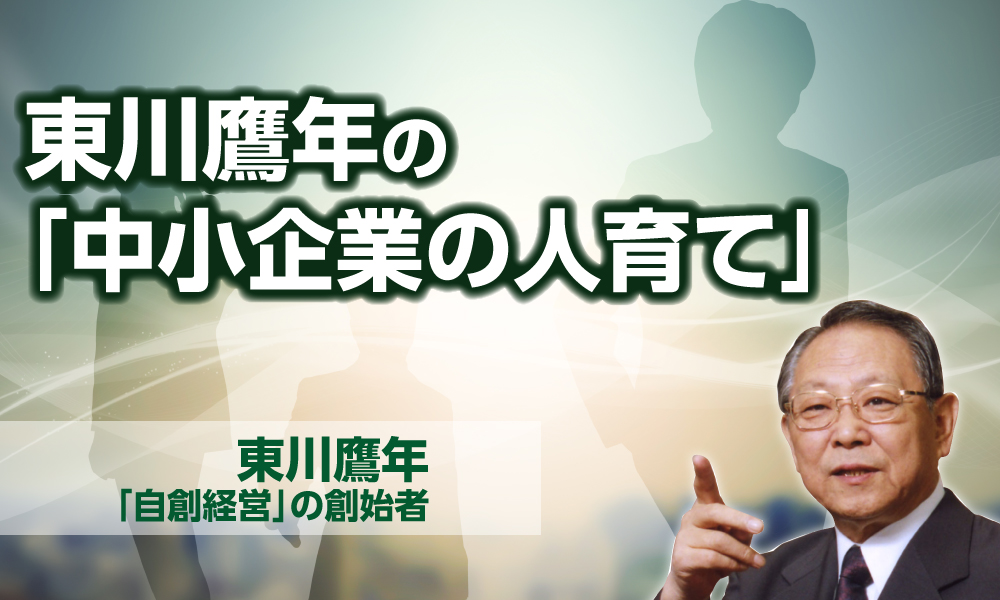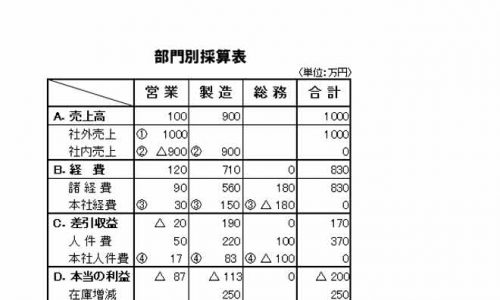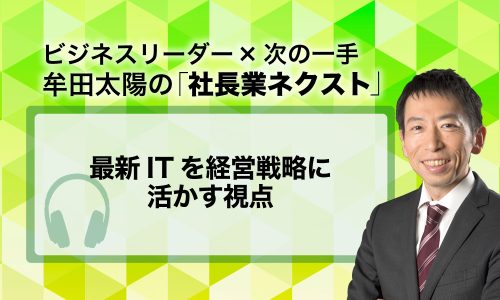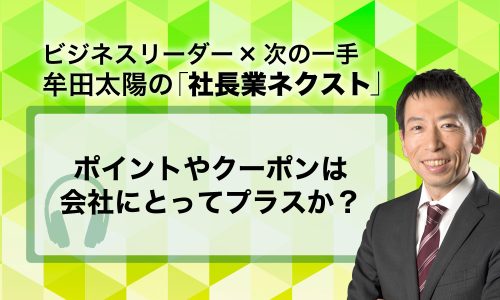- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 挑戦の決断(23) 四民平等の理想(板垣退助)
自由民権運動
明治時代に国民の自由に基づく政治を目指す自由民権運動を率いた板垣退助は反骨の人である。
土佐藩の上級武士の家に生まれ、明治維新期には尊王の立場で、公武合体に動きつつあった藩論を武力討幕へとかじを切り、薩摩藩の西郷隆盛との間で薩土同盟の密約を結んだ。西郷が京都で朝廷を取り込んで兵を挙げると、土佐藩兵を率いて上洛し討幕軍の東山道の先鋒を務め、会津攻めでは周辺の諸藩を新政府軍に寝返らせるなど大きな功績を上げた。
薩摩、長州、土佐、肥前の四藩が主導する新政府で参議の立場に就いたが、明治6年の政変(1873年)で征韓論をめぐって政府主流派と対立し、西郷らとともに下野する。新政府の成立を無視する朝鮮政府へ説得の使者として西郷を送ることに閣議で決定していたのを、欧州視察中だった岩倉具視、大久保利通らが帰国すると、世論の後押しを受けていた閣議決定を覆してしまったことへの反発だった。
「これでは何のための会議なのか」と板垣らはキレた。明治維新の理想として掲げた五箇条の御誓文の第一項にある〈広く会議を興(おこ)し万機公論に決すべし〉を盾に、下野した板垣は、国民の自由権、参政権の獲得を目指し反政府の動きを強めた。自由民権運動である。
藩閥政治への反感
同じく下野した西郷が、維新によって職を失った全国の士族の不平を背景に反政府反乱(西南戦争)を起こして政府軍に討伐されたが、板垣は言論に訴えて全国で早期の国会開設、憲法制定と地租(税金)軽減、不平等条約の改正を求める大政治運動を巻き起こす。
彼が新国家の理想としたのは、身分にかかわらず自由に意見を表明し政策を決定して行くという〈四民平等〉〈自由主義〉の理想だった。尊皇の意思が強かった板垣は、天皇と広く国民が理想の政治を目指す〈君民同治〉を掲げている。同じく四民平等を言いながら、政権を握った薩長の一部士族らが天皇という権威を操る藩閥政府主流の〈知らしむべからず寄らしむべし〉式の権威主義的政治思想とは全く相容れないものだ。
西洋思想に触れることもなく育った板垣が、西洋近代の自由主義思想ともいうべき発想を獲得できたのは、土佐藩士時代の経験によるところが大きいようだ。
義理堅く喧嘩っ早い彼は、正しいと思えば歯に衣着せずに藩主にも意見し、幾度か蟄居を命じられている。ある時、蟄居が解かれ地域の徴税官として赴任した。過酷な年貢の取り立てで住民たちの反感が強い地域だった。着任するなり板垣は農民たちに言った。
「不満があれば言え。それで処罰はしない。お前たちが意見を言うことで藩政もよくなるんだぞ」。自ら農民や職人たちとも交流し、問わず語りで実情を探る。もっともな意見は藩の上層部へ取り次いだ。改善点があれば具申した。それでまた彼は上司からにらまれた。いつの時代でも官僚統治機構とはそうしたものだ。風通しが悪い。権威主義的で効率が悪い。
企業も組織が大きくなると、同じ弊害が蔓延する。気をつけるべし。末端社員の本音が聞こえなくなったら、トップ自らが率先して社内で自由民権運動を。
本音で語る男
自由民権運動は、明治政府からは、民衆を煽る危険な政治運動とみなされた。明治天皇が10年後の国会開設を約束する詔(みことのり)が出された翌年の明治15年(1882年)4月、板垣は岐阜で遊説中に暴漢に襲われ刺される。一命をとりとめた板垣は、欧州へ半年の視察に旅立つ。明治政府が政治思想の模範としてあがめるハーバート・スペンサーと会ったときのこと。自由に関する彼の著作を読んでいた板垣は、本音をぶつけている。
「白色人種が語る自由とは、実質としては有色人種を奴隷のごとく使役した上に成り立っている自由であり、白人にとって都合の良い欺瞞に満ちた自由である」
筆者には、正論とも思える挑発だが、スペンサーは激怒した。「ようやく封建主義を脱したばかりで憲法も持たぬ日本が、西洋と肩を並べようとは傲慢だ」と席を立った。
日本はこの時、幕末に列強から押し付けられた不平等条約から逃れられないでいた。条約改正は板垣の政治要求のうちの大眼目の一つだった。礼儀など構わず権威に対しても本音で語る。板垣の面目躍如のエピソードである。
西洋文化、文明をただただ模倣することが近代化への道と盲信していた維新政府のリーダーたちには思いもつかぬ発想と、問答作法ではあった。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『板垣退助』中元崇智著 中公新書
『日本の近代2 明治国家の建設』坂本多加雄著 中公文庫