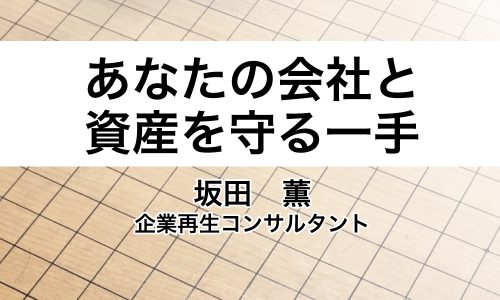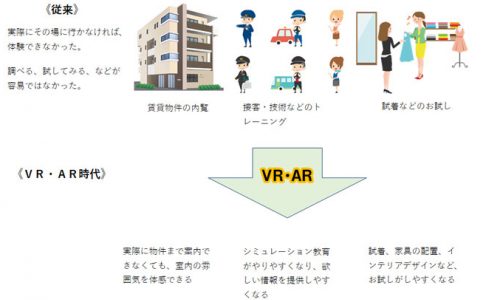「売上100億円を目指す!」「店舗数1000店舗を目指す!」等など、経営規模の拡大を目指す掛け声を、多くの場面で見かけます。しかし、経営は規模が大きいから良い、というものではありません。倒れたら元も子もないのです。
1)規模の拡大より、長く続けることが大事
顧問先のひとつに、墓石などの石材を扱う会社があります。創業90年です。90年間、営業赤字は一度もないのです。企業規模は年商約3億円です。
特にこの約10年間は、土地のオフバランスや退職金など、意図的な赤字をうまく活用して節税を図ってきました。その結果、現在の自己資本比率は90%超です。不況の荒波が来たとしても、この会社よりも先にライバルがどんどん倒れてゆきます。ライバルが倒れれば、生き残った会社へと、お客は流れます。もはや盤石な財務体質なのです。
この会社が規模を追っていたら、どうっだったのか?四代目社長に聞いたことがあります。その社長は言いました。
「うちの業界で規模を追っていたライバル会社はみな、倒れました。石材の市場が縮んだ時に、軒並み倒れていったんです。」
そのような現実を見てきたからこそ、その会社の社長も事業の規模を追うことなく、地域の中で長く生き残る経営に注力されているのです。
2)粗利益が下がりやすい
売上規模を追い始めると、幹部もスタッフも、とにかく売上を追うようになります。目標を売上高にするのは、社員にとってわかりやすいです。
しかし、この掛け声がきつくなるほど、売上高は伸びるものの、儲けは減ってゆきます。結局、売上ノルマを達成するため、ライバルよりも安値で売ってしまう、ということがじわじわ増えてくるのです。
最初は抵抗があるものの、同じような安売りを経験してゆくうちに、「まあいいだろう。」「売上目標を達成するにはこうするしかない。」などと、営業担当の中でも正当化されてゆくのです。気が付けば、売上高は伸びたものの、粗利益率は落ちて、営業利益はそう大して増えていない、となるのです。粗利益こそが、固定費をまかなう原資です。売上高を伸ばすことにいくら掛け声をかけても、粗利益が落ちては意味がないのです。
顧問先で、粗利益を目標としている会社があります。各種経費をまかなうための粗利益を明確にし、全社で粗利益の目標を共有化されているのです。なので、その会社では安売りは起こりません。
「売上を追うだけでは、必要な粗利益を確保できない!」
「粗利益を確保できれば、給与を上げることもできる!」
といったことを、社長自らが講師となり、社員への勉強会を定期的に行っておられるのです。完全なる、粗利益主義の経営なのです。規模を追うわけではなく、必要な粗利益を追う。そうすれば、おのずと売上高も伸びてゆきます。売上高は、伸ばすものではなく、結果として伸びるものなのです。
3)固定費がどんどん増える
規模拡大のために拠点が増えると人数が増えます。労務費や法的福利費が増えるのは当然のことながら、そのほかの間接費用も増えます。採用費、研修費、旅費交通費、健康診断、制服、ロッカー、駐車場など、何かと間接的なコストが増えるのです。
さらに、人が増えるとトラブルも増えます。パワハラ、セクハラをはじめ、不祥事を起こす、人間関係や金銭のトラブル、メンタルがやられて勤務不能になる、などなど。人数が増えるほど、人トラブルの種は増えるのです。
やがて、事業拡大に人が付いてゆけず、社員が悲鳴を上げ始めます。あちらこちらでトラブルの火消しが必要になってきます。トラブル対応にも、コストがかかるのです。このような状況で、多拠点展開する前と同じ程度の利益率を維持するのは、至難のワザなのです。
4)人材が追い付かない
売上規模の拡大を目指すと、拠点が増え、人数が増えます。そうなると、今まで以上に管理者人材が必要になります。しかし、どの業界においてもいま困っているのは、管理者人材がいないことです。人数がいても、そもそも管理者になりたくないという従業員が多いのです。
“管理者になっても、給与はそう大して増えないわりに、今の上司を見ていると、責任ばかりで疲弊しきっている。そんな風になるのは絶対にイヤ!”
と考える社員が、中小企業の場合は多いのです。
社長が規模拡大への舵を切り始めると、「人材なんてどうにでもなる。」と思いがちです。そんなことはありません。ましてや昨今の人手不足です。拡大するほど、通常の採用では人員をまかなえず、派遣会社や紹介会社への支払いが、雪だるま式に増えます。売上は伸びても、残る利益率はどんどん薄くなります。今のような人手不足の時代、労務コストは最も高くつきます。デフレ時代の感覚で規模の拡大を図ると、人材補給が追い付かず、業績は一気に落ち込んでゆくのです。
5)規模が大きくなるほど、環境変化に適応しづらい
会社経営は長期戦です。20年、30年を経過してゆくなかで、取り巻く環境は大きく変わります。環境が変われば、経営のやり方にも変化が必要です。この、変化に適応するということが、事業規模が大きくなるほど難しくなります。フットワークが重くなってゆくのです。
今から約30年前、ドコモなどの携帯ショップができ始めました。その後、“これからは一人1台、携帯電話を持つ時代に突入する!”と、携帯ショップがどんどん増えました。運営会社も最初の10年~20年、携帯電話が子供から高齢者まで普及する過程で、大いに儲かりました。
しかし、今となっては人口減少もあり、普及台数が増える環境にはありません。路面の携帯ショップへ行かなくとも、インターネットで完結するという売り方も出てきました。こうなると、店舗数が多く従業員数も多い、店舗の土地を自前で持っている、といった会社はそれだけで変化への適応が遅くなります。
加えて、携帯ショップ以外に事業の柱がないとなると、なおのこと適応しづらいです。稼ぐ柱が複数あり、各柱の事業規模がそう大きくない会社は、携帯ショップはもうやめて、まずは別の柱に注力しよう、人材もそちらへ移行してもらおう、等と手を打っておられます。
今はスペシャリティでも、30年後にはコモディティ化する、というものは、いくらでもあります。今は売り物になるサービスが全く不要になる、ということもあります。稼ぐメシの種は、将来の環境変化を見据え、事業内容を変えることを前提に考えておいてほしいのです。だから、ひとつの事業での売上規模を、追いすぎないでほしいのです。