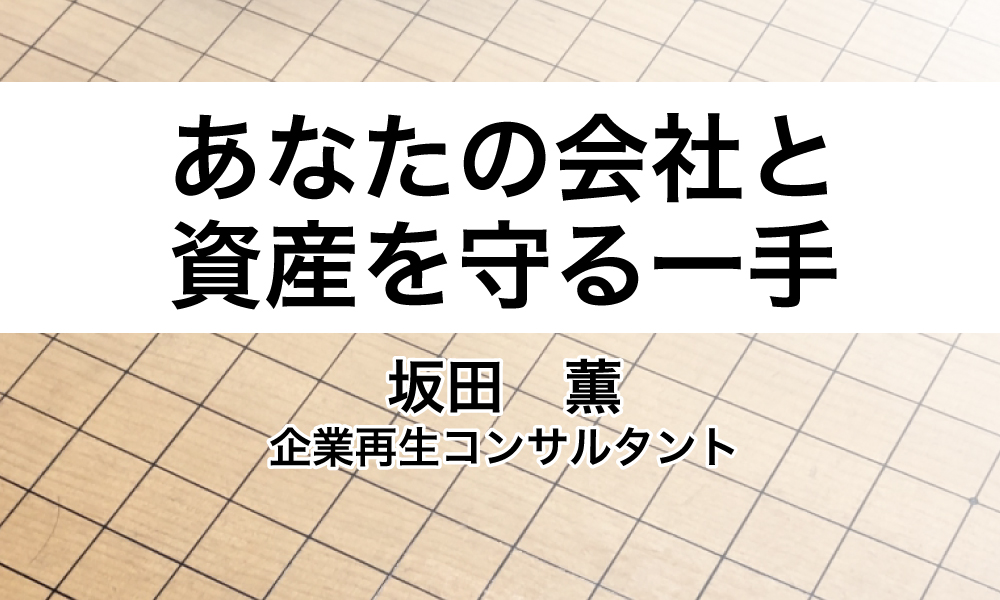商社ブームの到来
第一次世界大戦(1914〜1918年)を契機に、わが国では戦時軍需物資の欧州向け貿易を担うようになり、われもわれもと商社設立ブームが起きたことは、この連載で触れた。その中で、古河財閥が1917年に設立した古河商事はわずか四年で破綻し姿を消した。なぜ短期間で消えてしまったのかを考えてみる。
商社設立ブームは必然であった。まずは、戦場とならなかった日本が、米国とともに、欧州各国への物資の供給源として期待されたこと。その輸出に際してこれまで商社機能を果たしてきた英国、ドイツの商社の東京支店が機能しなくなったことがある。
古河財閥は、京都出身の初代・古河市兵衛(ふるかわ・いちべえ)が、明治初期に各地の鉱山の払い下げを受けて財を成した。明治10年(1977年)には、栃木県の足尾銅山を買収して近代技術を導入して国内最大の銅山に育てあげた。同鉱山の銅産出量は、わが国全体の半分を占めるまでになる。
「赤ガネ以外に手を出すな」
ここに辿り着くまで市兵衛は、生糸輸出、米穀取引で失敗を繰り返している。そこで彼は、ドル箱の銅商いに専心し、「赤ガネ(銅)以外には手を出すな」と公言し、これが古河の不文律となっていた。他の取り扱い品目は、銅製錬に不可欠な石炭ぐらいなものだった。
この遺訓は、市兵衛の死後も、番頭たちが頑なに守り、三代目の虎之助の時代に商社ブームが起きて、社内の営業部から起こる「取扱品目を増やすべきだ」との突き上げにブレーキをかけていた。大番頭の近藤陸三郎が1917年に死去すると、一気に商社を設立する。「好況に乗り遅れるな」の声がまさった。
同じころ、内務官僚出身でやはり銅山(別子銅山)経営が主力だった住友のトップの総理事に就いていた鈴木馬左也(すずき・まさや)は、多方面の情報を整理して、社内の商社設立の動きに、「住友にはいまだ、商社のノウハウはない」として、商社設立計画を白紙に戻している。まったく対極の決断だった。
負の連鎖を避ける扇子商法
商いとは、時代とともに変容してゆく必要がある。それは事実だ。いつまでも初代が打ち出した旧時代の遺訓を墨守(ぼくしゅ)するだけでは事業に発展性がない。しかし一方で、やみくもに時代のムード、ブームに乗ってはやけどするのも、真理だ。
銅は戦時に軍需品として重宝される商品であるのは間違いない。しかし、1918年11月に第一次大戦が終わると、銅は加工品の電線も含めて世界的にだぶつき価格が暴落した。これが破綻の序章だった。古河商事では、取扱商品の多角化の一環として、肥料として需要が急増する満州地方の大豆粕を増やす。これで銅製品取引で開いた穴を埋めようと試みる。しかし、大連支店では、一気に勝負をかけて先物取引に邁進し、目論見がはずれて市況が大暴落し大きな損失を抱え込む。さらに支店ではこの損失を隠蔽したことで本社の対応が遅れ、銀行は融資の引きはがしで、古河商事を見放し、1921年に入ると破綻した。
小さな破綻の芽を穴埋めしようと悪あがきしている間に負債はどんどん膨らむといいう、ギャンブラーが陥りがちな負の連鎖にはまってしまったのだ。
好況と不況は循環する。好況のときに目の前の短期のビジネスチャンスに飛びつくと人材も資産も注ぎ込むことになる。チャンスにトライするなら必ず訪れる不景気への対応が必須なのだ。
大阪船場の商人の間では、「扇子商法」という言葉がある。商いとは、好景気の時には扇子をいっぱいに広げ、不景気の時は扇子を畳んでやり過ごせ、という商道の極意である。
追い風に上げた帆も、畳みどきを間違えると、風雨に翻弄されて船は沈むことになる。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『日本の15大財閥 現代企業のルーツをひもとく』菊地浩之著 平凡社新書
『財閥の時代』武田晴人著 角川ソフィア文庫
『財閥のマネジメント史』武藤泰明著 日本経済新聞出版