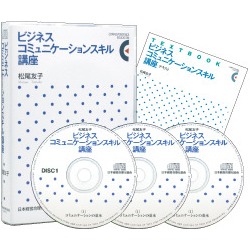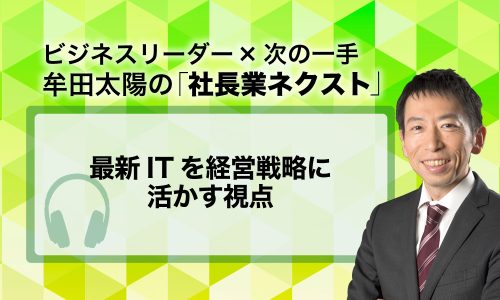武装中立
欧州の地図を開いてみる。その中央部に、EU(欧州連合)にも、NATO(北大西洋条約機構)にも加盟していない国がある。アルプスの高峰に取り巻かれた高原盆地に位置する人口896万人の小国、スイス連邦共和国だ。スイスと聞くと、牧歌的な平和イメージが浮かぶ。実際にいかなる軍事同盟からも距離を置く永世中立国として国際的に認められている。
しかし、アニメ「アルプスの少女ハイジ」で日本人が描くのどかな平和イメージとは違っている。スイスが目指すのは「武装中立」だ。国民皆兵制度を敷く民兵国家で、20-50歳の男子全員に兵役の義務があり、定期的に軍事訓練を課し予備役として登録され、小火器は自宅に保管されている。常備軍としての職業軍人は4,000人に過ぎないが、有事となれば、6時間で30万人の予備役が招集可能な体制を敷いている。陸軍、空軍それぞれに最新鋭の兵器を装備している重武装国家なのだ。
「自ら戦争を放棄さえすれば、どこの国も攻めて来ないだろう」などというどこかの国のように極楽トンボ的な発想はない、牧歌的なアルプス山中の小屋に戦車や大砲がカムフラージュされて配備されていて、敵が攻めてくるだろう要路のトンネル、橋には敵軍の進軍を阻止するための爆薬が仕掛けられている。
こうした臨戦体制を怠らない背景には、周囲の大国に振り回され侵略されてきた歴史がある。
大国の力関係のはざまで生き残る
古代ヨーロッパの地政学について書かれたカエサルの「ガリア戦記」に、現在のスイスは「ヘルウェティ族の国」として登場する。当時の超大国であるローマ(イタリア)がガリア(フランス)、ゲルマン(ドイツ)に軍事遠征する際には、まっ先に攻略されている。
中世にも、フランス、イタリア、神聖ローマ帝国(オーストリアから南ドイツ)の間の戦争に、まだ小さな州の緩やかな連合体だったスイスは巻き込まれ、振り回された。
こうした歴史の中で、山岳国家のスイスが培ってきた有力な資源が、山岳ゲリラ戦で鍛えられた屈強な戦士たちだった。周辺各国で傭兵戦力として重宝がられ、盛んに“輸出”された。先日、コンクラーベ(教皇選挙)が行われたバチカンの衛兵をスイス兵士が務めるのもその名残りだ。
ナポレオン戦争後に増す存在感
18世紀末にフランス革命が起きて王政が瓦解するとヨーロッパ中に衝撃が走り、混乱が生じる。とくにナポレオンが1799年に実権を握り、皇帝に就任するとフランス軍は、革命の波及をおそれるイギリス、プロイセン、オーストリア、ロシアの連合軍を相手に大戦争を仕掛ける。スイスも両軍の進撃路として侵略されるが、一方、国民の間に近代国家建国の意識が芽生えていく。小州の連合体は、協議機構を整えて憲法に基づく連邦共和国の体制に向かっていく。
ナポレオンの敗北後、戦後処理をめぐるウィーン会議(1814−15年)で、スイスは国家として独立を認められ、周辺大国の影響を排した永世中立の国是を承認された。
折しも、イギリスでは、蒸気機関の活用による産業革命と資本主義の進展が始まりつつある。新生の小国スイスは、いち早く動力革命に注目し、蒸気船をライン川などの物流に、また、登山鉄道に蒸気機関車を導入して観光拠点の礎を築く。匿名性の高いスイス銀行口座は、欧州の資本を吸収してゆく役割を果たした。大国に取り囲まれた地政学的な弱点は、周辺勢力のバランスを利用した緩衝国としての立場を強めてゆく。
山岳ゲリラ戦略を想定する武装中立路線はまさに小国の生き残りの知恵だった。(この項、次回に続く)
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『一冊でわかるスイス史』踊共二監修 河出書房新社