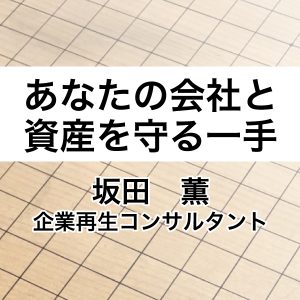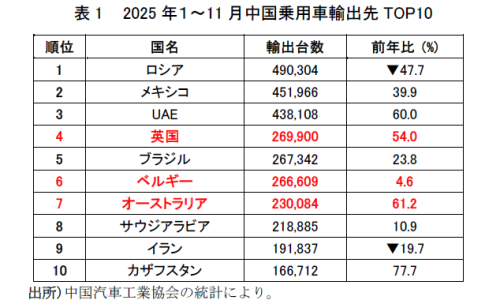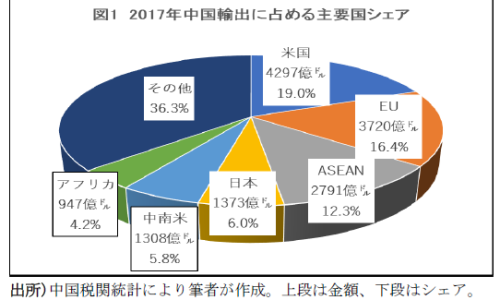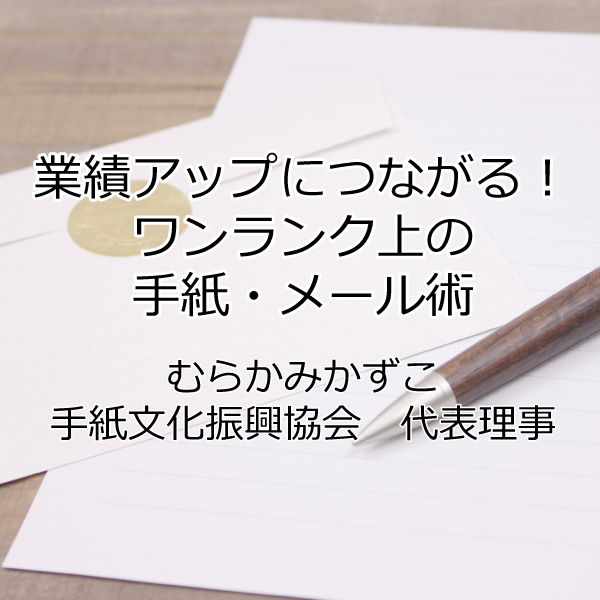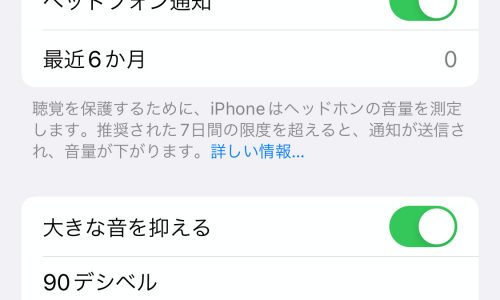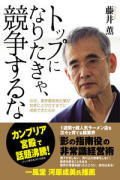会社の領収書を確認していると、怪しいと思えるものに出会うことがあります。それらのほとんどが手書きのもので、仕訳科目で言えば交際費、会議費に該当するものや個人から購入した消耗品に該当するものです。じっさい数年前まで経理担当役員をやっていた会社でもこのようなものをみかけたこともあり、管理の甘い会社ではこういった領収書で脱税や不正がおこなれるのかもしれないと思うこともありました。
交際費や会議費の対象となる飲食店によっては、いまだに白地の領収書を発行する店もあり、取引先の誰と何人で行ったかだけでなく、金額、日付けの筆跡までもチェックしないと後で問題になることもあるのが実状です。
ところで、会社のものを不法に自分のものとする、いわゆる横領についてですが、単純に現金を抜いていれば現金の照合ですぐに犯罪が発覚してしまうため、架空の領収書をでっちあげたりという手口が使われるケースがあります。そんなときに前述の手書きの怪しい領収書が使われることになるわけですが、会社にしてみれば架空や、捏造された領収書の金額がすでに経費として損金計上されているため横領された金額以上の損失になることが多くあります。
具体的に書くと、税務署が調査にはいり、架空の領収書による横領がみつかり、その金額分だけ経費が否認され損金で落ちないこととなるわけです。これはその分利益が増えることを意味し、追徴課税の対象となるのです。 ただし、さいわいなことにこれらの事実では「仮装隠蔽」(注1)という要件を単純には満たさないため重加算税を課されることは少ないはずですが、修正申告を要求され、その利益によっては追徴課税されると理解していたほうがよいかと思います。
業務上横領は初期の段階で見つかればいいのですが、時間とともに被害額も増えていきます。これだけでも被害は甚大なのに、税務調査でまれに重加算税が課されるケースもあります。
経営者にしてみれば自分がやったことでもない犯罪でむしろ被害者であるにも関わらず重加算税とは常識では考えられないのですが、そういうこともあり得る程度には理解しておいた方がよさそうです。
ところで、横領によって会社が損失を被った場合、会社はそれを雑損失に計上できますが、同時に加害者である従業員に対して損害賠償請求権という資産をもつことになります。法人税基本通達(注2)では一般的に、そのおカネを返してくれることが確定したときにそれが資産計上されるものとなっていますが、横領の場合はこの通達は使えないのです。(注3)
これは横領されて事実上損失が発生しているのにもかかわらず、税務上、純粋な損失の発生としては認めてはくれないということを意味します。
つまるところ、多くのケースで横領された場合、その被害は横領金額以上に増えていきます。このようなことにもならないために経理や監査がいかに重要か理解しないと思わぬ罠にはまることがあるものです。
注2: 損害賠償金等の帰属の時期
法人税基本通達2-1-43
他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」により改正)
(注) 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により ほてんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
注3: 不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期 -法人の役員等による横領等を中心に- 参考ページ国税庁HP
法人税基本通達2-1-43について、「・・・・・・その相手方が「他の者」に当たらない場合、すなわちその法人の役員又は使用人である場合には、通達上その取扱いは明らかにされておらず、上記通達の趣旨解説において「例えば、役員の場合にはその行為が個人的なものなのか、それとも法人としてのものなのか峻別しにくいケースが多いことから本通達をそのまま適用することには問題がある場合が多い。」とし、「役員又は使用人に対する損害賠償請求については本通達の取扱いを適用せず、個々の事案の実態に基づいて処理することとされている。」と記述されるにとどまっている」
「1 その損害がその法人の役員又は使用人による横領による損失であるような場合には、通常、損害賠償請求権はその時において権利が「確定」したものということができるのであるから、被害発生事業年度において、当該損失の額を損金の額に算入するとともに、損害賠償請求権を益金の額に算入する」
(上記参照ページよりの抜粋)