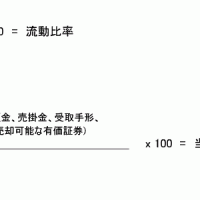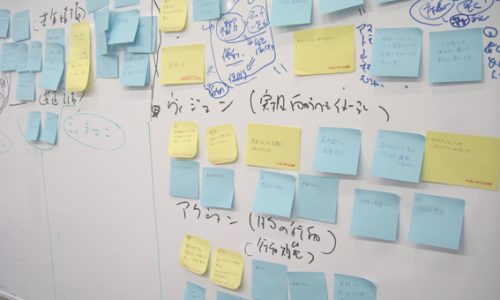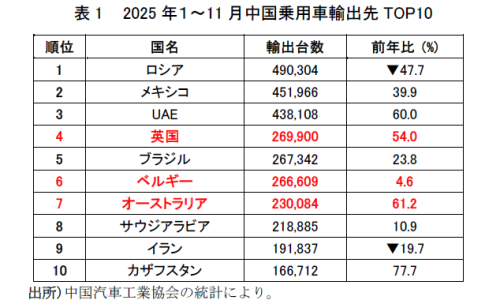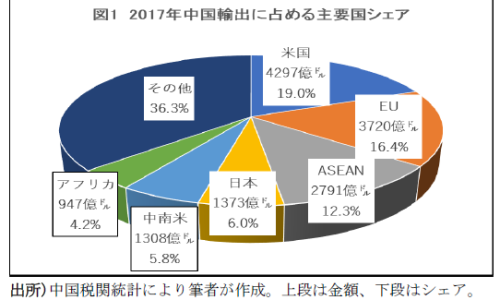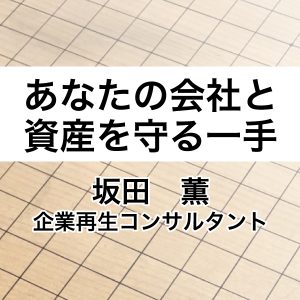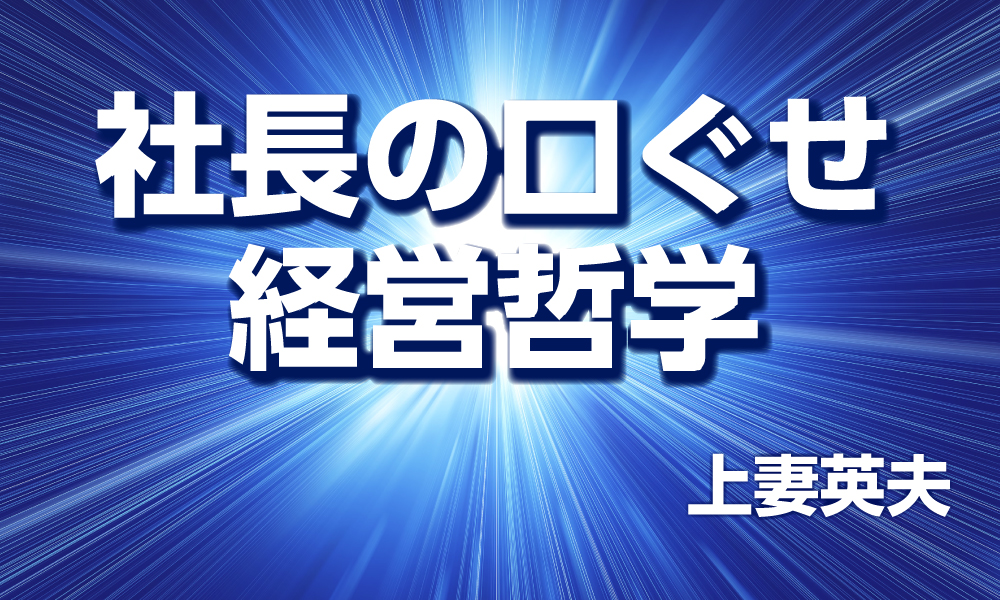銀行融資の延滞と、税金や社会保険の滞納とでは、債権者の取り組みはあきらかに異なります。
回収余力のある担保不動産があるか、ないかによってと、返済に協力的か否かによっても対応は違いますが、おおむね銀行は経済原則にそくして行動してきます。つまり、債務者の現状を見て、より多く回収できるならそちらのほうを選びたがります。ただ、そこに信用保証協会がからむと対応はまた変わってきますが・・・
銀行に比べて税の滞納や社会保険の滞納においては、租税平等原則(注1)があって、どの滞納者でも同じ扱いをしなければならないため、情け容赦なく取り立てしてきます。じっさい税務署や役所に滞納者が相談に行っても、そこで話は聞いてくれるものの、交渉はできないのがふつうです。納税は国民の義務だからしょうがないのですが、徴税する側は納税を猶予する制度にあてはまるかどうかを検討し、あてはまらなければ、滞納者の資金繰りや回収状況などはあまり考慮してもらえません。滞納者にしてみればこれは非情に感じるものです。
たとえば、先順位の債権者がいて余力がないだろう不動産があった場合、銀行はその不動産に差押えをしてきませんが、税務署や役所は平気で差押えをしてきます。1円も回収できないとわかっているのにです。(注2)
さらにいえば、銀行と、税務署などの役所とでは情報収集能力の点で格段の違いがあります。役所の場合、国税総合管理システム(KSK)を使えばどこからどんな収入があるかがわかり、市役所の徴税担当者でも相手が会社であれば決算書の内容も見ることができてしまいます。
さらにはNTTデータが提供するPipitLINQ(注3)を使えば預金の情報もかんたんに取得できます。
中小企業が一度破たんして返済遅延や税の滞納が発生した場合、これらの制約を考えながら行動することになります。そしてほとんどが破たん初心者であることからどこかで落とし穴にはまることになり、再生できないことになります。
再生することを決断しても、民事再生ができる場合などを除けば相談した弁護士は破産をすすめてきます。だから、もしも再生したいという気持ちがあって、民事再生などができないのであれば、一度、信頼できる中小企業の再生専門家の話を聞くことが重要になるのです。その話を聞いてから、未来を選択しても損はないはずです。
(注1)wikipediaより引用
租税公平主義(そぜいこうへいしゅぎ)または租税平等主義、租税平等原則、公平負担の原則、租税負担の公平原則とは、租税負担を納税者の担税力に即して公平に配分しなければならず、租税法律関係において納税者を平等に取り扱わなければならないという租税の領域における平等原則である。
(注2)
国税徴収法第四十七条 (差押の要件)
次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
地方税法第三百三十一条 (市町村民税に係る滞納処分)
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき
(注3)預貯金等照会業務のデジタル化サービス「pipitLINQ」