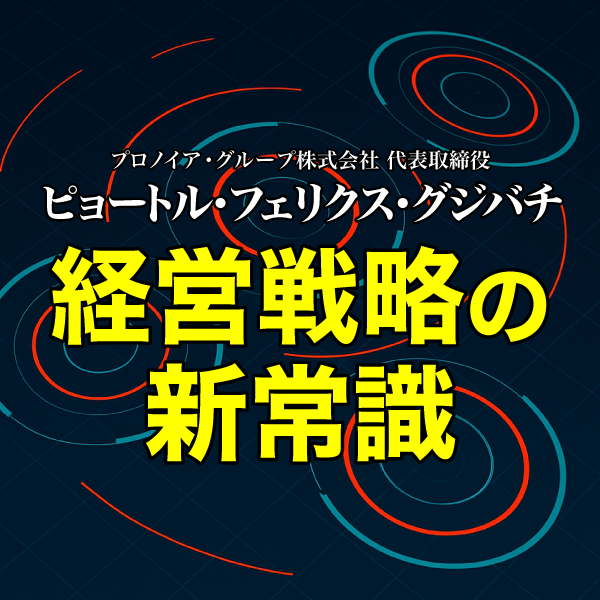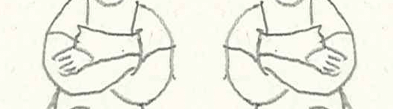2021年の時点で、我々が義務教育期間中に教わる漢字は2,136、そのうちの約半分の1,026文字を小学校6年間のうちに習う。これにひらがな、カタカナを加えたいわゆる「漢字仮名交じり文」をいとも簡単に書いている姿は、他の国から見れば何とも不思議であり、日本人の知性の高さと日本語の難しさを感じさせるかもしれない。
もっとも、端で眺めるのではなく、覚えて書く身としては容易なことではない。最近はすっかりコンピュータ頼りで、習ってもいない難しい漢字も使える代わりに、習った漢字が満足に書けない、笑うに笑えない逆転現象がどこの職場でも起きているだろう。
私は戦後の生まれで直接に習ったわけではないが、「旧仮名遣い」と言われる「歴史的仮名遣い」が加わる。「てふてふ」と書いて「ちょうちょう」と読ませる類のものだ。さすがに、戦前の書籍でもない限りは目にする機会は減っているものの、私のように物を書く仕事をしていると、明治期の本などを読む時には歴史的仮名遣いから逃げるわけには行かない。さらに、江戸期にの書物には崩し字が加わり、お手上げに近いこともある。昔の人は頭がよかったのだなぁ、と感心することしきりだ。
資源の乏しい日本は加工に優れた能力を発揮するとは昔から知られた事実だが、それは商売の品々ばかりではない。「漢字」も「漢」が付くことからも中国由来の文字なのは明白だ。しかし、普段われわれが使っている漢字の中で「国産」の物も数は多くはないが存在しており、これを「国字」と呼ぶ。
例えば「峠」。山の上と下とを分ける境目を意味する。この本来の意味が拡大し、大きな分かれ目を迎える際に使われることもある。しかし、この文字は日本で造られた文字なのだ。
「辻」。偏の「しんにょう」は人が多く集まる場所を差す。「十」は交差点を現わしたもので、「辻」は確かに人が多く集まる場所を意味する漢字になる。そこに立ち、いろいろな話をして通行人から僅かな喜捨を求める行為を「辻説法」と呼ぶ。なるほど、と思わせる語源だ。
「畑」。「田畑」と言うが、「畑」は日本オリジナルの文字だ。田んぼで稲をたわわに実らせるには、土の手入れが大事だ。しかし何年も続けていると、土が痩せ、米を実らせるほどの肥沃な栄養を失う。現在であればそうなる前に土を肥やしておくことは造作もないが、土が本来持っている養分や力に頼らざるを得なかった時代には、土を生み出すだけの力が田になくなると、田を焼き、畑として次の活用法を見出した。縄文期以来、「焼き畑農業」が日本でも行われていたが、これは山林や雑木林などを焼き、灰を肥料として数年その土地を寝かせて畑に転用するものだ。
日本でできた「国字」は、その意味を端的に現わしており、「なるほど」と別の側面で漢字への興味を掻き立ててくれる。
その一方で、「だから何なのだ」という意見もあろう。「漢字」としてみんなが認識し、問題なく使えていれば、中国産だろうが国産だろうが構わないではないか、と。まさにその通りだ。しかし、国字を生み出す発想は「何か」に似ていないだろうか。例えば輸入食品、あるいは加工食品。前者は国産より安く、多少味は落ちるかもしれないが、わが国得意の技術で補える。後者は、海外から安く仕入れた原材料を変身させ、元来の姿よりも美味しい食品に変身させて食べさせる。「カニかまぼこ」を見て、原材料になっている魚の姿を思い浮かべる人は少ないだろう。
こうした食品などは原料仕入れの資金が必要だが、文字を書くのにお金を払う必要はない。しかし、「オリジナルを加工して、新たな物を生み出す」発想は、食べ物や衣料品などの消耗品の範囲を超えて、日本の伝統文化の中で営々と続けられて来たことなのだ。
形のある商品の加工や変化などだけではなく、「無形の精神」ないしは「考え方」などに、こうした先人の発想を応用することで、更に視野が広がる可能性はないのだろうか。視野を広げ、新たな発想を生むための要素はいくつもあると思うが、その一つが「柔軟性」ではないだろうか。組織が硬直化すると途端に業績が落ちるように、トップやリーダーの思考が常に柔軟性を保っていることは必要だ。新将命の著書の中にも「組織は頭から腐る」との言葉があり、まさにその通りだ。一見突拍子もないものを結び付ける発想を頭から否定するのは簡単な話だ。しかし、それでは先がない。
多くの産業分野で行われてきた「ないものは新しく作ればいい」との発想。これが「国字」が果たした大きな役割の一つではないだろうか。その範囲や分野、他の例もたくさんあるはずだ。何も考えることなく使っていた「文字」をきっかけの一つとして、ビジネスアイディアを生み出すこともできる。
世の中、身の回りには、見方を変えることで違ったものが見えてくる事象の何と多いことか。先人が積み上げてきたものは、すべてが勉強や発見の素材になる、と言っても言い過ぎではないだろう。