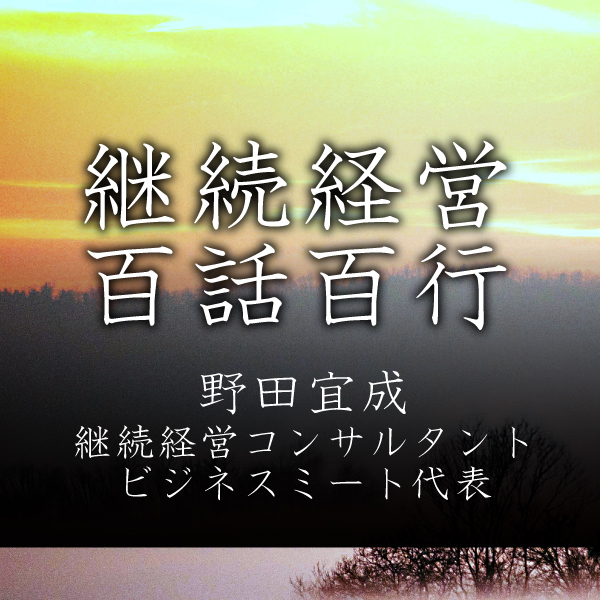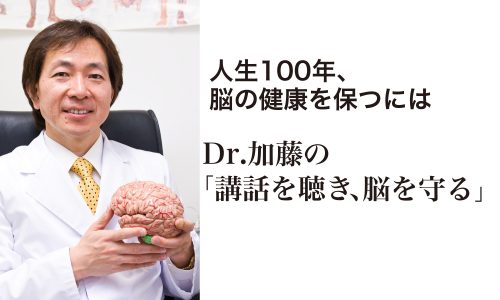陸上戦の分岐点
ガダルカナル島は、南太平洋のソロモン海に浮かぶ四国の3分の1ほどの島だ。連合軍にとっては太平洋を機動移動する米軍と、オーストラリア軍とを繋ぐ結節点にある。ミッドウエー沖海戦(1942年6月)で米機動艦隊に大敗した日本軍としても南太平洋の制海、制空権確保のために譲れない要地だった。
海軍は同島のジャングルを切り開き飛行場建設を始めていたが、同年8月7日、米海兵隊1万900が突如上陸作戦を敢行し、日本海軍の飛行場設営隊を駆逐し、完成間近の飛行場を占拠した。
米軍の陸戦での本格反攻は翌年からだとタカを括っていた大本営は慌てた。
グアム島から一個支隊2,000を呼び寄せて島の奪還に当たらせることにする。上陸した米海兵の規模も同程度だろうと誤認していた。一木清直(いちき・きよなお)大佐率いる先遣隊900は8月18日夜、駆逐艦に分乗して上陸し、後続部隊の到着を待たず飛行場を守る米軍陣地に向かう。悲劇の始まりだった。
増派しても生かされない教訓
勢力判断を誤っての多勢に無勢。しかも敵海兵隊は、盤石の防御網を敷いて待ち構えている。艦砲の射撃も航空勢力の支援もない中で。未明の銃剣による白兵突撃を試みる支隊に自動小銃、迫撃砲、戦車まで登場しての集中砲火が浴びせられる。明るくなると、攻撃目標の滑走路から飛び立った敵機の機銃掃射も加わり、撃退、壊滅される。一木大佐は自決した。
気迫の突撃で活路を開く、これではまるで戦国時代だ。いや日露戦争の旅順二〇三高地攻めでも同じ愚が行われたが、最終的に勝利したことで過ちは教訓化されないまま旧陸軍の伝統となってしまった。
ガダルカナルでも一木支隊の悲劇は修正されずに繰り返される。九月、5,600の兵(支隊長・川口清健=かわぐち・きよたけ=少将)が増派されて第一回総攻撃が試みられる。前回作戦から修正されたのは、海岸線からの攻撃が失敗したので、迂回してジャングルからの奇襲に切り替えたことだけだった。夜陰に乗じて突撃が繰り返された。野砲、山砲、速射砲なども送り込んだが、ジャングルを切り開いての進軍で、砲は後方に置き去りにされる。結果は同じだ。しかも飛行場の完成で、周辺の制空権は完全に奪われて、米軍も6,000人が補強されている。当然に攻撃は失敗し、1,500人が犠牲となった。
メンツにかけても島を奪還したい大本営は、10月にもさらに規模を拡大して第二次総攻撃を準備する。兵力は2個師団2万5,000人、火砲176門、糧食30日分で、正面作戦を行う計画だった。しかし、食糧と資材の揚陸作業中に艦載機の爆撃を受け、食糧と火砲の大半を失う。作戦は、前回同様のジャングル迂回の夜襲作戦に切り替えられ、またもや日本軍は撃退され、生き残った兵も飢餓線上をさまようことになる。
硬直化した軍(組織)は生き残れない
ガダルカナル作戦の失敗は、太平洋戦争における陸戦面での大きな岐路となった。ガダルカナルでは、日本軍が島の奪還に成功するチャンスはあった。一木支隊が上陸した時点で、米軍はまだ島を死守する体制はできていなかった。島周辺を遊弋する日本の連合艦隊、航空勢力におびえていた。
このとき、戦力を小出しにせず、一気に2個師団を投入し、火砲、艦砲、航空支援を最大限に活用すれば、形勢はどうなったかわからない。しかし、それができず、情勢の深刻化に合わせて戦力を逐次投入することで、傷口を深くし、作戦は失敗した。
ビジネスにおいても同じだ。チャンスと見たときには、持てる資源を出し惜しみせず投入すべきなのだ。出し惜しみしても最終的に投入される資源は同じである。そして失敗する確率が高い。この原則は防衛的局面でも同じだ。
そのためには、情勢を正しく判断できるだけの情報と統合的な戦力運用が必要である。「今ここでこそ」の判断が求められる。島伝いに東京に近づき、一気に本土爆撃し、最終的に本土上陸で日本を降伏に追い込むプランを描いていた米軍は、陸軍、海軍が統合的に動いた。しかも島伝い作戦の専用部隊としての海兵隊を、陸海軍から独立させ装備を充実させつつあったのだ。
日本軍は決して物量差だけで負けたのではない。戦いの終着点も思い描けず、白兵突撃という伝統的戦術から抜け出せない硬直化した日本軍は、生き残れない運命にあった。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『日本の歴史 25 太平洋戦争』林茂著 中公文庫
『失敗の本質 日本軍の組織論的研究』戸部良一ら共著 中公文庫