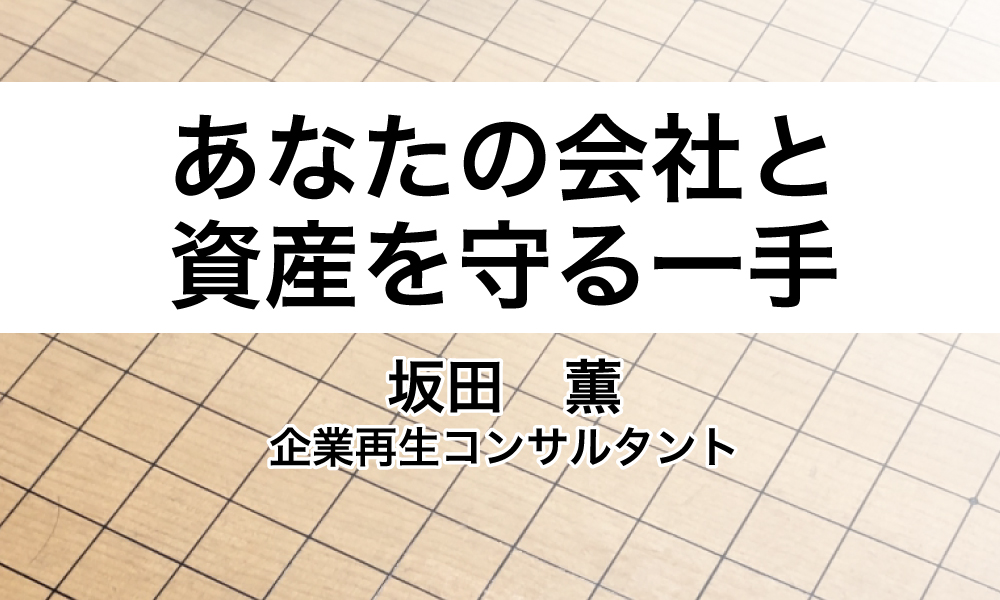物価の安定とデフレの進行
大蔵卿・松方正義(まつかた・まさよし)による中央銀行としての日本銀行の創設(明治15年、1882年)と強引なまでの不換紙幣の回収整理は日本の近代的財政の出発点となったのは間違いない。一時、銀貨と紙幣の交換比率が1.7対1にまで紙幣価値が落ち込みインフレ経済となっていたのが、日銀発足の4年後には、ほぼ1対1にまで持ち直した。紙幣価値の裏付けとなる正貨としての銀の流通紙幣に対する保有率も8 .3%から37%まで増大したことが裏付けとなった。今でいうなら、ドルの保有高が国家通貨の信用度を占う指標となっているのと同様だ。
財政の安定は、殖産興業と軍備増強を進める資本移動の活性化をもたらした。インフレは抑え込まれたが、紙幣流通を抑え込んだ過度の緊縮財政は、デフレ状況をもたらし、農民の糧である米と生糸の価格は暴落し、国民の8割近くを占めていた農民は路頭に迷うことになる。
貧富の差の拡大と社会不安
食い詰めた農民は、農地を手放して労働者として都市に流入する。農地は借金のかたとして、富農のもとに集約され、農村に留まる農民の多くが小作農に転落してゆき、貧富の差が拡大してゆく。作家の太宰治が、青森津軽地方の富農で農民に金を貸していた実家について、「一日歩いても実家の農地から出ることができなかった」と書いた状況が全国に広がった。江戸時代に繰り返されてきた構図だ。貧富の差が、自由民権運動が各地で盛り上がる背景となり、社会不安は広がってゆく。デフレの世の中が、貧富の格差を生むことは、今の世に暮らすわれわれも経験している。
松方財政は、維新後、国家の投資で創設した官営工場、鉱山、炭鉱の民間への払い下げを推進する。それが財閥を生む力となっていく。日本銀行は、「銀行の銀行」として手形の割引で資金を財閥に供給する機能を強化して、資本主義発展の原動力になるが、払い下げの利権をめぐり、財閥の政商化も促進させた。
日本銀行の独立性
明治初期に産声を上げた日本銀行は、渋沢栄一らが主導した日本の資本主義定着の礎を築いたことは肯定的に評価できる。明治国家が模範としたベルギー中央銀行と同じく、国家の金融政策を主導する独立法人として設立されたが、政府の監督権限が強く、事実上、大蔵省(政府)の一機関として機能した。総裁は天皇が任命する勅任で、役員も最終的には政府の任命が必要とされた。しかし、国家統制色が強いものの、主要金融政策は重役会議で議決されるなど、曲がりなりにも独立性を担保していた。
しかし、第二次世界大戦が始まると、昭和17年(1942年)に日銀法が制定されて、その第二条で、「日本銀行ハ専(もっぱ)ラ国家目的ノ達成ヲ目的トス」と定められ、戦争遂行のための金融政策機関と位置付けられ独立性を失うことになる。
現代の資本主義社会では、中央銀行政策の独立性は不可侵とされている。しかし、資本主義社会の盟主である米国では、トランプ大統領が、中央銀行機能を持つFRB(連邦準備制度理事会)の人事に露骨に介入し、利下げ圧力をかけ続ける事態も起きている。
次回は、戦後の日本銀行の政策の流れを見ながら、中央銀行の独立性の問題にてついて考えてみたい。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『日本の歴史21 近代国家の出発』色川大吉著 中公文庫