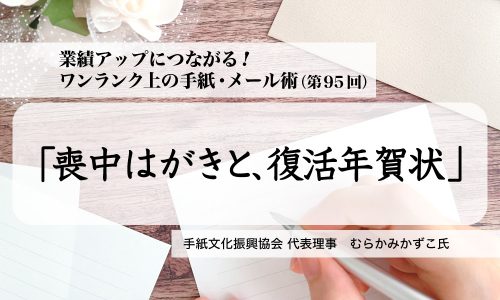- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 逆転の発想(37) 敗軍の将には智慧がある(韓信)
劉邦、有頂天での敗戦
人の上に立つ者はだれしも部下の意見に耳を傾けることは得意ではない。ましてや何をやってもうまく当たって得意の絶頂にある時はなおさらである。引きこもった都から東へ打って出てから連戦連勝で宿敵・項羽との戦いの劣勢を逆転し始めた劉邦(りゅうほう=漢の高祖)がそうであった。
出撃時に数万だった手勢は、撃ち下した周辺の国の軍勢を合わせて、50万人以上に膨らんでいた。勢いに任せて項羽の拠点の彭城(ほうじょう)を占領してさらに自信を深める。「天下統一は近いな」と有頂天である。
ただ一人、作戦を任されていた武将の韓信だけは事態を憂えていた。
「陣内は勝利によって驕りが蔓延し、士気は鈍い。ましてや寄せ集めの軍では危ういな」。現場指揮官だからこその体感だ。
しかも彭城を降したのは、項羽が陣を離れて戦いに出た留守のこと。「項羽は復讐の意気に燃えて引き返してくるでしょう」と韓信は劉邦に進言したが聞き入れられない。「蹴散らしてくれるわ」。勝ち続けているのは名将韓信の巧みな戦術によるものなのに、劉邦は自らの威光がもたらしたものと勘違いしたのだ。
はたして、怒りに燃え引き返してきた項羽軍はあっという間に劉邦軍を打ち破った。それを見ると新参の他国軍は項羽に寝返り、劉邦たちは散り散りとなり西に落ちのびた。
韓信、敵将に戦略を聞く
劉邦は、敗軍を率いた韓信を呼び詫びた。「忠告も聞かず申し訳なかった、ゆるしてくれ」。項羽の祖国の楚への進撃は中断され、「残る軍を預けるから隣りの趙を攻めてくれ」と韓信に託した。ようやく「軍も政治もつかさつかさに任せる」劉邦の流儀に戻る。このあたり、敗戦の責任を部下に負わせて詰め腹を切らせる並みの王とは劉邦は違った。
とはいえ、趙には諸国に聞こえた名軍師の李左車がいる。難敵である。任された韓信は、有名な「背水の陣」を敷いて陽動作戦で趙軍をおびき寄せ、数倍の敵を破った。
さて、ここからが韓信の真骨頂だ。李左車を捜し出して捕らえるように部下に命じる。李左車が打ち首を覚悟して現れた。ところがである。韓信は彼を上座に座らせ、深々と頭を下げて問う。
「この後、北方の諸国を討つ必要がある。どうすればよいか、あなたの意見を聞きたい」
李左車は答える。「急ぐことはない。まずは連戦で疲れているあなたの兵を休ませなさい。慌てて攻めることはない。責めると見せかけて知略で各国を従わせればいい」。李左車が授けたのは〈戦わずして勝つ〉という究極の兵法である。
そして付け加えた。「どうか趙の国民をいたわっていただきたい」。
忠告を受け入れ、兵は十分に英気を養った。そして敵国民を丁重に扱うことで人々は劉邦を慕い、反逆の恐れは消える。劉邦の漢軍は一兵も失うこともなく、周囲を平定した。
耳の大きさがリーダーの条件
韓信は、「戦術においては並ぶものはいないが、戦略に疎い」と自覚していた。彼の偉いところは、そのことを知り、敵の軍師に素直に戦略的意見を求め、実行したことにある。
ここで、秦末の混乱を収めて長期王朝の漢を開いた劉邦と、敗れた項羽のことである。項羽は軍事から政治まで、何から何まで自分で差配しないと気がすまないワンマンリーダーだった。身内に恨みと敵を抱え命取りとなった。
対する劉邦。捉えどころのないお茶目な大男であるが、「自分には政治も軍事もわからない」と知っていた。他人の意見に耳を傾け、それぞれのエキスパートに差配を任せた。しかし、その劉邦においてさえ得意の絶頂には自らの力量を過信し、聞く耳を持たず危機を招いたというのが、今回の話の教訓である。
有頂天の時にこそ、耳を大きく開け。それができるかどうかでリーダーの力量は決まる。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『世界文学大系15A、B 史記』司馬遷著 小竹文夫、小竹武夫訳 筑摩書房