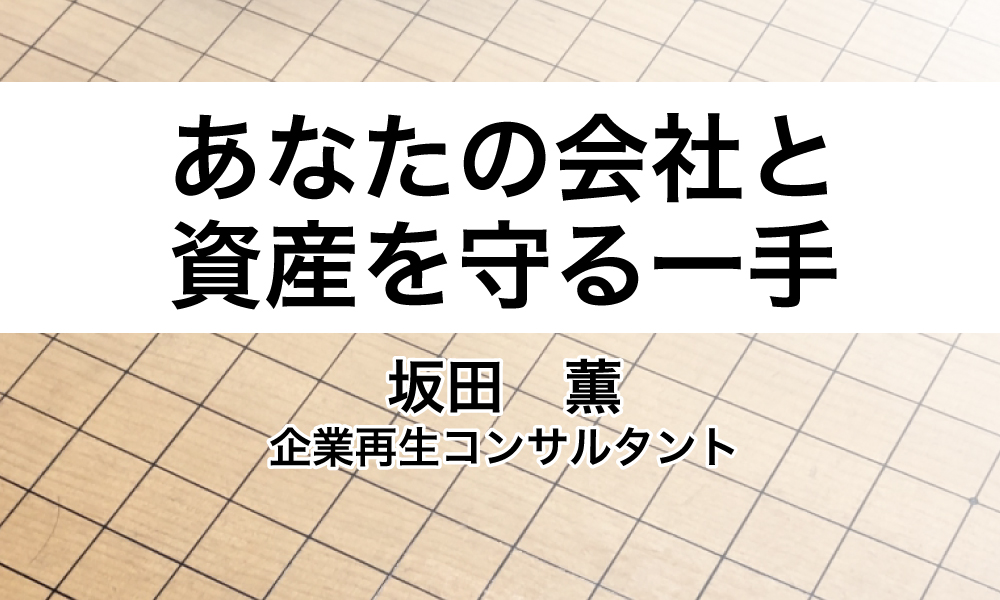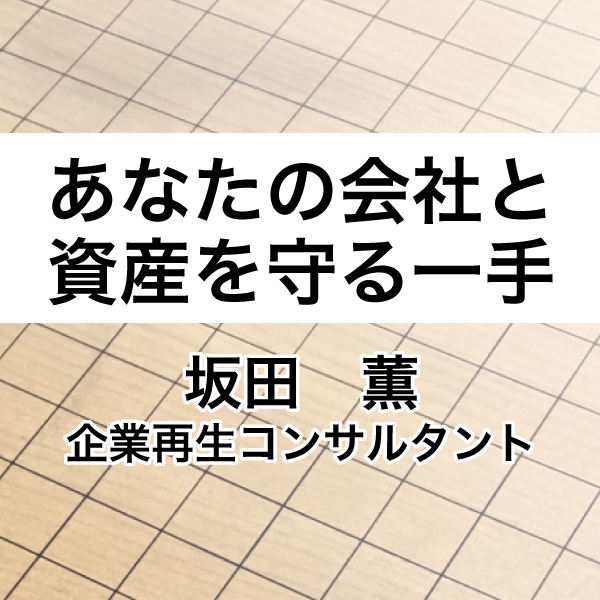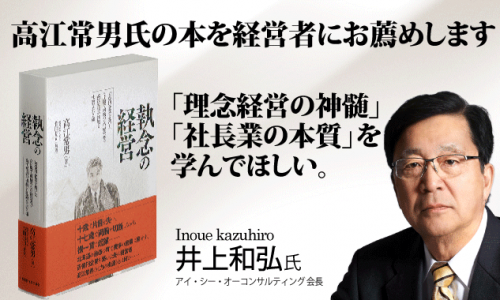折れた火かき棒
「経営の神様」と呼ばれた松下幸之助は、製造場面でも会計、人事場面でも部下の過ちについては容赦なく叱りつけた。それでいて叱られただれもが、叱責されたことを誇りに感じて振り返る。烈火の如き舌鋒に見舞われながら心は幸之助の虜になっていく。叱り方に極意があったようだ。
松下電器(現・パナソニック)で幸之助に長く仕え、三洋電機の創立に参加し副社長まで務めた後藤清一は、ある冬の日に幸之助に呼び出された。独断で工場従業員の給与の歩合を上げたことが発覚したのだ。幸之助は鬼の形相で、「君はいつからそんなに偉くなったんや」と叱りつけた。石炭ストーブの火かき棒でストーブをガンガン叩きながらの叱責は深夜に及ぶ。ストーブの熱と幸之助の怒りの熱に後藤は気を失いそうになった。
「わかったか」。ようやく追及が終わり肩を落として退出しようとする後藤に幸之助は曲がってしまった火かき棒を渡して言った。「君があまりに俺を怒らせるから、こうなってしもたやないか。自分で直していけ」。すっかり叩きのめされた後藤は、曲がった鉄の棒を叩いて直す。反省の時間を与えたのだ。「二度とこういうことをするな」と、口で畳みかけられるより、叱責の意味とそれへの反省が骨身に染みたことだろう。
直った棒を受け取った経営の神様はこう言うのである。「なかなか上手やなあ、真っ直ぐになったなあ」。これで叱られた部下は心をわしづかみにされる。
このエピソードにはさらに続きがある。秘書課長に後藤を車で家まで送らせて、迎えに出た奥さんに伝言を伝えさせた。
「ちょっときつく叱りすぎた。心配なので今夜はご主人から目を離さないでください」。なんとも心憎い配慮ではないか。失策は許さない。心から叱り、フォローする。決して叱りっぱなしにはしない心配りだ。
自尊心を傷つけない
叱り方の極意について幸之助は生前、本気で叱る必要性を強調していた。「本気で叱らんと部下に失礼やろ」。そして相手の自尊心を傷つけないこと。言葉はきつくても、相手のために叱っていることを相手に伝えなければ、叱責の意図は空回りし、感情的な反発だけが残ってしまう。
リーダーならば部下の失策、失敗は許せない。しかし人にはだれでも自尊心がある。怒りのあまり、「もういいよ、君には二度と頼まないから」と言ってしまっては万事休すだ。組織のために働こうという意欲も萎えてしまう。大事な仕事を「二度と頼まない」ような部下をなぜ雇っていたのか、彼をより良い「仕事師」に教育する意思はないのか。捨てぜりふはブーメランとして戻り、上司としての自らの資質をおとしめることになるだけだ。
松下幸之助は、人を叱るときには、必ず自室、自宅に呼んで個人的に叱ったという。満座の前で叱ることはしなかった。本気で叱るのだから言葉はきつくなる。同僚、あるいは部下の前で叱れば、本人の自尊心がずたずたになるのは火を見るより明らかだ。同様に酒席で感情に任せて叱ることもなかった。叱りの場の原則だ。
一度めの過ちは経験
また、人にはだれでも〈自己認知欲求〉がある。他人に自己の能力を認められたいという本能的欲求である。これを満たすためにも幸之助は気を配った。叱った後には、こう付け加えたという。
「このことについては、本当に反省してるならもうええわ。君ならきっとやってくれると思うてたんや。今でもそう思うてるよ」。そしてポンと肩を叩いて別れる。「自分は認められている。期待されている」。これでやる気にならない部下はいない。心憎いばかりの叱りの演出だ。
単なる演出ばかりではない。多くの場合、叱ったあと幸之助は、即座に当の部下にこう言った。「実は新しい企画を考えている。君に手伝ってもらいたいんや」。落ち込んでいる相手に再チャレンジの機会を与える。新企画は失敗をそそぐチャンスとなる。
幸之助はこんな名言を残している。
「一度めの過ちは高くつく経験や、同じ過ちを繰り返したら、それは失敗というんや。二度と犯したらあかんで」
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『松下幸之助に学ぶ部下がついてくる叱り方』江口克彦著 方丈社