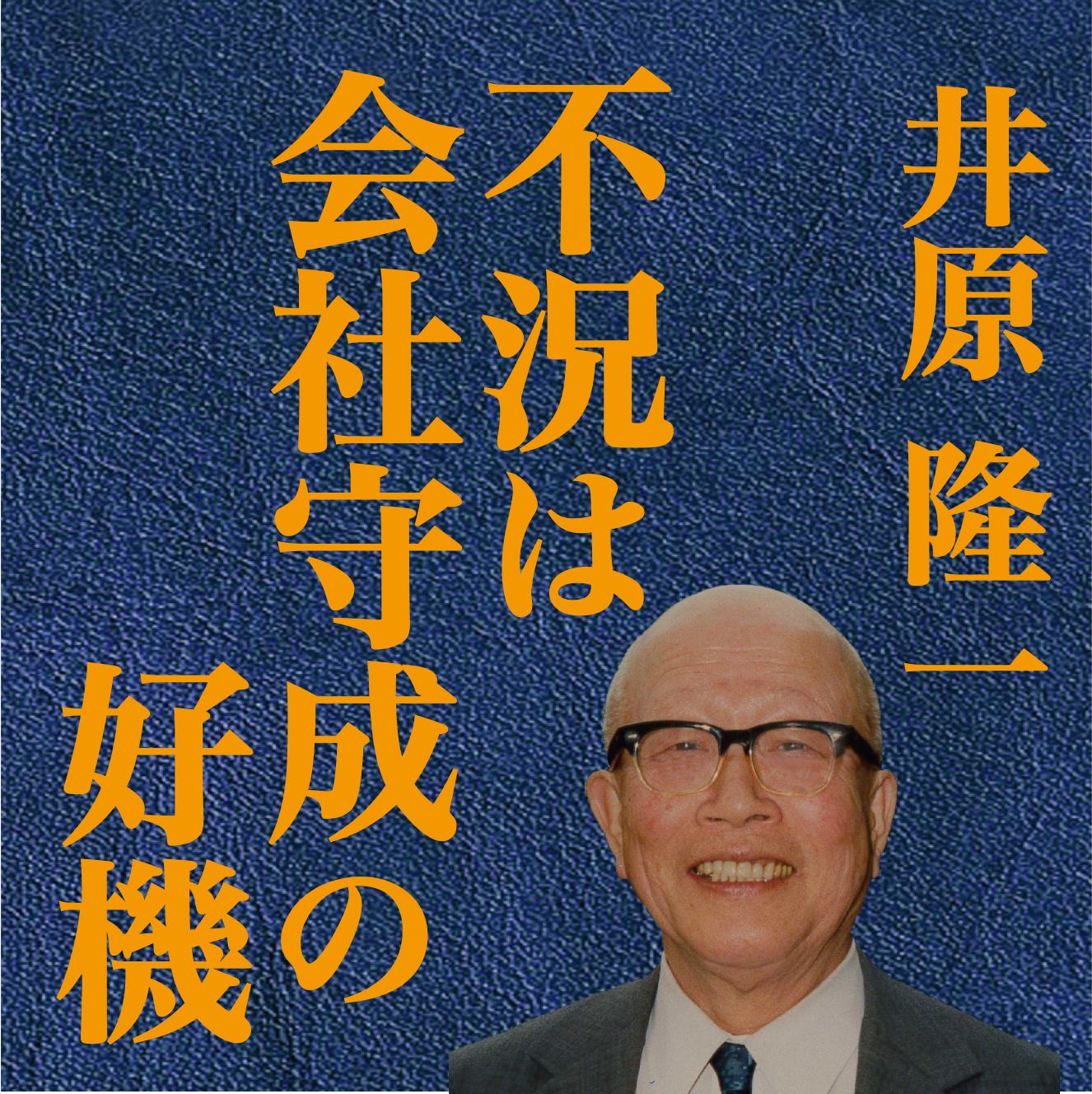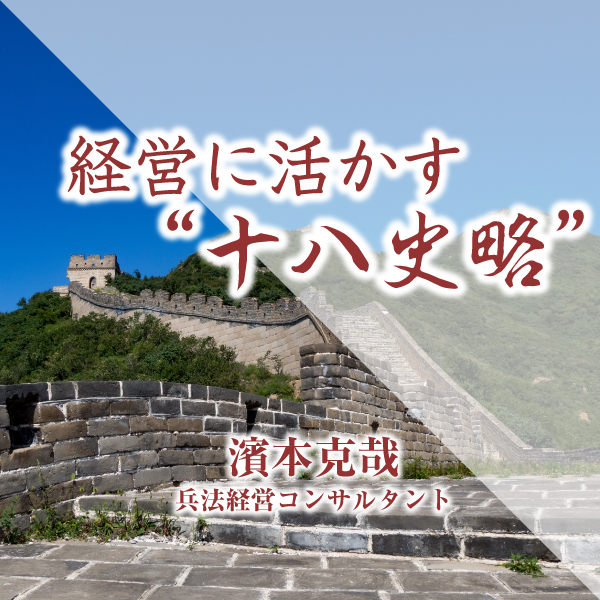会見で垣間見えた影の支配
タレント中居正広の女性スキャンダルの収拾策をめぐるフジテレビのやり直し会見(1月27日)は、なぜ10時間にも及んだのか。理由は明らかである。その場に、対応の決定権者が不在だったからだ。フジテレビと持ち株会社であるフジ・メディア・ホールディングスの会長、社長ら登壇者による記者たちへの答弁は苦渋に満ちていた。〈これを答えていいのだろうか〉〈上のご機嫌を損ねないだろうか〉。一視聴者としてみても、会見を支配する、見えない影への慮(おもんばか)り、配慮が透けて見えた。
会見では、「なぜこの場に日枝氏がいないのか」との厳しい質問が相次いだ。フジ・メディア・ホールディングス、フジテレビの取締役で相談役の日枝久(ひえだ・ひさし)氏(87)のことだ。フジテレビ労組も会見に先立ち、日枝氏の会見出席を求めている。
「日枝氏欠席」について問われたフジテレビ幹部は、「彼は現場にはタッチしていないので」と答えた。もちろん中居トラブルと、問題覚知後も同局が中居氏を番組に起用し続けた責任が取締役・相談役の立場でしかない日枝氏に直接あるわけではない。だが、フジサンケイグループ代表として絶対的権限を持つ日枝氏の口からしか今後の経営刷新方針は聞けない。日枝氏がグループの総帥として人事権を振るい最高権力の座にあることは周知の事実なのだ。
成功体験依存が招く時代とのずれ
「日枝氏が責任をとって取締役を辞任することはないのか」と問われ、同社幹部は、「日枝氏には経験と識見があるので…」と言葉を濁した。確かに日枝氏は編成局長時代から、「面白くなければテレビじゃない」路線を掲げて、視聴率競争でフジ黄金時代をリードしてきた立役者だ。同テレビは、1982年から1993年まで視聴率三冠王を他局に譲らなかった。
1988年6月に生え抜き初のフジテレビ代表取締役社長に就任して以来、同会長、持ち株会社設立後は同会長として辣腕を震ってきたのは周知の事実である。現在の幹部たちは、黄金時代から日枝に抜擢された部下たちで固め、誰も日枝方針にはノーと言えない。イエスマンばかりとなった。
しかし時代は大きく動いている。視聴率は、1993年にトップの座を日本テレビに奪われて以来、低迷している。
メディアの多様化で、テレビ事業は各局ともに苦しい時代に突入した。CM収入は落ち込み続けている。フジの場合、番組制作費は、2006年度に1153億円だったのが、2023年度には682億円まで急激に落ち込んでいる。それは番組コンテンツの質の低下に繋がり、視聴率の下落を招く。視聴率が下がれば、当然CM収入に響く。この負のスパイラルは他局に比べて著しいとされる。
中居スキャンダル発覚後のCMキャンセルによる収入減ばかりではない。コンテンツのサブスクリプション展開など新規事業の展開強化に向かう大胆な経営刷新が求められている。だが、オーナー企業でもあるまいし、80歳代後半までトップの座に居続け、イエスマンで固めた体制で時代についていくのは容易ではない。
院政支配がもたらす無責任経営
事態を踏まえて、フジ・メディア・ホールディングス株の7パーセントを保有する大株主の米国の投資会社ダルトン・インベストメンツは2月3日付の書簡で、日枝氏の辞任を求めている。
今まさにフジテレビが直面しているのは、院政支配の弊害である。裏返して言うなら、院政支配ほど権力者の地位を保全するシステムはない。院政とは、朝廷が政治支配力を保持していた平安末期の政治体制をいう。失政に対して天皇は責任を負うが、退位後の上皇、法皇に権力の中枢を移せば、責任を取らずにすむ。天皇、あるいは側近を切り捨てることで権力は維持される。
徳川時代ならば、将軍の地位自体が院政的実態を帯びた。将軍の意思は、側用人、老中を通じて伝えられ、将軍は失政の責任を負わず安泰な地位を守る。側近に責任を取らせ、首をすげかえればいいのである。
しかし、現代の企業経営において、責任を取らない最高権力者があってはならない。
報道によれば、日枝氏は、「お辞めになる考えはおありか」と聞いた幹部に対して、「お前が辞めればいい」と言ったという。
〈お前たちにはまだ経営は任せられない〉と、成功体験のある経営者は考える。そして時代の変化についていけなくなる。それを老害という。後進には任せられないと考えるのは、自ら次世代の経営者を育ててこなかったことの報いだと気づくべきなのだ。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com