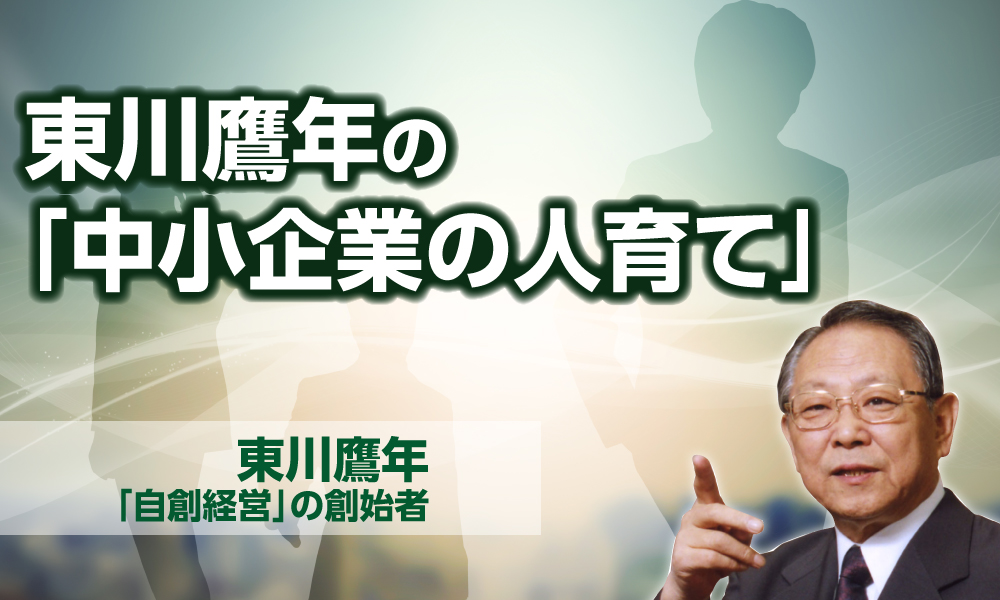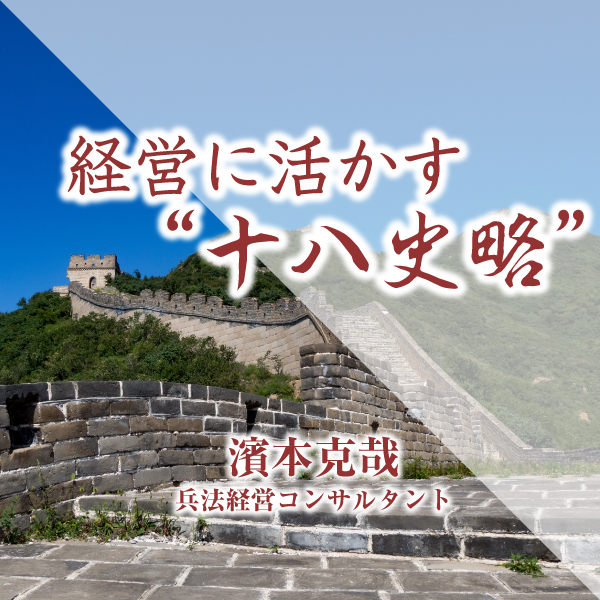エリート官僚の自負
「財務省亡国論」が喧しい。財政規律一辺倒で増税論に立ち、減税に抵抗する霞ヶ関を支配するエリート官僚に対する国民の不満も鬱積し、財務省周辺では「財務省は国民の敵」と抗議デモも起きるほどである。物価高騰の責任は財務省だけにあるではないだろうが。東大法学部出身者が主流を占め国を動かす霞ヶ関のトップエリートたちの自負心の象徴を垣間見たことがある。
1990年代前半、社会部記者として運輸省(現国土交通省)を担当していたある年末、政府予算案の説明会見を取材した。財務省の前身である大蔵省内の会見室で課長クラスの主計官が背丈ほどもある会見壇に上る。そこから記者たちを見下ろして、「運輸省に係る予算案の内容はお配りした資料の通りです」と尊大に言い放った。他省庁の会見室にはこれほどの高さの会見壇はない。エリートの証なのか、これほどの高みから記者を見下ろしているのは、大蔵省だけだ。
1869年(明治2年)に設けられて以来、予算編成にあたる大蔵省は、霞ヶ関のトップとして君臨してきた。政治家のように選挙の洗礼を受けない官僚たちは、「大臣だって2−3年の命。責任を持って国の運営を担っているのは自分たちだ」という自負がある。とりわけ大蔵官僚は、各省庁が上げてくる予算の概算要求を査定する権限が力の源泉となり、とりわけエリート意識が強い。
田中角栄蔵相就任
1962年(昭和37年)7月の池田勇人内閣の改造人事で、その大蔵省に、異例の人物が大臣として乗り込んできた。44歳だった若き田中角栄だ。大蔵官僚たちは緊張した。小学校卒の人物の学歴エリートに対する出方だけではなった。大臣就任直前まで与党・自民党の政務調査会長として重点政策の予算の上積み、米価の引き上げを大蔵省に求め続けた。財政支出を抑えたい大蔵省にとっては扱いに困る宿敵だった。
固唾を飲んで就任あいさつを待つ大蔵幹部たちを見渡して田中のダミ声が響いた。
「私が田中角栄だ。小学校高等科卒業である。諸君は日本中の秀才代表であり、財政金融の専門家ぞろいだ。私は素人だが、トゲの多い門松をたくさんくぐってきて、いささか仕事のコツを知っている。一緒に仕事をするには、互いによく知り合うことが大切だ。われと思わんものは誰でも遠慮なく大臣室に来てほしい。何でも言ってくれ。上司の許可を得る必要はない。できることはやる。できないことはやらない。すべての責任は、この田中角栄が負う。以上」
政治家が官僚を動かすには
新任地で部下を掌握するに、簡潔にして要領を得た名演説だ。田中とて議員立法を繰り返してきた政策通である。その男がへり下りエリート官僚たちの自尊心をくすぐる。「上司の許可を得る必要がない」と宣言することで、意見具申の風通しをよくすると同時に、省内のシンパを一本釣りしてゆく。
極めつけは、「すべての責任は私が負う」と言い切ったことにある。どんな組織、企業にもエリート官僚たちはいる。官僚組織では出世、人事の評価は減点主義で行われる。優秀な能力を持ちながら失敗を嫌い大胆な発想は避ける。「責任は私がとる」とトップが請けあえば、組織は活性化するものだ。
「トゲの多い門松(人生)」を潜り抜けてきた田中は、官僚組織の動かし方を心得ていた。
田中の蔵相就任は、政治と官僚組織の位相を動かす契機となった。その田中を最強エリート官僚組織の長に大抜擢したのは、大蔵主税局長から大蔵事務次官を経て政界に転身し、首相に上りつめた池田勇人だった。(この項、次回に続く)
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『財務省と政治 「最強官庁」の虚像と実像』清水真人著 中公新書
『財務省亡国論』高橋洋一著 あさ出版