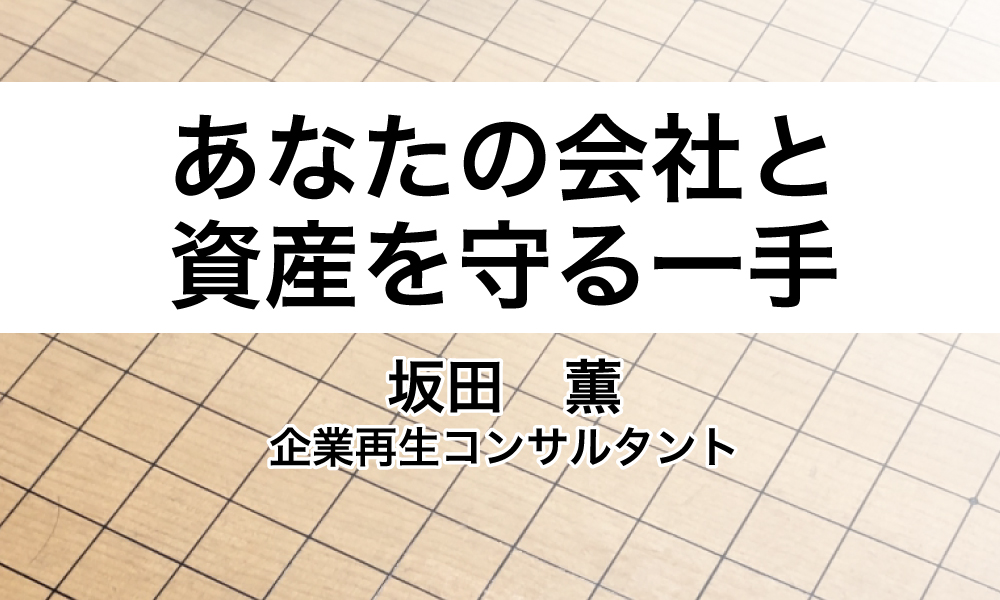もとよりお世辞にも「字が巧い」とは言えないが、おかしなもので横書きだと更に「悪筆」とも言うべき字になる。しかし、今の世の中ほとんど「横書き」で、困り果てている。自治体や公共施設、病院などでの記入はもちろんのこと、買い物に出かけ、物を送る、あるいは何かの会員申込など、割合いを調べたわけではないが、ほぼ100%近い書類が「横書き仕様」になっている。
どこの誰に言うべきなのか分からないので黙っているが、本来、日本語は「仮名」の続け字、崩し字をはじめとして「縦書き」に適した文字だ。水茎の跡麗しく、とは言えない立場だが「横書き」で続け字を書くことは不可能に近い。一方、アルファベットは言うまでもなく「横書き」に適した文字で、あれを縦書きで、と言ったら嫌がらせだと思われるだろう。
そんな話をしてみたら、どうも60代以上は縦書きが楽、それよりも若い世代は横書きが楽、という傾向があるようだ。統計を取ったわけではないので、漠然とした感覚に過ぎないが、今の20代、30代は私とは逆で、「縦書き」は書きにくいと一様に口にする。これは、一般家庭における素養・教養としての「書道」が衰退を見せ始めた時期と一致するのではないだろうか。今は「筆ペン」のように簡便な物もあり、昔のように硯で墨を擦る作業を省略し、キャップの蓋をはずすだけで手軽に筆字が書ける。しかし、道具がいくら便利になっても、その前提の「筆で字を書く」習慣が廃れてしまったので、横書きが縦書きを凌駕したのだ。
確かに、住居表示や電話番号などの数字は、横書きの方が書きやすい。しかし、問題になるのはその程度で、他の場合は圧倒的に縦書きの方が日本語の表記には向いている。
しかし、「縦書き」を阻む大きな流れがコンピュータだ。手紙を自筆で書く機会さえ少ない昨今、コンピュータないしはワープロであればどんな難しい漢字でも書ける。しかし、こちらもほとんど「横書き」の世界だ。一日の中で多くの時間を費やすことが多いコンピュータは、我々からどんどん「縦書き文化」の美しさを奪ってゆく。とは言え、コンピュータを責めることばかりはできない。便利なのは事実であり、現に、この原稿もパソコンのワープロソフトで作っている。また、設定を変えるだけで、縦書きで文字を打つことも、印刷することも可能だ。しかし、これだと何か「負けっ放し」のようで悔しくてならない。
このまま「横書き世代」に押し切られてしまうのも、と思う一方で、単に古臭いだけだと思われるのも業腹だ。何とか、縦書きの良さを、文字の美しさ以外で若い世代に知らせることはできないものだろうか。
すでに半分は「趣味」の領域だが、年賀状を除き、年間に200通ほどの手紙を書く。はがき、便箋併せての数だが、10年以上前から共にオリジナルの物を使っている。これには、インターネットの発達で手書きの原稿を受け付けてもらえなくなったことへの腹いせもあるのだろう。「オリジナル」を印刷したのは、決して高尚な理由ではない。だんだん「老眼」に蝕まれ、私の眼に快適な幅を持つはがきや便箋を探すのが面倒になったこと、相手先の住所はともかく、自分の住所を書くのも面倒になり、さりとてスタンプでは…という怠惰な発想からだ。更に言えば、書きやすいと思う老舗の便箋や封筒は、非常に単価が高い。
こうしたみみっちい不具合をクリアするために、世間には聞こえのよい「オリジナル」を使っている。
世の中は面白いもので、私が究極の手抜きを求めて作った便箋で手紙を出すと、受け取った相手は驚いてくれる。「オリジナルの便箋や封筒なんですね」と。そのうちの92.6%(中村調べによる)の方々が、その気は全くないのに「私も作ってみようかな」とおっしゃる。
私のような怠け者の物書きとは別の立場にいるビジネス・リーダーが同じ事をした場合の効果は凄いものになるだろう。難しく考える必要はない。内容は、はがきなら太目のペンか万年筆で7,8行もあれば充分だ。何よりも、「印刷ではない、直筆の手紙が、オリジナルの用箋で届いた」事に大きな意味を持つ。それは、受け取り手だけのものだからだ。
女剣劇で一世を風靡した女優の浅香光代(1928~)さん。下町の浅草住まいの気さくな人柄で、一緒に食事をしていても、ファンが話しかけて来る。気軽にサインや記念撮影に応じ、握手もする。凄いのは、マネージャーがそこで話した人たちの住所や名前を控えておき、その日のうちに、浅香さんが巻紙に毛筆で書いた手紙を全員に出すのだ。多い時は一日に20通を超えたそうで、80代後半まで続けていた。もらった人は「あの浅香光代から直筆の巻紙の手紙が来た」ことに驚き、喜び、ファンになり、舞台を観に来る。長らく営業畑にいた友人に酒席でこの話をしたら、こう呟いた。
「それは、営業の基本であり極意だ。でも、80歳を過ぎて続けているのは頭が下がる」と。ちなみに、浅香さんは9歳から舞台に立っており、満足に学校へは行けなかった方である。手抜きばかりを考えていた自分が恥ずかしくなった。