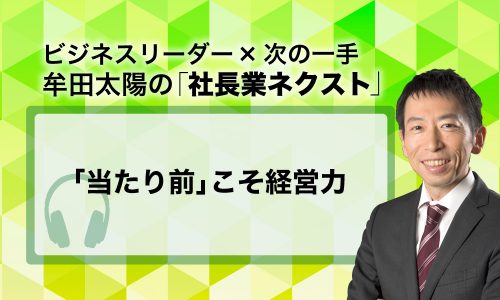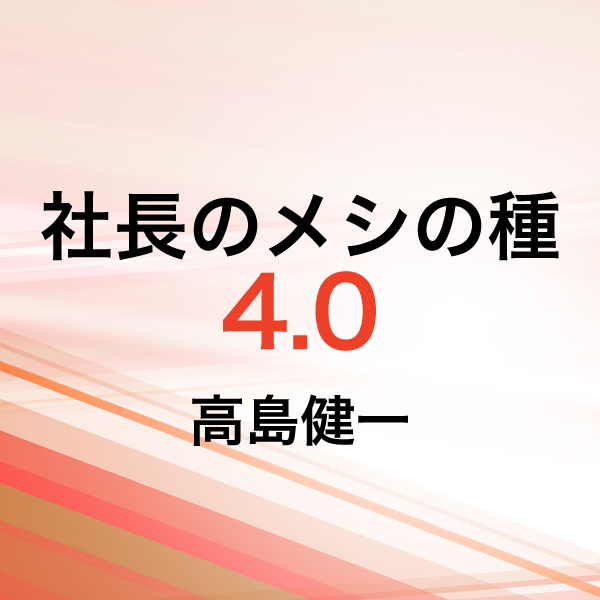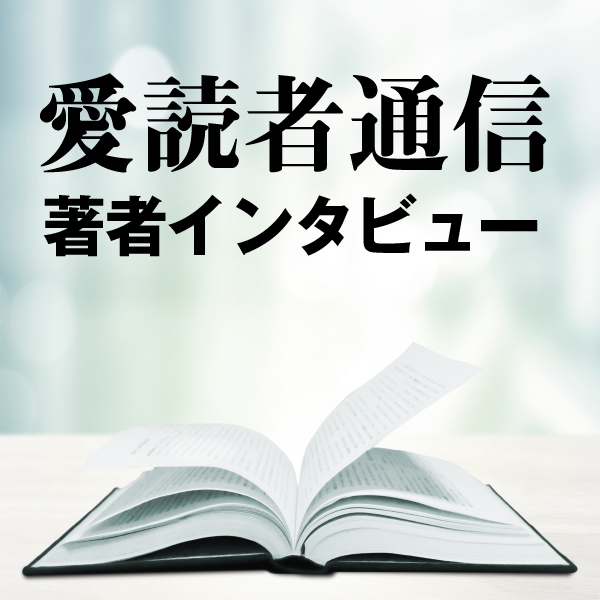時代の変化は薄情なまでに速度を増し、「去る者は日日に疎し」の諺どおり、多くの人々が忘れ去られ、歴史の波に消えてゆく。それは仕方のないことだが、寂しくもある。昭和の大半を占める期間、演劇、映画、テレビ、ラジオなどで活躍を見せ、古典芸能以外の演劇人として初めて文化勲章の栄誉を受けた森繁久彌(1913~2009)の名も、徐々に歴史の彼方に遠ざかっている。96年の長寿を得た一方で、晩年の数年間は表立った活動をしていなかったこともあり、実質的にはもう20年前辺りが最後の健在ぶり、となれば、知らない人が増えるのも無理もない話だ。
森繁久彌の評価は、ミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』を1967年に日本で初演し、以後、20年を掛けて900回を上演したというエピソードと共に語られることが多い。日本中をブームに巻き込み、完全に「ミュージカル」を定着させた功績は確かに大きい。しかし、私は、これだけで森繁久彌という人物を評価するのはいかがなものか、とも思う。
大正2年、現在の大阪・枚方市に生まれた森繁久彌は、大叔父に明治期のジャーナリスト・成島柳北(なるしま・りゅうぼく、1837~1884)を持ち、自らは旧制北野中学(現:大阪府立北野高校)へ進んだ。大正末期の大阪では名門校で、その後、早稲田大学へ進むことになる。大正期のインテリジェンスやモダニズムを持つ家庭で育ったことが後年の幅広い仕事に与えた影響は大きい。
俳優としての仕事だけではなく、ヒット曲『知床旅情』(元歌は『オホーツクの舟唄』)、などの作詞・作曲をはじめ、多くの詩を遺した詩人でもある。ユーモアやウィットに富んだコメントの数々や、「弔辞の名人」と言われた姿は、「言葉のセンス」を示すインテリジェンスに裏打ちされたものだ。
その一方で、喜劇人、コメディアンとしても豊かな才能を見せた。1956年に第一作が公開された「社長シリーズ」は1970年までに33作、1958年からの「駅前シリーズ」は1969年までに24作と、渥美清の『男はつらいよ』に匹敵、あるいは凌駕する喜劇映画のヒット作である。『男はつらいよ』ほどの評価が与えられていない理由の一つに、他の仕事の量が圧倒的に多く、膨大な仕事の中に埋もれていることが挙げられる。
森繁の魅力は、こうした、決して丁寧に創られたとは言えない喜劇で発揮する「うさん臭さ」にある、とは私の勝手な見方だが、そうズレてはいないだろう。もっと細かく言えば「うさん臭く見せる巧さ」、あるいは「自分の失敗をあたかも人がしたように見せる巧さ」だ。後者は舞台で何度か目にしたことがあるが、天下の名優でも台詞を忘れることがある。必死で想い出そうと慌てるのが普通が、そんな時の森繁は泰然自若、その落ち着きぶりに相手役が慌てるケースがあった。時には、自分が台詞を忘れているのに、相手に向かって「どうした?」などと聞く。相手役はたまったものではなく、いきなりの無茶ぶりに慌てふためく。この辺りで観客の気付くところとなり、時に場内は爆笑の渦に包まれ、「台詞を忘れる」という原因を作った森繁が結果的に拍手を浴びることになる。
「狡いやり方だ」との批判もあるだろう。しかし、1,000人、あるいはそれを超える観客を前に、一刻の遅滞も許されない舞台の上で、こんな芸当ができる俳優はそうはいない。見方を変えれば、これは森繁が鍛え上げてきた「胆力」が生み出す技とも言える。私は、森繁の魅力は、「インテリジェンスに裏打ちされた胆力」にあると考えている。紛れもない自信と、芝居の怖さを知る謙虚さが相まって永年の経験で出来上がったものだ。これがあるからこそ、「俳優」だけでは収まり切れない幅の仕事を見せたのだろう。
何度か世田谷の自宅で、あるいは出先のレストランなどで「芸談」とも「人生論」とも言える話を聞いたのは素敵な想い出だ。一番印象に残っているのは、「芝居はな、好きじゃなきゃできないんだよ、でも、好きなだけじゃダメなんだよ」との言葉だ。この「芝居」を自分の職業や趣味に置き換えても充分に通用する話で、結局のところは何をするにも「+α」がなくてはいけない。この「+α」を、流行りの言葉に直せば「人間力」「表現力」「雑談力」など、いろいろあろう。森繁は、感覚的に、人間は多面的な魅力を持たねばならないのだ、持っているのだという「人間愛」を持つ器量の大きさがあった。
我が家のリビングに、不似合いなほど立派な漢詩の額がある。『三国志』で曹操が詠んだ「歩出夏門行」(ほしゅつかもんこう)の一節だ。
「老驥伏櫪 志在千里 烈士暮年 壯心不已」。意訳すれば、「かつて千里を駆けた馬も、今は老いて厩につながれている。しかし、その志は変わることなく千里を駆け巡り、老いたからと言って己の熱い心を留めることはできないものだ」との意味だ。
70代後半に書いたものだが、森繁の雄渾で筆勢豊かな力強い文字で、形見としていただいたものだ。とかく怠けようとしがちな私を励まし、叱咤するように泰然としている。