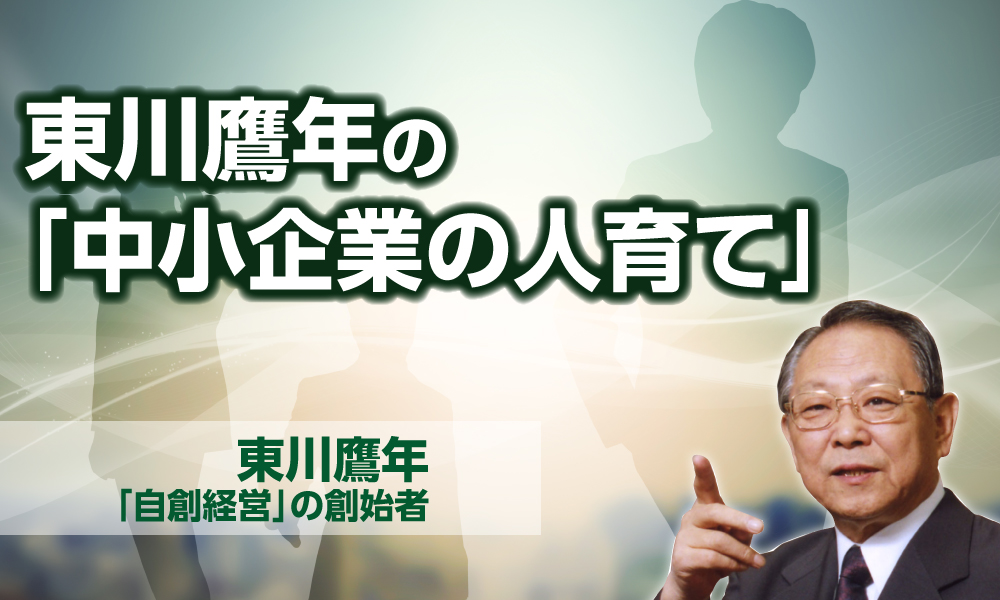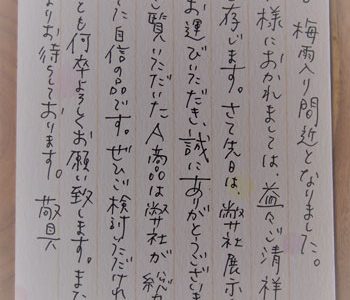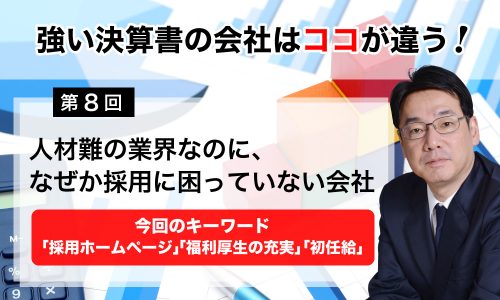「明治維新」という時代の大きなうねりが日本にどれほどの変革をもたらしたかは、改めて説明の必要はないだろう。我々の生活のあらゆる分野にその影響は及び、形を変えて現代に至っている。江戸時代から「近代」へ日本が大きく舵を切り替えた時期だ。
俗に「明治維新」と言われている変革がいつ始まり、いつ終わったのかについては、歴史家の間でも諸説があるようだ。慶應3(1867)年に、それまで260年以上にわたり日本の政治を担ってきた徳川家が天皇にそれを返上した「大政奉還」、あるいは元号が「明治」と改元された1868年10月23日を始まりとするケースが多いようだ。一方、終わりとなると、明治4(1871)年の「廃藩置県」、10(1877)年の「西南戦争の終結」、18(1885)年の「内閣制度の発足」など、政治や憲法の動きに視点を置くケースが多く、確定的な結論は出ていない。
時代が明治と改まり、日本の支配階級であった「武士」は存在しなくなり、「文明開化」の名のもとに、多くの外国の思想や文物が雪崩を打つように日本に入って来たのは周知の事実だ。
江戸時代の身分制度は法律上は廃止され、組織的な軍隊が作られ、憲法が制定され、鉄道が開通し、服装にも洋服が登場し、男性の髪型は「ちょんまげ」から「散切り」と呼ばれるスタイルに変わった。パンや牛乳、ビールなどの洋食も登場し、政府による教育制度が確立され、誰もが教育を受けられるようになった。産業も発展し、明治22(1889)年には「大日本帝国憲法」が公布された。この憲法は、日本が第二次世界大戦に敗戦する昭和20(1945)年まで続くことになる。
当時、「新しく憲法が発布される」との言葉の意味が庶民には伝わらず、「お国から新しい「絹布の法被」(絹の筒袖の簡便な羽織)が配られる」と勘違いした、という笑い話もある。生活のあらゆる面が激変とも言える変化の中、こうした勘違いを笑うことはできない。
「明治維新」が後世の我々にもたらした利便性は計り知れないほど大きく、時代の転換期を担い、のちの名を残す人物たちが私欲を捨てて新しい時代の国家建設のために力を尽くした結果である。しかし、何事もすべて「プラス」の面だけではない。「マイナス」の例を挙げれば、幕末から明治にかけて各地で起きた「廃仏毀釈」と呼ばれる行為だろう。明治政府は、それまで混同されて考えられていた部分が多い「神道」と「仏教」を分離するために「神仏分離令」を出した。それが一般的に拡大解釈され、仏教の排斥運動として全国に広がったのだ。
現在も国宝が多い奈良県では、興福寺の「五重塔」が競売に掛けられた。幸いに買い手が付かなかったが、大阪府の住吉大社の「大伽藍」はほとんどが破壊された。こうした例は枚挙に暇がなく、残されていれば重要文化財や国宝に指定されたであろう貴重な建物や仏像が、僧侶たちが寒さを凌ぐための焚き付けにされた例も少なくはなかったと聞く。
インターネットの例を引くまでもなく、我々は「利便性」を得るたびに「精神性」を喪失しながら生きている。そのすべてを否定することはできない。その一方で、「コロナ禍」という改めて人間の無力さを思い知らされる大きな時代の変わり目に我々は生きている。この時代をどう生き抜き、次の世代にどのような形で受け渡すことができるのか。これは、ひとえに企業や組織を担うリーダーの考え方による。
「明治維新」には当時の新進気鋭の若者のパワーが大きな力を発揮した。これは私見だが、それだけでは、あれほどの変わり目を乗り超えることはできなかっただろう。多くの若いエネルギーの後ろには、それを動かし、爆発させるために必要な、上の世代による経済面、精神面をはじめとした大きなバックアップがあったはずで、この意味は大きい。
時代の変革期の最中の今、これを機に更にエネルギーを蓄え、発想を転換して「プレイング・マネージャー」の立場を貫くリーダーもいれば、第一線を退き、次の世代のブレーンとしての役割に自分の立場を変えるリーダーもいるだろう。他の形態もあるかもしれない。
いずれにせよ、世相が乱れ、混乱期にあってはリーダーの肚の座り方が大事なのは言うまでもないことだ。その人生経験をもとに、広く大きな視野で時代をどこまで読み取り、次の一手を打つことができるか。リーダーの資質を発揮するには、「混乱の中の冷静」が必要だろう。
我々は過去の歴史に多くを学び、生きている。功罪相半ばする面を持つ「明治維新」という大きなうねりに何が起き、何をしてきたのか。あるいは、何をしてこなかったのか。過去の歴史に学び、教訓とすべきことは多い。見逃しがちなのが、「してこなかったこと」だ。それにより、どんなメリットとデメリットがあったのか。詳しくは専門家の検証に譲るが、この考え方は大事だろう。「明治維新」のありようは、多くのリーダーにとって良き参考書となるのではないだろうか。