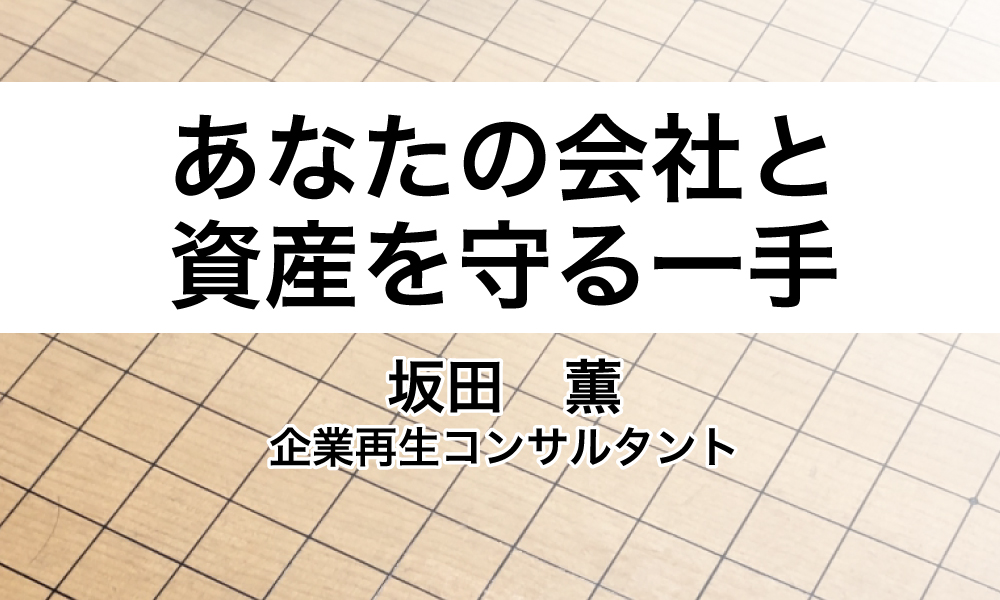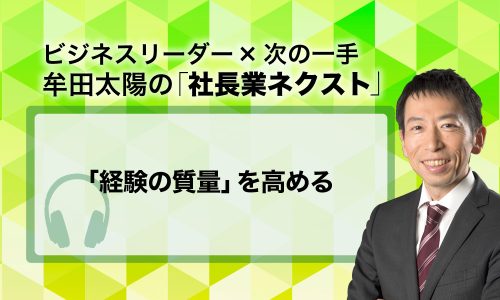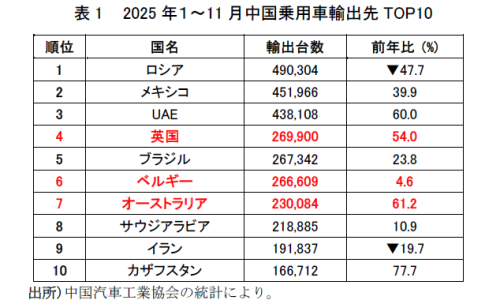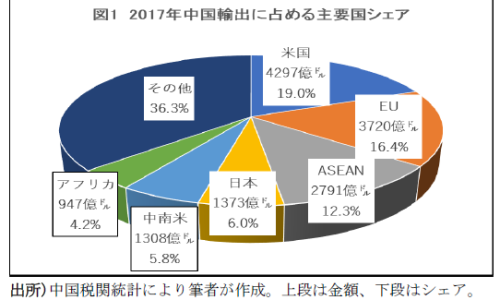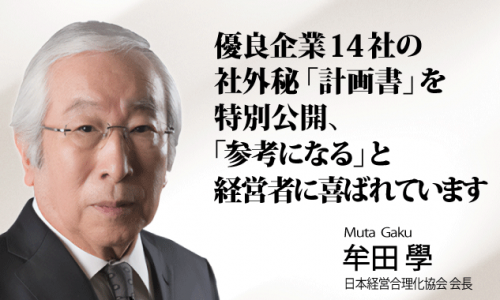決算対策という言葉は経営者ならよく理解していると思う。利益をどうするかという問題だが、その解決策である節税方法の多くはじっさいに手元のキャッシュがなくなるものであって、決算上の利益は減ったが手元のキャッシュも減ってしまったということになりやすい。売上の計上基準を変更したりということがある本に書いてあったが、その判断は微妙すぎて「もしかして税務署には認めてもらえないかもしれない」と思うことも多々生じることとなる。
家賃を1年間一括前払いして、それを資産勘定ではなく損金として落とすということも、それが継続できて、賃貸の契約書もそうなっているのなら可能らしい(注1)が、相手もあることだし、今後数年間の売上・利益・資金繰りの推移などわかるわけがない。今年は1年分一括で支払えても来年はどうかわからない。だいたいにおいてそんなことをしたら資金繰りが悪化する。中小企業経営はそんなふうにできているものなのだ。
決算が終わって支払う税金は法人税、地方特別法人税、法人都民税等だけではなく、消費税もある。ところが、消費税対策と言う言葉はほとんど聞かない。せいぜい本則課税を選んだほうが得か、簡易課税を選んだほうが得かくらいで、これも毎年コロコロと変えることもできない。消費税を軽減する方法として設備投資をするという選択肢もあるが、手元キャッシュで設備投資をおこなえばキャッシュがなくなり、銀行借入れで行えば資金繰りが苦しくなり、設備投資したものの資産価値は急激に下がっていくが、負債の減少ペースはかんばしくなく、多くの会社で財務内容が設備投資前より悪くなる。
では、どうしたらいいのか?
その答えをもっている会社の社長はきわめて少ない。
だいいちその答えがあったとしても、その会社には通用するが他の会社では通用しない。さらにはそういったことは本に書かれたりといった公にされるものでもない。門外秘伝というものなのだ。
もちろんそんな会社の税務を見ている税理士もその門外秘伝を理解していない。だいいち、税理士は国家資格でその資格を手放したくはないから税法の運用指針に沿った税務処理をしたがるし、それが税理士の仕事なのだ。費用対効果の観点からいえば脱税に手を貸す税理士などいない。
仮に、脱税ではないキャッシュの残る節税手法を税理士がみつけたとしても、それにもとづいた税務処理がおこなわれていくうちに公知のものとなり、税務当局がそれに対処して通達を出したり、法令化したりする。
もちろん節税は無駄ではない。しかしそのアプローチの仕方が細かい税務通達にかたよりすぎると、「木を見て森を見ず」の状態に陥る。
要は、キャッシュが残せればいいのだ。
そして、それを実現するためには「利益という数字はどこから生まれるのか?」と「利益と手元キャッシュの関係」を徹底的に追求する必要がある。
破たんした企業を再生させる仕事をしていると、再生がうまくいって利益を出すようになった企業は必ず「利益という数字は、どこから生まれるのか?」と「利益と手元キャッシュの関係」ということを考え抜いて生き残っていることに気づく。
もちろん、その企業のもっている営業力、体質、財務によって答えはいくつもあるが、それを考え抜いた企業はとても強い企業になっている。
注1:国税庁ホームページ より下記引用
通達(短期の前払費用)
2-2-14前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)
(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。