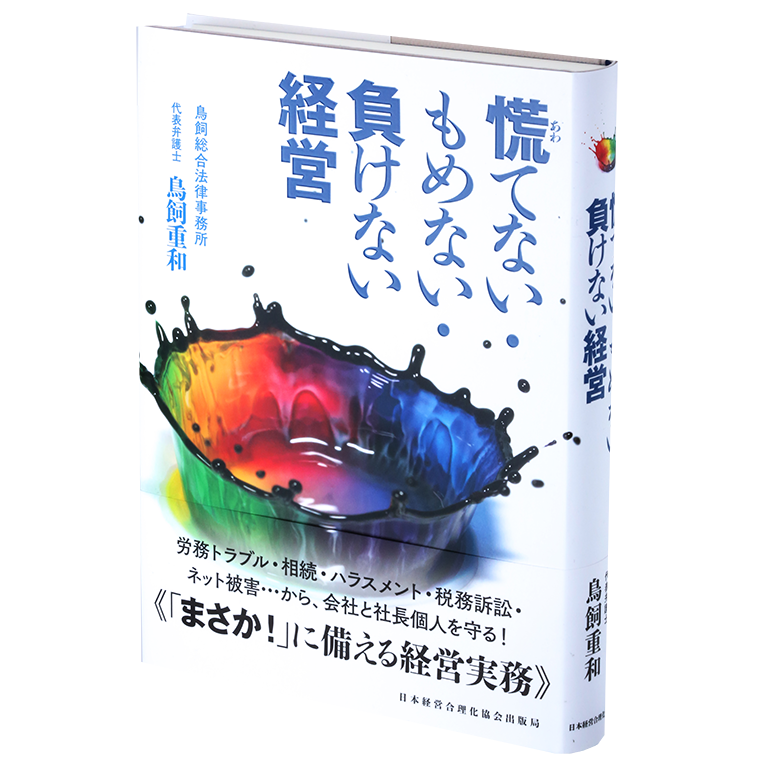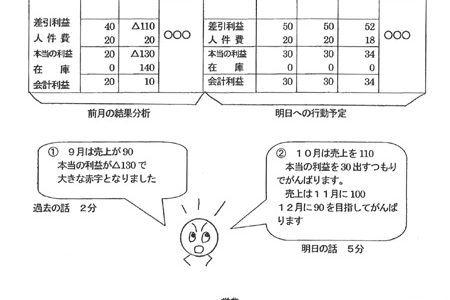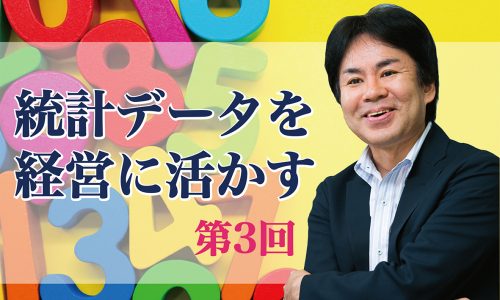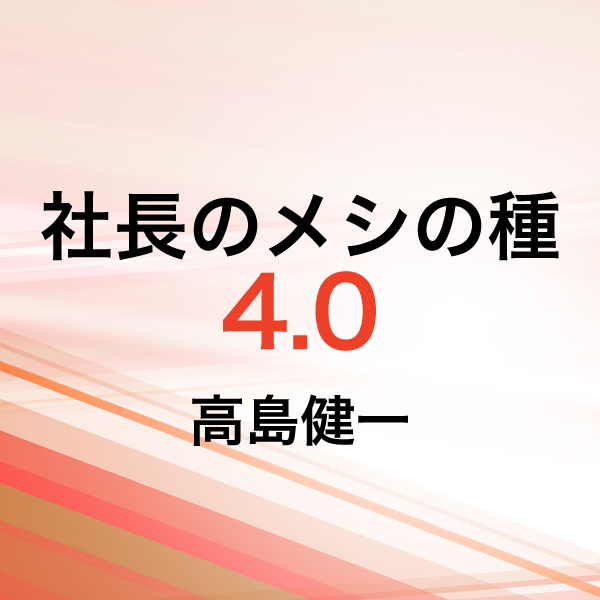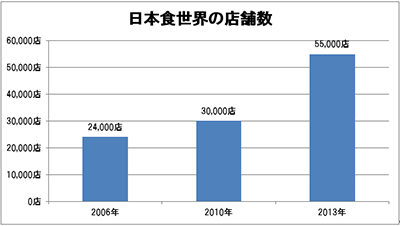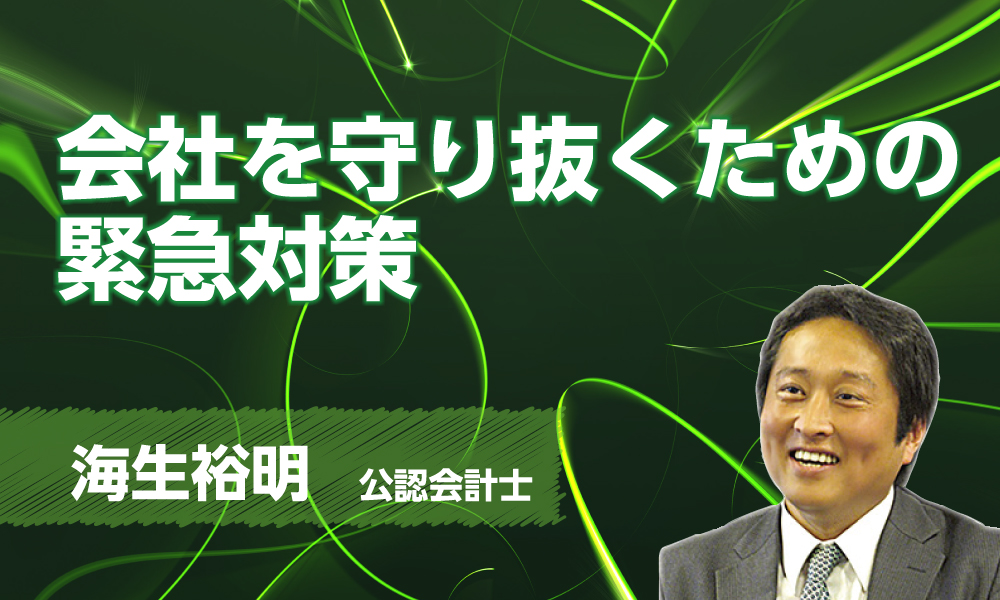103万円の壁が見直される!
とある朝のテレビ番組で「年収103万円の壁」が見直されたことを耳にした佐藤社長。サラリーマンやパートタイマーに影響があることは分かっているものの、具体的にはどのようなことなのか、会社経営にどのような影響があるのかは理解ができておらず・・・
* * *
佐藤社長:昨年の衆議院選挙から「年収103万円の壁」が世間の注目を集め、令和7年度の税制改正で早々に世論が反映されたと聞いています。具体的にはどのようなことですか?
賛多弁護士:いわゆる「年収103万円の壁」の「103万円」とは、所得税の基礎控除額「48万円」と給与所得控除における最低保障額「55万円」の合計額を指していて、昨年までは年収103万円以下であれば所得税が課税されなかったために「年収103万円」が一つの区切り、つまり「壁」と表現されていました。それが、令和7年度の税制改正によって、この「48万円」と「55万円」がそれぞれ「95万円」と「65万円」に引き上げられることとなり、結果として、年収「160万円」以下であれば所得税は課されないことになりました。なお、納税者の8割強にあたる4,600万人が所得税の負担軽減の対象になると、政府は試算しています。
佐藤社長:なるほど、基礎控除がおおよそ2倍になったのですね!私も所得税を納めていますから、その恩恵を受けられるのですね!!
賛多弁護士:実は、基礎控除として「95万円」を控除できるのは、給与収入が200万円相当以下の方のみで、給与収入が多くなるにつれて逓減することとなり、給与収入が2,545万円相当を超える場合には令和6年以前と基礎控除の考え方は変わりません。換言すれば、給与収入が2,545万円相当以下の方の基礎控除が見直されたことになります。
佐藤社長:巷でいう「高所得者優遇」とならないように、工夫がされているのですね。
賛多弁護士:さらに、給与収入200万円相当超850万円相当以下の場合には、令和7年と令和8年に限り「上乗せ特例」があり、令和9年以降は一律「58万円」となります。つまり、令和7年度の税制改正では、基礎控除を「10万円」引き上げつつ、当初2年間だけに「上乗せ特例」を設けることとしました。
佐藤社長:令和7年分の給与はすでに1月から支払っていますが、何か変更すべき点はありますか?
賛多弁護士:基礎控除の改正は、令和7年12月1日の所得税について適用されることとなり、給与所得者については令和7年分の年末調整において適用できることとされていますから、変更することは特にありません。ちなみに、令和8年分以降の所得税については、毎月の源泉徴収の際に考慮することになりますから、覚えておいて下さい。
佐藤社長:給与所得控除の改正で影響のある範囲も教えて下さい。
賛多弁護士:給与等の収入金額が190万円以下の場合については、最低保障額を65万円にすることとしました。この改正は、令和7年分以降の所得税について適用されることとなり、給与所得者については令和7年分の年末調整において適用できることとされています。また、給与所得者の源泉徴収は、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用がされますから、基礎控除の改正と同様に、現段階では給与計算などで変更することはありません。
佐藤社長:所得税のかからない範囲が拡大されたことは理解できました。では、それが会社の経営にどのような影響を及ぼすと考えられるのでしょうか?
賛多弁護士:まず、昨年までは「年収103万円の壁」を意識して「働き控え」をしていたパートやアルバイトの方が多かったと思いますが、基礎控除や給与所得控除の見直しにより税負担が減ることで、働く意欲のある方はより長い時間・より多くの日数働くことができるものと期待できます。
佐藤社長:毎年、クリスマスや年末に人材不足で悩まされていたのですが、それが解消できそうで、経営者にとっては嬉しい限りです。
賛多弁護士:そうですね。ただし、「もっと働きたい」という方が増えると、社会保険に加入させなければならない可能性も増える、ということになります。働く方も会社も、社会保険料の負担が増加しますので、注意が必要です。
佐藤社長:確かに。社会保険に加入することで手取りが減ってしまっては、また「働き控え」が起きてしまいますし、会社にとっては、増加する社会保険料の原資を確保するための対策も必要となります。あと、住民税の負担も考えなければなりませんよね。
賛多弁護士:参考までに、106万円の壁(厚生年金等)、110万円の壁(住民税)、130万円の壁(国民年金等)というものもありますので、あわせてご注意下さい。(※)
(※)自治体によって要件が異なります。
* * *
上述のとおり、基礎控除及び給与所得控除の改正は、令和7年分の所得税については、年末調整で減税の対応をすることとされていますが、当社の従業員のみならず、そのご家族の所得状況まで把握をしたうえで年末調整をする必要があるなど、確認すべき事項が増えるため、事務手続が煩雑になることが予想されます。従いまして、毎年11月ごろから作業を始められる会社が多いと思われる中、少しだけ前倒しでの作業スケジュールを組んで頂き、早めに従業員へ周知する、速やかに書類を集める、多めの確認作業時間を確保する、などとされることをおすすめ致します。
執筆:鳥飼総合法律事務所 税理士 田坂 尚靖