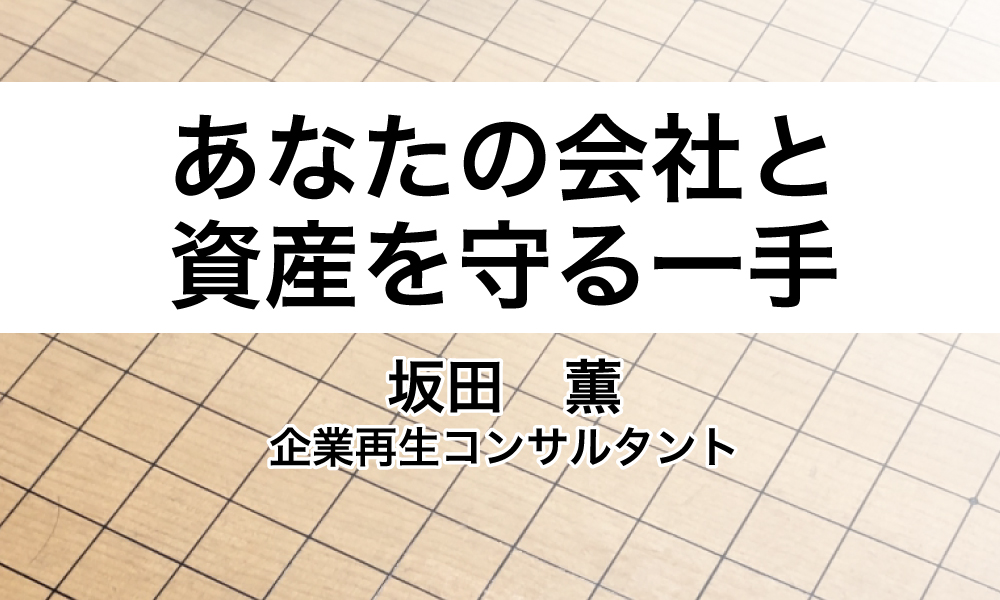毎年、季節ごとの変動が激しくなって久しい。このところ、年に少なくも一度は死者が出るほどの大きな災害があり、夏の暑さは「異常気象」と聞いても「またか…」と思うほどの記録更新を続けている。世界中で温暖化に対する方策が考えられてはいるのが救いだが、「産業革命」以降、長い時間を掛けて地球の温度が上がってきたのだ。現在の我々の取り組みはこれからの地球を担う世代へのお詫びを含めた行為と考え、100年後のためにと腹を括らなくてはいけないのかもしれない。
「何か便利なものを一つ手にすれば代わりに何かを失う」とは近代化が始まって以降の言葉で、それ以前の時代の人々は文明の恩恵で四季を快適に過ごすことは叶わなかった。その分、温暖化も今ほどではなかったのが唯一の救いだろうか。
自分の力ではどうにもならない状況の中、先人たちはそれを受け入れ、少しでも快適に過ごそうとする知恵に長けていたようだ。湿度が高く、だからこそ木と紙を主な素材とした家屋が合ってはいるが、夏が暑いことに変わりはない。軒下に「風鈴」を吊るし、僅かな風のそよぎで鳴る音に「涼しさ」を求める気持ちは精神性の問題だ。温度計がない時代とは言え、風鈴が数回涼し気な音を奏でたところで気温が下がるわけはない。しかし、そこで「涼しい風が吹いてきた」「風が抜けて爽やかになった」気分を味わうことで、暑さを一瞬忘れる行為は、かなり洗練された精神活動だ。今の我々なら「暑い!」と感じればすぐにエアコンのリモコンに手を伸ばす。実質的な効果で言えば、盥に水を張り、「行水」を使うだけでも気分はさっぱりする。我々がシャワーを浴びるのと同じ感覚だ。ボタン一つで風呂が沸くわけではないが、家に浴室がない分掃除の手間もない。
季節が移ろう中で、今でも過ごしにくいのは「冬」だろう。寒いのは当然で、その上に「新型コロナウイルス」のパンデミック以前にも季節性の「インフルエンザ」の流行をはじめ、寒さで血行が悪く免疫力が下がった身体はいろいろな病気に罹りやすくなる。今よりも栄養も満たされず、医学も発達していない江戸期には、ごく普通の風邪でも命とりになるケースは多かった。また、恐らくはインフルエンザに近いものだろうが数年に一度、「コロナウイルス」のような風邪が疫病として多くの人が命を落とした。
気軽に暖房を使用できる環境ではない時代、重ね着とは言え、庶民はボロを重ねるしかなかったが、体温を逃がさない工夫をし、「冷え」が万病の元になることを経験的に知っていた。こうして厳しい寒さを乗り切る中で、新年を迎え、自分たちの手では如何ともしがたい健康や長寿を新しい年の神仏に祈ったのだ。統計の採りようがないが、新年を迎えて気分が変わることで身体の免疫力が高まる「プラセボ効果」のような感覚は相当に高かったはずだ。
厳しい夏や冬の合間に、短い期間ではあるが過ごしやすい「春」と「秋」が挟まれているのが「四季」を持つ日本の有難さだ。厳しい季節を乗り越えた「御褒美」として天が与えてくれたのかもしれない。春には多くの花々が咲き、山は青々とした姿を見せる。麗らかな春の一日、江戸であれば向島辺りへ出掛け、当時は「大川」と呼ばれていた隅田川を飛ぶ鳥を眺めながら、向島の土手に咲く花々を愛で、名物の「長命寺の桜餅」に舌鼓を打つ。一週間程度の「旬」に咲き誇る櫻を眺め、その下で宴会をする光景は現代にも残っている。
秋は、これから冬に向かう寂しさがあるものの、米も野菜も魚も美味しい収穫の時期だ。冬に向けての保存食を貯える時期でもあり、抜けるような空の下で、せっせと気持ちのよい汗を流す日もあれば、少し郊外まで足を延ばして、「紅葉狩」を楽しむこともできる。もっとも、基本的に移動は「徒歩」という時代、行動範囲はそう広くはない。その代わりに、品川にも中野や杉並にも紅葉の名所はあり、日帰りでも充分に季節を楽しむレジャーは可能だった。
こうした日々を過ごしながら年を重ねる中で、江戸時代の人々がそれぞれの季節をどう感じ、どんな言葉を使っていたかが簡単に分かるのが、俳句で使われる「歳時記」だ。四季折々の「季語」を集めたもので、膨大な数にのぼると同時に、意外な言葉や現在の我々が使わない言葉などが収められており、俳句を作らずともパラパラとめくっているだけでも楽しめる。さしずめ、今の季節なら「山笑う」という季語だろうか。山が若葉青葉で覆い尽くされ、その生気を盛んに溢れさせている様子をたった五文字で現わす豊かな表現力には眼を瞠る。食べ物で言えば「初鰹」は今でも生きている。江戸時代初期に活躍した山口素堂の「目には青葉 山ほととぎす 初鰹」の句は、視覚、聴覚、味覚の季節感を現わした句として名を残し、今でも引用されることは多い。
それぞれの季節の感覚を、「暑いなぁ」「寒くて…」だけではなく、他の言葉にすることで、少しは気分が変わるかもしれない。一度、お試しあれ。