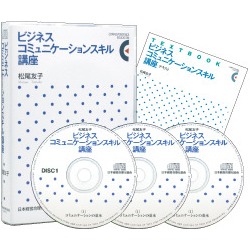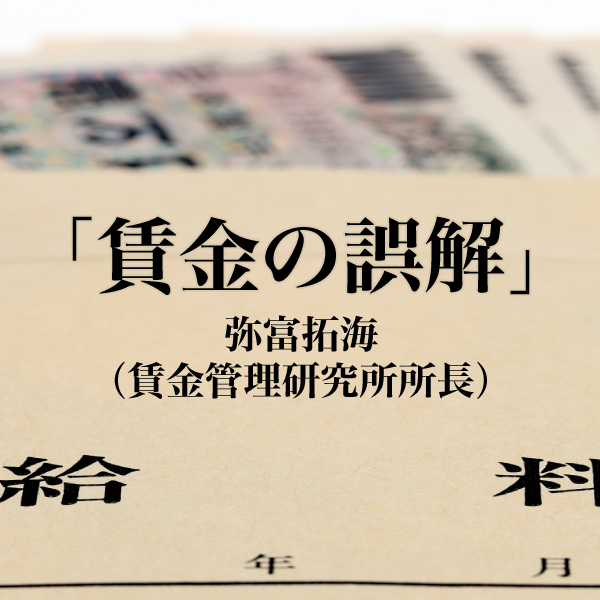■温泉選びで失敗しない裏技
ふらっと初めて訪れた温泉地で立ち寄り入浴をするときは、どの宿を選ぶべきか迷う。事前にインターネットなどで調べていれば、自分の好みを外すことはあまりない。しかし、行き当たりばったりで入った温泉がいまいちだと、その温泉地に対するイメージは最悪である。ひどい場合は、「もう二度とこの温泉には来たくない」と思ってしまうかもしれない。
私は3900以上の温泉を巡る経験を通じて、温泉選びで失敗をしないポイントをいくつか学んだ。そのひとつが、「湯元」「湯本」「元湯」といった名の付く宿や施設を選ぶこと。
このような温泉は、その名のとおり、古くから自家源泉をもっているケースがほとんどである。自家源泉をもつということは、引き湯をする距離が短く、新鮮な湯が湯船に注がれている可能性が高い。また、温泉街でいちばんの老舗であることが多く、代々温泉を守ってきたことから、湯を大事にする意識も強いはず。つまり、温泉自慢の宿が多いのである。
もちろん、「湯元」「湯本」「元湯」といった名前を冠していても、循環ろ過されて、温泉の個性が死んでしまっている温泉もある。だが、この基準で温泉選びをするようになってから、失敗するケースが大幅に減ったのも事実だ。
■鄙びた雰囲気が魅力の温泉街
群馬県と新潟県を結ぶ三国街道沿いに位置する湯宿温泉を初めて訪ねたときも、この基準が功を奏した。
湯宿温泉は、注意していないと見落としてしまいそうな小さな温泉地。開湯は1200年前という古湯である。歓楽街などは一切ない鄙びた温泉街だが、江戸時代の宿場としての面影が今も残り、石畳や昔ながらの家並みが温泉情緒を誘う。つげ義春の漫画『ゲンセンカン主人』の舞台となった温泉としても知られる。
湯宿温泉には、地元の人が利用する共同浴場が健在である。温泉街には数軒の宿と小さな集落があるのみで、温泉街の端から端まで歩いても5分程度。にもかかわらず、「窪湯」「小滝の湯」「竹の湯」「松の湯」という小さな共同浴場が4軒も密集している。現在は地元専用となっているが、共同浴場のある温泉街にハズレはない。
そんな温泉街を初めて訪ねたときにまず立ち寄ったのが、湯治宿の風情を残す「湯本館」だ。鉄筋3階建ての味気ない外観だが、「湯本」という旅館名から考えれば、温泉の質は期待できるはず。
なにより、湯本館の入口には、「湯本〇〇」という表札が堂々とかけられていた。これで、湯がよくないわけがない。
■湯は熱いけれど水は加えない
狙いは的中。15人は浸かれそうな円形の湯船には、宿の敷地内から湧出する約63℃の透明湯がかけ流しにされていた。やはり、「湯本」の名を冠した温泉宿にハズレは少ない。

無色透明の湯はアツアツで、湯船に入る瞬間はキリリとした緊張感が走るが、一度身を沈めてしまえば、スベスベとしたやわらかい湯に包まれる。まさにツンデレ系温泉である。
一緒に入浴したおじいさんは、「田植えシーズン前の時期は、英気を養うために毎年ここで湯治している」という。湯治とは、古くから行われている温泉療養の形式で、通常は数週間以上の長期間、温泉場に滞在し、心身の回復を図るものだ。日本の温泉の伝統的文化である湯治が、湯宿温泉には今なお生き続けている。
おじいさんは、「いろいろな温泉に入ってきたが、湯本館がいちばん。熱い湯なのに水を加えないのがいい」とも話してくれた。よく見ると、源泉はそのまま湯口に投入されずに、一度、湯船脇の石が転がるエリアに一度たまってから、湯船へと注がれる。これは、加水することなく、源泉を適温にする工夫である。ここに「湯本」としての美しきこだわりを垣間見たような気がした。