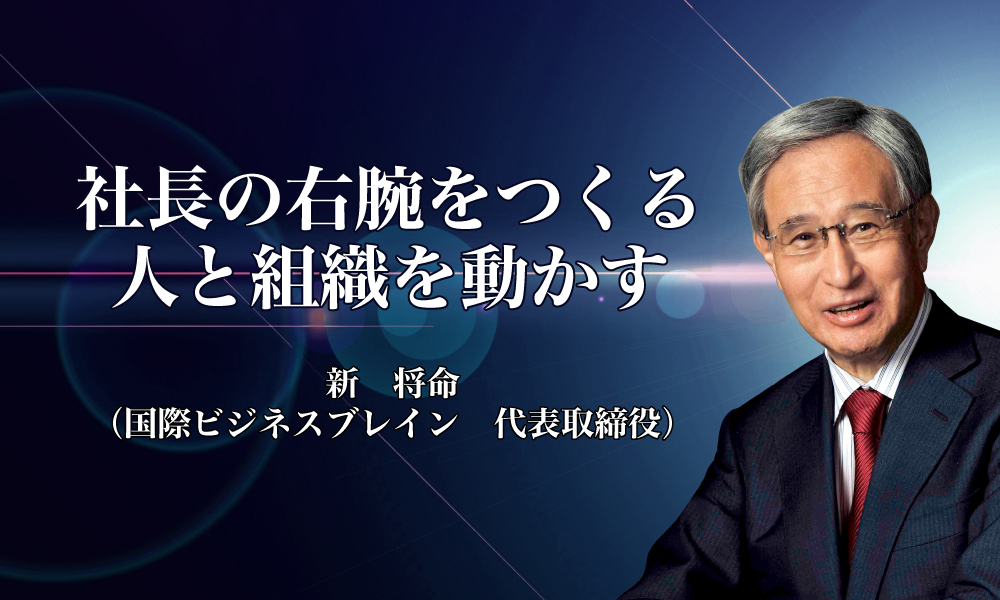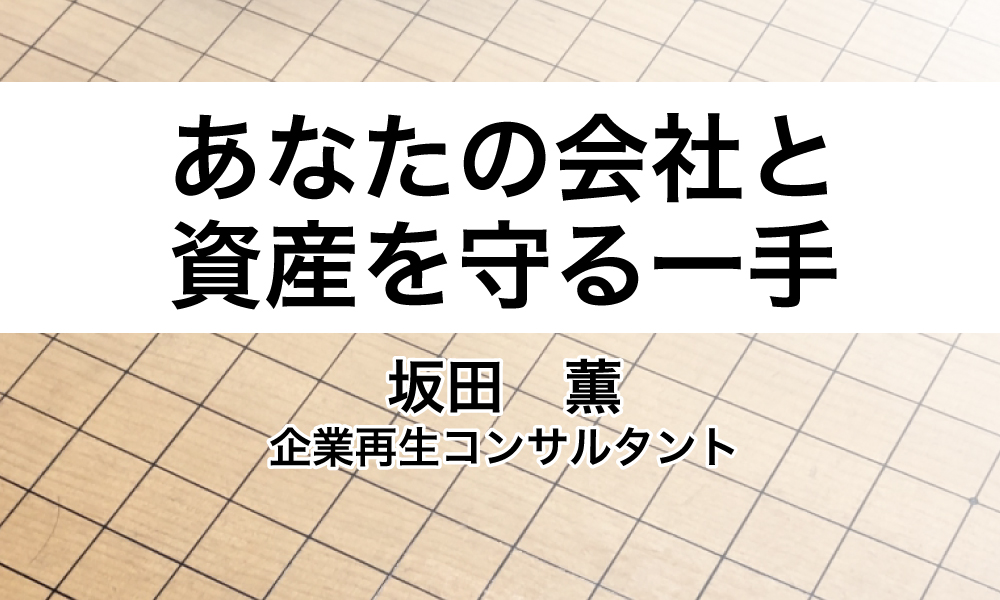- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 逆転の発想(46) 使える権威は利用する(織田信長)
下克上と新たな秩序
室町時代末期、戦国時代は足利将軍家の権威が失墜し、力あるものが思うままに、将軍が任命した守護に従う旧秩序による権力にとってかわる「下克上」の時代である。
その中に現れた風雲児、織田信長にしても、尾張守護代の家臣の家柄に過ぎなかったが、家督を継ぐや守護代家を討ち滅ぼして尾張一円の統治権を奪い取った成り上がりに過ぎなかった。
将軍家の権威が盛んだったころは、将軍―管領-各知行地の守護という権力構図が生きており、そのヒエラルキーの各段階での主君は家柄によって譜代の家臣を従え、家臣は、君主に忠誠を誓った。しかし、将軍家の掌握力が揺らぐと、君主と家臣の関係は、所領と保護という現実的、経済的な「恩恵」にのみ基づく関係に変わった。家柄による統治は過去のものとなった。恩恵が十分に与えられないなら、家臣は君主を裏切りその保護下から逃れ、あるいは取って代わって権力を奪う自由を得たことになる。
新時代の君主には家柄に代わる権力の掌握力が求められる。下克上の世は決して無秩序ではなく、新秩序を求め始めた。しかしその答えがまだ見えなかったに過ぎない。
信長の革新性
信長は、家柄に拘らない実力主義の人事で家臣団を束ね、新時代を切り開こうとしていた。直属の武力を失った将軍家は、こうして各地に勃興した戦国大名たちの武力に権威の確立を委ねざるを得なかった。逆に戦国大名たちはわずかながら残る将軍の権威を支えることで、領地の経営の安定を託したのである。
京都を追われ越前の朝倉義景に身を寄せていた将軍候補の足利義昭は、上洛して将軍権威の再興を目指す。朝倉義景ら多くの戦国大名が領国の経営を優先させて将軍上洛への武力提供に二の足を踏む中で、上洛同行を決断したのが信長だった。
経営の一線を退いたオーナー家の持ち株を取り込めば経営権掌握に利用できると踏んだのが取締役の一角に食い込み始めた新役員・信長の狙いであった。信長は、「将軍家の再興」を旗印に、義昭とともに岐阜城を出発し、近江から一気に京都に攻め上る。将軍の権威を笠に進軍する信長に道中、抵抗らしい抵抗はない。「腐っても鯛」である。将軍権威利用の思惑は功を奏することになる。
上洛を果たし15代将軍に就いた義昭は感激する。信長に副将軍、管領の地位を提案するが信長は拒絶する。畿内5か国の知行の提案も断った。「上洛した上は、実質的に天下に号令するのは自分だ」というのが、信長の狙いだった。上洛までの道中のために権威は利用するが、旧体制の権威に天下統一の力はないと見抜いていた。
過去の権威の限界を知りつつ利用し次の時代システムの構築を始める。これが信長の革新性である。
古い権威主義の限界
信長上洛に先立って京都、朝廷周辺の治安を握っていた三好長慶(みよし ながよし)、松永久秀(まつなが ひさひで)らは、不都合な将軍は殺害し、あるいは排除し、息のかかった将軍を操り人形として祭り上げようと画策し、失敗した。
信長を本能寺の変で滅ぼした明智光秀も、不安定な暫定政権を将軍の権威で維持しようとして挫折を味わう。機能しない権威は権力奪取に役立っても権力維持には無力である。
その後、天下を取るのは、関白・太閤という朝廷権威を手に入れて、名ばかりながら国家統治の大権威を手に入れて天皇・公家を手玉にとった豊臣秀吉と、将軍職に自ら就いて朝廷権威を凌ぐ実質権力を掌中にした徳川家康なのである。
権威は利用しつくすが、権威には利用されない──これが佳境に入った大河ドラマ『麒麟がくる』の鑑賞ポイントだ。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『現代語訳 信長公記』太田牛一著 中川太古訳 新人物文庫
『戦国時代』永原慶二著 講談社学術文庫
『織豊政権と江戸幕府』池上裕子著 講談社学術文庫