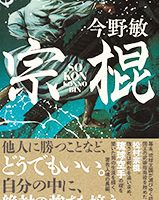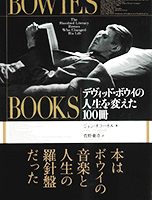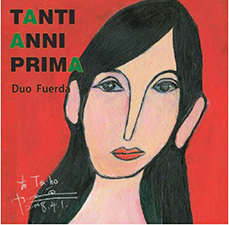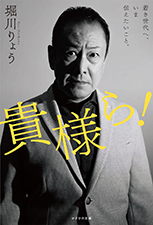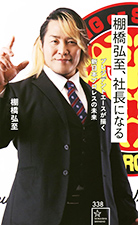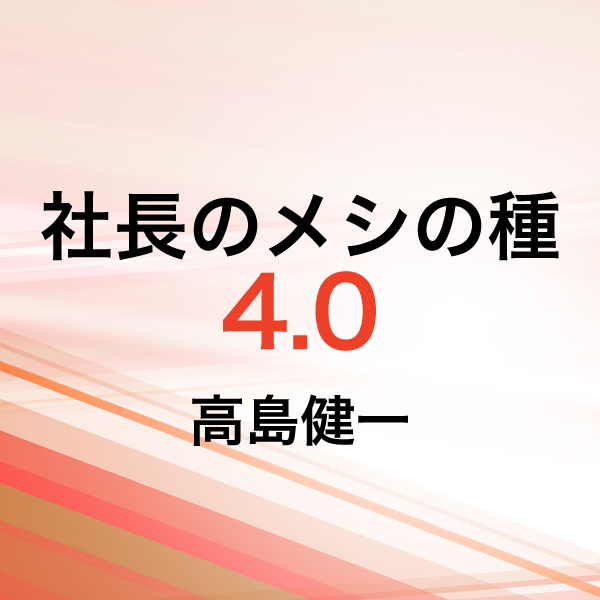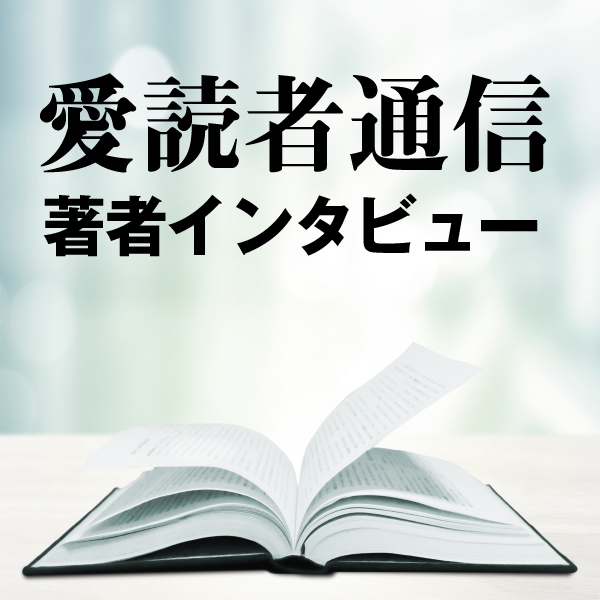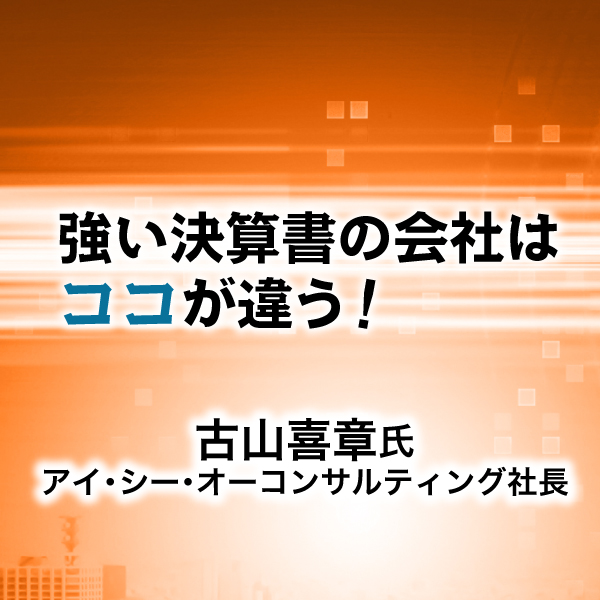楽聖バッハの名曲をジャズにアレンジしたアルバムは、
数多くあります。
中でも、秀逸だと感じるのが、
ルーマニア人ピアニスト、オイゲン・キケロによる、
『ジャズ・バッハ』です。
他の音楽家たちと一体どこに違いがあるのか?
アレンジの技術や演奏力は、そこまで違うとは思えません。
それどころか、技術的なことだけを見れば、キケロよりも上手い場合もあります。
しかし、彼を超えることはない。
いろいろ考えた結果、「観察力」が違うのではないか、と
思い至りました。
具体的にどこがどう違うとは言えないのですが、
楽曲、及びバッハを見つめる眼に、おそらく秘密があるはず。
それを知りたくて、繰り返し聴いてしまう。
そして、新たなコロナ禍とともに始まった2022年、
成功のカギを握るのは、やはり、「観察力」ではないかと思うのです。
先行き不透明な状況であるからこそ、一層、観察力がモノを言う!
そこで今回紹介するのが、
『観察力の鍛え方』(著:佐渡島庸平)
です。
観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか (SB新書)/amazonへ
著者の佐渡島氏は、
『宇宙兄弟』や『ドラゴン桜』などの大ヒット漫画の編集を手掛けた後、
クリエイターのエージェント会社・コルクを創業。
新たな時代のエンターテイメントをリードする存在として、注目を集めています。
本書は、数々のヒット作を生み出し続ける佐渡島氏が、あらゆる創作の根源となる
「観察力」について、詳述したもの。
さすがに、目の付け所が鋭い。
たとえば、
・観察を阻むものから考える
・「問い→ 仮説→ 観察」のサイクルを回す
・観察は、いかに歪むか
・成功者の話を真に受けすぎない
・問題の原因を人の能力に求めない
・感情を「情動」と「混合感情」に分ける
・「すること」と「いること」
…といったあたりは、経営者、リーダー必見!
観察力を高めるための具体的なアイデアも多く記載されていて、
すぐ実行できます。
同時に、「悪い観察を避ける」ための考察も見逃せません。
観察に際して、誰しも、何らかの形でバイアスがかかってしまいますので、
失点を最小限にするとともに、逆にそれを活かすことも考える。
その攻守の絶妙なバランス感覚も、大きな読みどころ。
観察力を鍛えるのに、うってつけの一冊です。
いぶし銀の玄人芸を堪能できます。
今の時代を乗り越え、そしてこれからの未来を見る、つくるために、
ぜひとも読んでみてください。
尚、本書を読む際に、おすすめの音楽はもちろん、
『ジャズ・バッハ』(演奏:オイゲン・キケロ)
です。
名人による名演の妙味、本書と合せてお楽しみいただければ幸いです。
では、また次回。