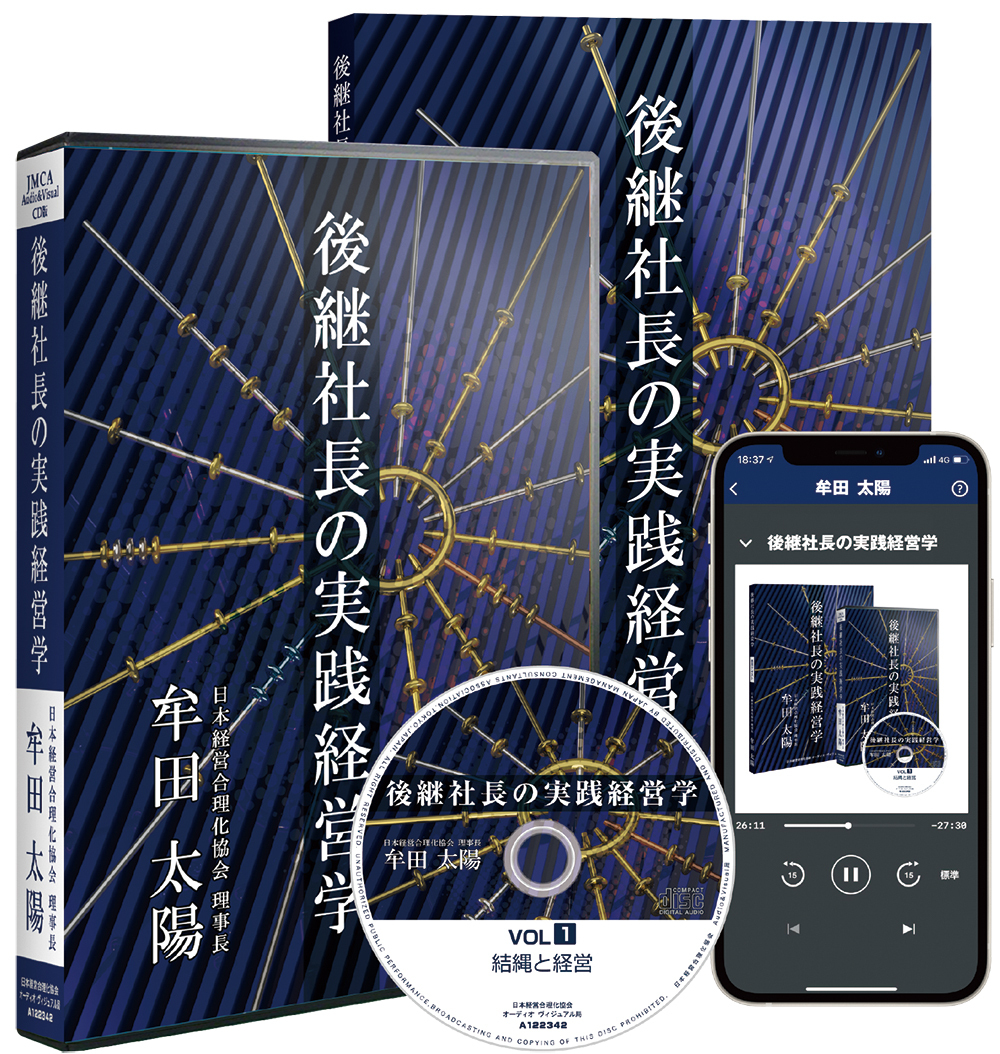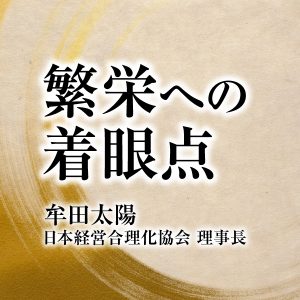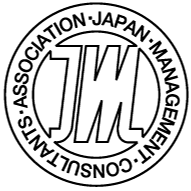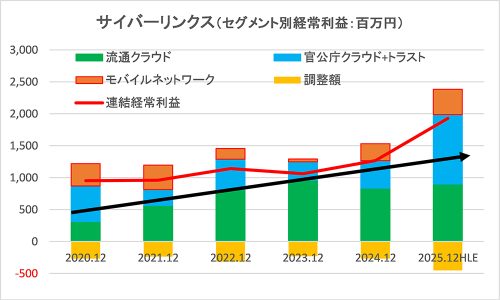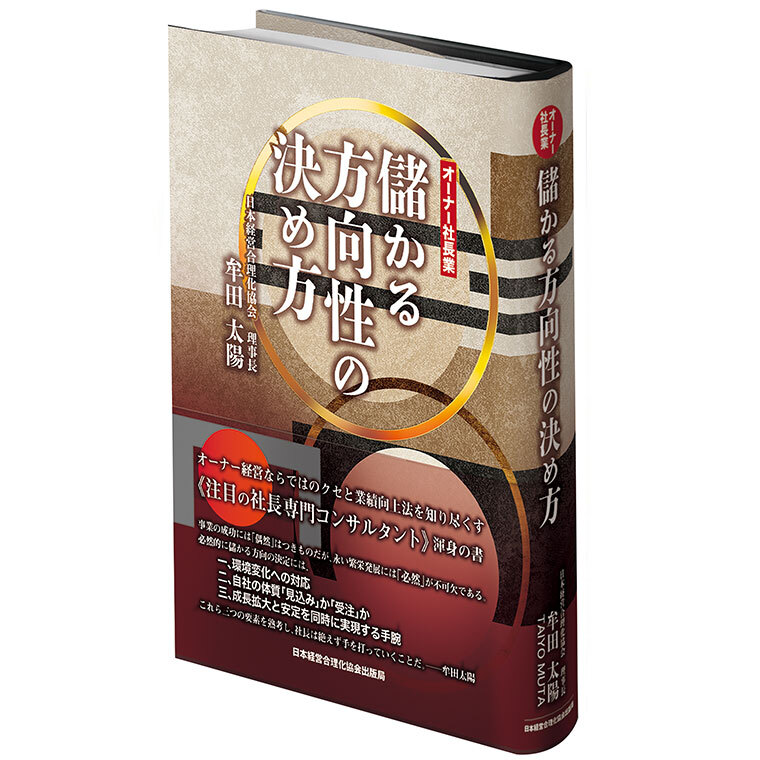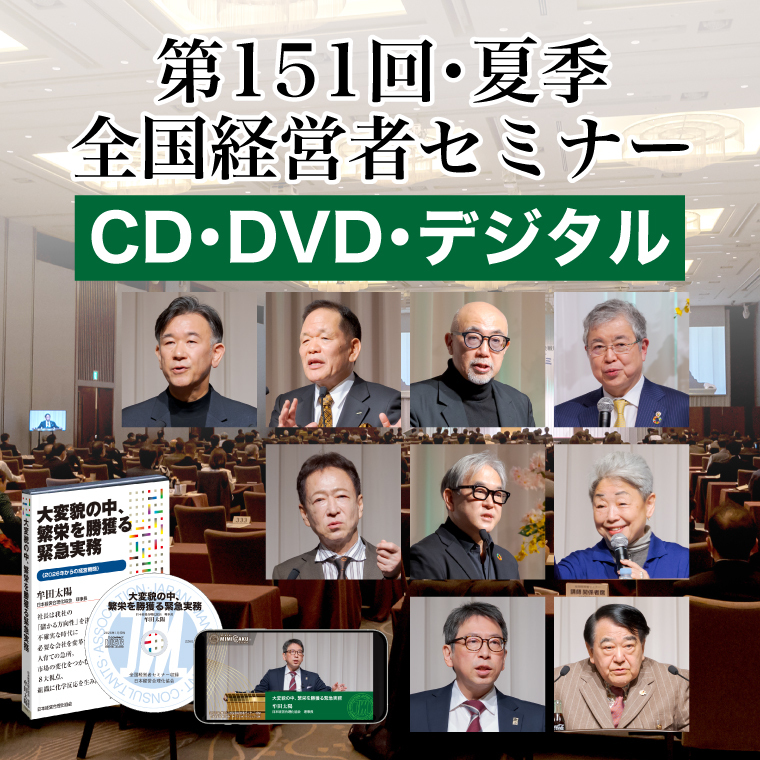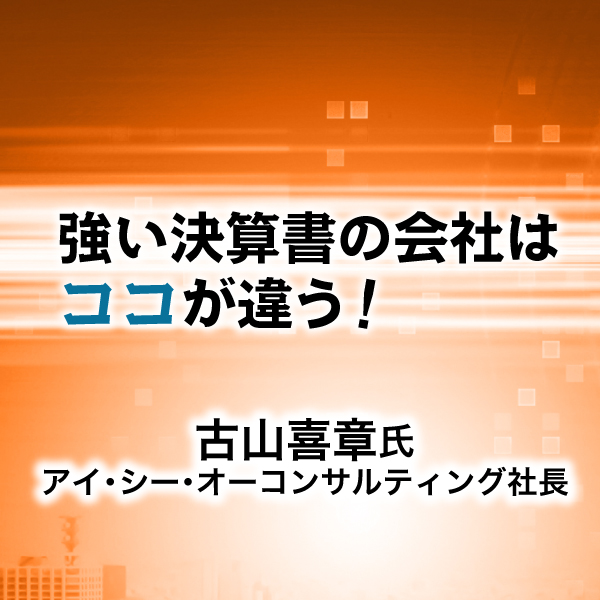※本コラムは2024年8月の繁栄への着眼点を掲載したものです。
自分の分身と3人の腹心、これが組織の最小単位である。
まず自分の分身とは、「社長の片腕」のことである。専務であるのか。副社長であるのか。自分がいないときに経営的判断ができる人がいるのかどうか。私の考えは、「いないよりはいた方が良い」というものだ。携帯電話の普及により、日本中何処にいても連絡はつくようになった。かつては、「日常業務から切り離して経営と向き合うように。直ぐに帰れない場所で」などと箱根やら、沖縄やら、初島などで合宿を開催したこともあった。それも交通網と情報網の発達で関係なくなってしまった。
それでも、海外などはいまでも別である。時差があるので連絡が取れない。または物理的に直ぐに帰れないなどの問題がある。その時に社長の代わりに経営の判断ができる者が社内にいないよりはいた方がいいだろう。食品関連など、人の口に入るものはなおさらである。そういった社長の片腕をまず探して育てること。
その下に、「作る」「売る」「分配する」この3人つくること。
「作る」とは製造部門のトップである。「売る」とは営業部門のトップである。「分配する」とは出た利益を分配する総務部門のトップである。この3人を揃えられるかどうかで会社の成長が決まる。これが組織の最小単位である。
もしこれを読まれているあなたの会社が売上10億円未満であるなら、この3人を揃えることでその壁を超えることができるはずだ。
そしてさらに重要なことは、「自分の分身と、3人の腹心」をつくり続けなくてはいけないことである。人間は誰もが平等で、一年経てば、一つ歳を取る。創業者が会社を設立して会社が大きくなっていくと何となく片腕や、3人の腹心が出来ていることがある。
しかし、自分の下の代の片腕や、3人の腹心まで考えている創業者は少ない。日本経営合理化協会でも、私が入協したとき牟田 學は61歳であった。大学の先輩、後輩であった「創業メンバー」といわれる世代は、私が入協して数年で全員定年退職でいなくなった。私が幸運であったのは、社内に熊谷、作間、岡田、成田などの次代の幹部が育っていたことだ。有難いと思う。
いま無門塾の参加者を見ていると、組織に対しても近視眼的に考えている人があまりに多い。創業者が考えていないのであれば、自分で片腕や3人の腹心を見つけ出し育てていかなくてはいけない。言うほど簡単なことではない。営業畑で育ってきた人は営業をえこひいきする癖があるし、製造畑で育ってきた人は製造をえこひいきする癖があるからだ。社長だってそうではないか。営業から現場を踏んできた二代目は営業ばかり強化するし、製造で現場を踏んできた二代目は製造ばかり強化するものだ。やはりそれではいけない。
これからの強い組織の特徴は、多様性である。かつては、「あの会社は金太郎アメみたいだ」という会社が多かった。「どこを切っても社長のクローンみたいな社員ばかり」というものだ。「イズム」が浸透しているという意味では決して悪いことではない。ただ、「これからの強い組織」は少し違う。金太郎アメは金太郎アメでも、切ったら違う表情が出てくる組織、切ったら違う味が出てくる組織でなくてはいけない。味とは、「特技」のことである。そういったバラエティー豊かな人材を揃えてほしい。人の差が会社の差である。それがこれからの組織である。
※本コラムは2024年8月の繁栄への着眼点を掲載したものです。