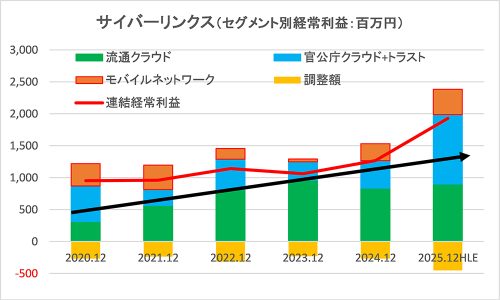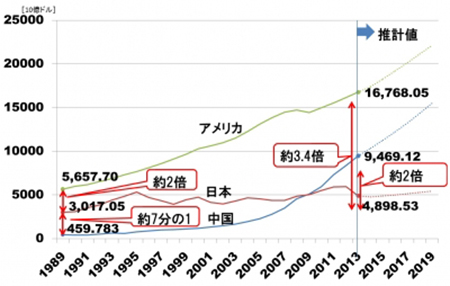「重い球」を投げ込んでくるビジネス書に向き合う
経営書のジャンルでは、その時点での時流に乗って多くの人々の興味関心を惹くテーマに狙いを定めた本が多い。これを書いている時点でいえば、DXとかESGとか働き方改革とかジョブ型雇用とか、そうした旬の話題についての本が次々に出てくる。
野球の投手に例えるならば、コントロール優先で球を置きにいくというタイプだ。確かに多くの経営者の関心事をとらえてはいるのだが、いかんせん球が軽い。この手の本は読んでもたいした意味はない。
一方で、鋭い考察や論理を教えてくれる良書がある。スライダーのキレがイイというタイプの経営書だ。経営にとって本質的な問題に正面から構え、骨太の議論を展開する。これは本格派の速球勝負の本といえる。
本格派経営書の傑作『会社という迷宮』
しばらく前に出版された石井光太郎『会社という迷宮』は本格派経営書の傑作だ。コントロール優先の凡庸な経営書の真逆を行く。球種はストレートのみ。ど真ん中の剛速球、しかも異様に球が重い。読んでいて手が痛くなる気がした。ここまで重い球を投げ込んでくるビジネス書は稀である。
経営戦略コンサルティングを仕事とする著者は、40年近くに亘って経営者との対話と重ねてきた。その中で「晴れることなく膨らみ続けてきた疑念とも違和とも悔悟ともつかぬ、モヤモヤと霧のかかったような思念を、何とか言葉に落として書きつけ」たのが本書だ。
外形的な基準に追い立てられ、ありもしない「正解」探しに明け暮れる経営に本来の自由意思を取り戻す――本書の主題は「経営における主観の復権」にある。著者から出てくる言葉は経営の本質を鋭く抉り出す。
あまりにも本質的であるがゆえに、経営者が見て見ぬふりをしてきた「核心」
しかし、それは「新奇な独創」ではない。言われてみればその通りだけれども、言われなければ分からない。あまりにも本質的であるがゆえに、経営者が見て見ぬふりをしてきた核心をストレートに衝く。経営の本質(だけ)を論じる本書は実質的にアフォリズムに近い。
「精神生活を語るためにあるのは、詩かアフォリズムかのいずれかだ」というエリック・ホッファーの言葉を想起させる。かといって、主張が押しつけがましくない。数多くの経営者と相対してきた著者の思考の試行錯誤をストレートに開陳している。
鱗が目を塞いでいるために、視野が狭まり、本来は見えるべきものが見えずにいる。その鱗を取り除くことによって、本来の経営のあるべき姿を正面から見せてくれる。本書を読んでいて、「目から鱗が落ちる」という実感があった。
会社は競争をするために生まれてきたのではない。志を実現するために競争しなければならなくなったというだけ――
多くの企業が戦略として公表しているものは、戦いの前に対外発表しているというその行為自体において戦略と呼べる代物ではない――
組織の存在理由が1+1>2であるとすると、人材の側から見れば、組織にいることで自分が1以上の働きができるということが組織にとどまっている条件となる――
市場は本来「いちば」。経済主体が縦横に動き回り、渉猟する中で、売り手と買い手の複雑かつ精妙な出会いが生まれる場――
市場は本来その会社の独創であり、独自の市場観がその会社を会社ならしめている――
国家と違い会社にはステイクホルダーに参入・退出の自由がある。利害を束ねるには、利害関係者を自由意思で凝集させるような柱を立てるしかない――
会社に目的(パーパス)が必要なのではない。そもそも目的があるから会社が生まれる――
痺れるような洞察の連続だ。一つ一つが経営者にとって血となり肉となるだろう。
決してとっつきやすい本ではないが、掛け値なしの名著。読後感は「参りました」の一言に尽きる。今年を代表する収穫といってよい。地味な本だが、発売以来よく売れている。コントロールを気にして球を置きにいかなくても、本当に良い本はきちんと売れるものだということを再確認した。
あらゆる経営者にじっくり読んでもらいたい本だ。副題は「経営者の眠れぬ夜のために」。あまりに考えさせられる本だけに、眠れぬ夜に読むとかえって眠れなくなるので要注意。